こんにゃちは、猫月です😸
この記事を書いているのは
3月も終盤に差し掛かろうという頃なのですが
あなたは年度末をどのようにお過ごしでしょうか?
保育準備としては、かなり忙しい時季ですよね
3月31日まで子どもたちは通ってきますし
4月1日には新年度が始まり新入園児もやってきます
保育園によっては入園式も催すでしょう
(うちの子の場合は初日から通常の登園でした)
保育士にとってはとても忙しい時季ですが
子どもたちにとってはどうでしょうか?
新入園児は泣きながらも保育者との関係を築き
在園児は進級してちょっと背筋をピンとしながら過ごしている
「ちょっと前までは、あの子たちが泣いていたのにね」
なんて大人の呟きも聞こえてきます
ところで、
年度末には『進級を喜ぶ』『期待を持つ』
等のねらいで保育をすることもあるかと思いますが
実際に進級をして新年度を迎えた子どもたちは
どのような思いで過ごしているのでしょうか

ひとつ大きくなったことを喜んで
新入園児にお兄さん・お姉さんとして
お手伝いしている姿がありますね

でも、進級したのに「保育園に行きたくない」って
保護者と離れない子もいるわよね
もうちょっと、しっかりして欲しい子もいるかなー

気持ちはわからなくないけれども
子どもは『進級した』ことをどう感じているのかな?
大人の思い込みで評価していないか、気を付けたいよね
新年度は大きく環境が変わります
保育者が忙しくしているということは
当然、毎日一緒に過ごしている子どもたちも感じています
「いつもと同じ」に過ごせるはず、ないですよね?
今回は、子どもにとっての新年度についてお話ししていきます
子どもにとって「入園」「進級」って?
子どもにとっての「入園」や「進級」って
どんな感覚なんでしょうね
こういう時、私は自身に置き換えて考えます
たとえば、「入園」は新しい環境へ飛び込むのですから
大人であれば、「入社・入職」ですよね
とても大きな環境変化ですから
子どもが激しく動揺するのも納得できると思います
では、「進級」は大人でたとえると何でしょう?
私は、「異動」や「転勤」に近いのかなと思っています
日々のタスクは同じだとしても
環境が変わればぎこちなく感じるものです
料理が得意な人だって
キッチンが変われば、調味料や食器の場所が違うので
スムースに調理するのは難しくなります
保育士だって、担任を持ち上がったとしても
新しい保育室や環境に慣れるまで
それなりに時間が掛かりますよね
大人の場合、先のことを想定して準備や心構えができますが
子どもの場合はそうはいきません
そもそも「入園」も「進級」も
子どもが望んで起こるイベントではないですしね
そういう引き起こされた状況の中で
子どもたちは適応しようとあくせくしているのです
そんな姿を見て「いつまでも泣いている」とか
「進級したのだから、しっかりして欲しい」というのは
なかなか酷な話だと思いますよ
自分が就職したばかりの心境や
異動や配置転属された時のことを考えたら
子どもの姿を、大らかな気持ちで受け止められるのではないでしょうか
子どもの“肌感”を尊重する
ある担任した3歳児クラスで
2月の下旬くらいから
『保育園に行きたくない』という子がいました
いわゆる“行き渋り”というやつです
登園拒否というほど大袈裟なものではなく
保育園へ来てしまえば
友だちと楽しそうに遊んでいます
『保育園ではあるあるですよね』
という見解もあるでしょうが、
“あるある”で済ませて良いものでしょうか?
子どもには、子どもなりの“理由”があるものです
ただ、そこは子どもですから
明確に「これ」と言葉に表せないことは多々あります
今回のケースで言うと
私が推測した理由は大きくふたつありました
・弟妹が4月に入園することが決まった
・「進級」という言葉が耳に入るようになった
私の勤める保育園では
2月末に入園面接が行われます
保護者は入園準備を始めますし
大人からも『(弟妹と)一緒に通うのね』という
何気ない言葉を頻繁にかけられるようになります
進級に関しても
「ひとつ大きくなるね」
「○○組さんになるね」
と大人は喜ばしいこととして声を掛けます
でも、これって子ども自身はどういう風に捉えているのでしょう
子どもが4月からの生活を見通しているのであれば
大人と同じく『嬉しいこと』と思うのでしょうけれど
見通しがはっきりしない場合は
『よくわからないけれど、大きな変化があるんだ』
『これまでとは違う毎日になるんだ』
と漠然と感じるのではないでしょうか
大人だって、先の見えないことは不安ですよね
それこそ『保育士になる』ことが決まったときに
「やったー!」という気持ちと
「どんな仕事をするんだろう…?」という気持ちと
どちらも正直な気持ちだったものです
子どもは経験が少ない分
未来に『期待を持つ』というのは
なかなかに難しいことだと思います
年度末の保育のねらいに
『進級へ期待を持つ』と入れがちですけれど
あれって、子どもからしたら
『“進級”って何?』
『ひとつ大きくなるってどういうこと?』
『弟妹が保育園へ来たら、自分はどうなるの?』
と思っているのかも知れません
もちろん、素直に『嬉しい!』と思っている子もいますから
期待も、不安も、子どもの感覚を尊重したいのです
「そうだね、大きくなるって嬉しいね」
「そうか、わからないって不安だよね」
そのどちらも、有り得るってことです
一括りに「進級は嬉しいこと」と決めつけないように
ひとりひとりの子どもの肌感を尊重したいものです
「今年もこの時期が来た」と思っているのは大人だけ
保育者の立場からすると
新年度を迎えるのは毎年のこと
なので、「今年もこの時期が来た」と感じます
新年度へ向けての準備とか
この時期に見られる子どもたちの姿とか
保護者へのケアやアプローチ
新入園児の受け入れなど
ある程度の算段をつけながら対応していきます
でも、ここで気を付けたいのは
「今年もこの時期が来た」と思っているのは
大人だけということです
子どもたちからすれば、
この新年度は”初めての新年度”です
もちろん、本当は大人にとっても初めての新年度なのですが
心理学の『ジャネーの法則』により
「今年も」と勘違いしがちなのです
※『ジャネーの法則』とは
時間の心理的な長さは若い頃に感じる時間は濃密で
大人になるにつれて時間が短く感じられるというものです
0歳から20歳までの体感時間と
20歳から80歳までの体感時間がほぼ同じとされます
「この新年度は初めての新年度」と子どもたちと関わるのと
「今年も来た新年度」と思って関わるのとでは
保育士の姿勢や態度は大きく変わるでしょう
「今年も」と思っていると
『進級したのに泣いている』とか
『自分でできることは自分でやって!』
などと子どもの姿を評価しがちです
でも、実際は「大人にとっても初めての新年度」なのです
だから、何となく心にさざ波が立つし
これまでと同じように保育をしようとしても身体が動かない
ちょっとしたミス…たとえば紙やペンの場所がわからないとか
そんなことの積み重ねで
「保育がうまく進まない」ということも起こるのです
そういう時に
「まぁ、新年度だもんね!仕方ない、気にしない」と考えるのか
「これまで通りに行かない…子どもたち、しっかりして!!」と捉えるのかで
以降の保育は大きく変わっていくでしょう
保育士が現状を受け入れ、受け止める姿勢を見せれば
子どもたちもアジャストしてくれると思います
他方、保育士が子どもたちの姿を否定的に捉えては
子どもたちは不安な心情で過ごす期間が長くなります
「今年も」ではなく
「初めての」として
子どもたちと新年度を迎える方が
保育士も子どもも、そして保護者も
新しい環境に馴染みやすいと、私は考えています
まずは“安心できる”環境を整えること
人間なら誰しも、自分の持っている力を発揮するには
リラックスしていることが大事です
子どもたちが新年度の環境でもこれまでと同様に生活するには
“安心できる”環境を整えることが最善だと思います
でも、“安心できる”って、どういうことなのでしょうか
私は、物理的環境と心理的環境から
アプローチするようにしています
安心できる物理的環境
とある私立保育園を見学した際に
3才以上になると『クラスがない』保育園がありました
決まっているのは個人のロッカーだけ
子どもたちは自分の過ごしたい場所で過ごし
給食は食堂で食べたい時間に食べる
午睡も午睡室があって眠りたい時に眠る
集団生活の時間もあって
その時は所属するグループ(異年齢構成)で活動するのですが
基本的には自由に子どもたちは過ごしています
保育は、アフォーダンス(そうしたくなるような環境)からアプローチする形ですね
この保育園でいえば
『素材室』という部屋を用意し
紙や木材、はさみやのこぎりなどを自由に使えるよう
環境を整え保育士を配置して
子どもがいつでも制作や表現遊びを行えるようにしています
『やりたい時にやりたいことができる』ことで
子どもが自ら遊びへ飛び込んでいくのです
見学をした際に印象的だったのは
ある3歳児の子どもが
遊びの中で服が汚れたからと
自分のロッカーへ行き着替えをしていたことです
生活のベースとして”自分の場所”が根付いていたのだと感じました
新年度を迎えても
パーソナルスペースであるロッカーはそのままですから
子どもにとっての“ホーム”はそのままです
そして、どの保育士とも関わるのが日常ですから
誰にでも自分を受け止めてもらえる環境です
この保育園の実践をすべて真似するのは難しいにしても
『ここは変わらず、自分の場所』という環境を目指せば
年度が変わったとしても
子どもたちの余計な不安は解消されるのではないでしょうか
安心できる心理的環境
新しい環境の中で
子どもも大人も実は漠然とした不安を抱えている
というのが私の認識なので
「しょうがないよねっ!」と口にするようにしています
「まだ慣れてないんだもん、しょうがないよね」
「初めてなんだもん、しょうがないよね」
「新入園児なんだもん、しょうがないよね」
ネガティブな意味合いではなくて
「この時期特有だからさ」といった感じでしょうか
思ったようにやれないのは
子どもも保育士も同じです
私だって、前のクラスへ行ってしまったり
新しい環境でティッシュの場所さえわからなかったり
小さなミスは山ほどあります
(元からウッカリなのは置いておくとして…)
新しい環境に馴染むには時間が掛かるのです
私としては2~3か月は見積もって良いと考えています
ざっと「夏前までに新クラスへ慣れたら万々歳」という感じです
「慣れるまで時間が掛かって当然」
「でも、段々と実力を発揮するよね」
という姿勢で子どもを見守っていることで
子どもたちも新しい環境でも
『自分でやってみようかな』と
チャレンジをしやすくなるのではないでしょうか
『まだ慌てるような時期じゃない』
『一本だ、落ち着いて一本いこう』
『まだ慌てるような時間じゃない』
某バスケットマンガの有名なセリフですね(笑)
私は、保育でもこの心構えが大事だと思っています
子どもたちの成長を見通す際に
「○歳児として、これができるようになって欲しい」と
年間の保育計画は立てていきます
ですが、それはあくまで目安であって
目の前の子どもたちに、成長の期待は持っているんだけれど
「落ち着いて一本いこう」です
今の子どもたちが達成できそうな遊びや生活習慣から
一歩一歩、着実に保育を進めていくのです
たとえば、4歳児クラスを担任していたら
「2歳の時は、大人に手伝ってもらいながらやっていたよね」
「3歳の時は、大人が傍にいれば自分でできたよね」
「今度は、自分で何をすれば良いかを考えられるようになって欲しい」
とこれまでの成長と、これからの期待を伝えるようにしています
もちろん、「手伝いはするよ」という見守りの姿勢を示しつつ
「ただ、自分から『手伝って』も言えるようになってね」
「みんななら、できると思っているよ」とも伝えます
実際のところは
3歳児時点で「今は何をする時か」は
自分たちで考えられるようになっているのです
ただし、いつでもどんな状況でもとまではいきませんから
たとえば着替えの始末を
これまで1週間のうち3日くらいは自分でやっていたところを
4日以上は自分で頑張ってもらいたいな、という願いを込めてです
これが、ちょっと見誤ると
「4歳児に進級したんだから、80%はできてもらわないと!」
と大人が意気込み過ぎてしまいます
4歳児の目標は、あくまで3月に達成していること
4月5月で成せるものではないと、心しておくものです
だから保護者会などでは
「今年1年間で、子どもたちに期待することです」と
保護者に対しても見通しを伝えるようにしています
公に伝えることで、保育士も保護者も
「3月までに達成すれば良いんだから」
と心情をフラットにできると思います
『進級する』という言葉だけで
何となく子どもたちが「ぐんと伸びた」と思い込んでしまいがちですからね
実際の子どもの成長は、毎日が右肩上がりではありませんし
成長しているがゆえに、大人を困らせるような姿も見せます
だから、「落ち着いて一本いこう」
『まだ、慌てるような時期じゃない』を心掛けるのです
「子どもたちと一緒に、“今できること”を重ねていきたいですね」
最後までお読みいただき
ありがとうございました
保育園で生活していると
進級のたびに、子どもたちの成長を感じます
それは、「昨年の今ごろは…」と
一年という時間の中での変化があるからです
ただ、忘れてはならないと思うのは
就学直前の子どもも、まだ6歳だということ
私は「もうすぐ小学生なんだから」よりも
「まだ6歳だもんね」という視点で
子どもたちを見つめるようにしています
子どもたちは確実に成長していますし
卒園後もきっと、歩みを続けてくれるはずです
でも、それでもやっぱり
人生はまだまだこれから
6歳には6歳の、ちょうどいい頑張りどころがあります
だから、大人の期待を必要以上に背負わせず
“今”という時間を大切にしたいと思うのです
大人の見通しは
子どもたちがこれから経験していく時間の
何倍もの月日を重ねて得てきたもの
だからこそ、0〜6歳の子どもたちに
その時間軸をそのまま当てはめないように
自分のまなざしを、いつも見直していたいと思っています
進級を一緒に喜ぶためにも
“今このときの姿”を大切にしながら
『明日はこんなことができるかもね♪』と
未来を楽しみにする気持ちを
子どもたちと分かち合っていけたらうれしいですね
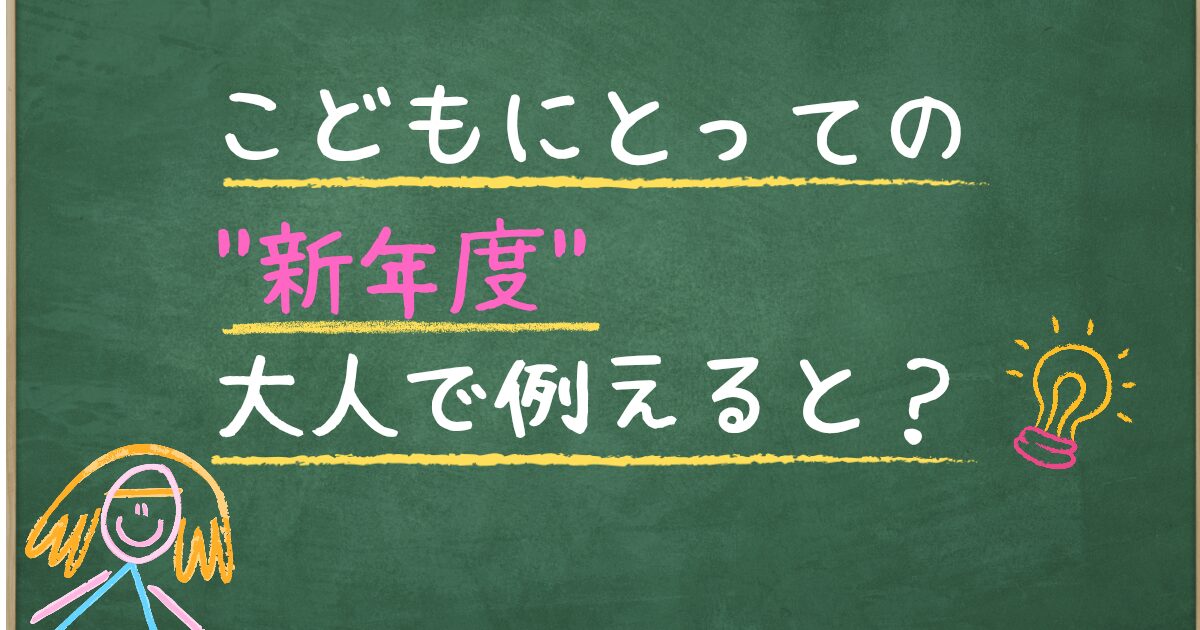
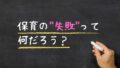

コメント