先日、できたら良いは「まだで良い」という記事を掲載しました
・ひらがなが書けた方が良い
・数がわかる方が良い
・椅子に座って過ごせる方が良い
・泳げた方が良い
・相手の気持ちを考えられる方が良い
記事中で、5つの具体例を挙げたのですが、
もう少し深掘りしていこうと思います
ということで、今回は
『数がわかる方が良い』について
お話ししていきます
結論から言うと、就学前に大切なのは
「速く計算すること」や「数字を書くこと」よりも、
生活の中で育つ数の概念
(量の感触・1対1対応・前後関係など)
がわかることです
🔽 マンカラは遊びながら数の概念が身につきます
就学前は、数の概念を育てたい
まず「数の概念」は、
“量と順番を数でとらえる力”のことです
算数の土台になる考え方で、
主に次の二つからできています
・集合数(基数)
「全部でいくつ?」をとらえる力です
たとえば─
りんごが3個なら、「3」は量そのものを表します
多い/少ないが分かることもここに含まれます
・順序数(序数)
「何番目?」をとらえる力です
「左から2番目のりんご」のように、
並びや位置を数で言えます
ここで大切なのは、
「数字(1,2,3…)を覚えること=数の概念」
とは異なるという点です
就学前に育てたいのは、次の“体験を伴う力”です
・数唱:1・2・3…と順に言える
・計数:実物を1つずつ数えて量と結びつける(1対1対応)
・数字の理解:記号としての「3」と、3個の量がつながる
幼児が数の概念を身につけるには、生活の中で
「どれだけあるか」「どっちが多いか」「何番目か」
を実際にやってみる経験が必要です
配膳で“1人に1つずつ”、
列で“前から3番目”、
片づけで“同じ数ずつ分ける”などが効果的です
この数の概念が十分に育っていると、
小学校で学ぶ計算や文章題にスムーズにつながります
言いかえると、
算数の前に身につけておきたい基盤
となる認識力です
3〜5歳の発達段階の目安
3〜5歳は、数を体験からことばへつないでいく時期です
「数=数字」ではなく、
「どれだけあるか/どっちが多いか/何番目か」
を考える感覚が少しずつ育ちます
※個人差は大きいです
3歳ごろ:数を“ことば(音)”として楽しむ時期
「いち、に、さん」と数唱を好みます(意味の理解はこれから)
量との対応はまだあいまいで、
3個と4個の違いさえ
わかりにくいことがあります
「りんご3つ」と言われても、
形や色に注意が向いてしまいやすい段階です
例:配膳で“1人に1つずつ”が大人の支えで成立する
4歳ごろ:数と“実物の量”がつながる時期
1〜10を順序よく数える場面が増えます
数字の形にも親しみが出てきます
「3つ」「4つ」の多い/少ないを比べやすくなります
言った最後の数=全部の数という“基数性”への気づきが育ちます
例:おやつを数え終えて「ぜんぶで5つ」とわかるようになります
5歳ごろ:数を“考えて使う”力が育つ時期
10のまとまりや、前後関係(1つ前or後)がわかってきます
「2と3で5」「5から2を取ると3」などの
分解・合成(加減の考え)に取り組みやすくなります
列や順序で「2番目・3番目」を理解し、
長さ比べも言葉で表しやすくなります
例:双六などで“+1/−1”の感覚が育ちます。
※「1〜99まで言える」などの暗唱は個人差が大きく、
暗唱=理解ではありません
量との結びつきを優先します
発達の特徴を要約すると──
・3歳:数を音として楽しむ段階(量の対応はこれから)
・4歳:量と数が結びつく段階(多い/少ない、基数性)
・5歳:数を考えて使う段階(分解・合成、前後関係)
観察チェック(この辺が見えたらOK)
・ものを配ったとき、数えた数と実物が一致しやすい(1対1対応)
・数え終わりの数を全体の量として使える(基数性)
・3〜5個は見ただけでわかることが増える(サビタイジング)
・「7は4と3」「6の1つ前は5」が言葉や動きで表せる(分解・合成/前後関係)
数の概念を身につけていくポイントは、
「数字を書く・速く解く」よりも、
「量の体験 → 言葉の順」で積み上げると、
あとで計算や文章題を考える力に
つながりやすくなります
幼児にとっての数は、生活の道具です
幼児が「数の概念」を身につけるには、
遊びやお手伝いなどを通して、
日常生活の中で数にふれることがいちばん自然で効果的です
特別な教材がなくても、
食事・遊び・外出の中にチャンスがたくさんあります
具体的な例を挙げてみましょう
「絵本を持ってくるから、30数えておいて」
ねらい:数唱の経験/待つ時間の見通し
やり方:「30数える間に持ってくるね!」と伝えます
大人がが一緒にゆっくり数えます
ポイント:10で区切る(10・20・30…)と目安にしやすいです
経験し初めの頃は5・10など短い数から
「もうじゅう狩り」ゲーム
ねらい:1対1対応/グループの大きさ=文字数の対応
やり方:「キリン!」→「キ・リ・ン」で3人組になる
ほかにも「サイ(2)」「カバ(2)」「チーター(4)」など
ポイント:人数が合わないときは保育者が入り調整します
文字数は2〜5文字くらいが楽しみやすいです
買い物の場面
ねらい:量の比較・計数/数字と量の結びつき
やり方:「6個入りの卵パックを探して」
「どっちのパンが多い?」など
買い物の手伝いをお願いします
ポイント:答え合わせは実物で確認できます
「家にある玉ねぎがあと3個」のように
残り量の言い方も取り入れます
配膳のお手伝い
ねらい:1対1対応/基数性(最後の数=全部の数)
やり方:「みんなに1つずつ配ってね」
配り終わりに「ぜんぶで何個だった?」と聞きます
ポイント:余りが出たら「どうして余ったかな?」を尋ねます
人数の増減で足す・引くの感覚が育ちます
他にも、トランプの「スピード」や
ボードゲームの「マンカラ」も
数の前後感覚(+1/-1)を含んだ遊びですね
「数を使うこと」を“勉強”ではなく、
“生活の一部”にするのがポイントです
毎日の中で、
量→対応→分解・合成→前後関係を
体験と会話で積み上げていきましょう
数が好きな子への関わり方
ひらがなと同様に、
数・数字に興味を持つ子もいますね
ちょっとした遊びをするだけでも、
子どもの数の概念は育ちます
たとえば、ままごとをする中で、
「コーヒー1杯と、ハンバーガー2つください」
「お寿司、イカ2貫とマグロ3貫をお願いします」
と注文をする
これだけで、数に触れる環境になるのです
食べた後に、
「そういえば、私なん貫食べたっけ?」と尋ねたら
『えーと、全部で5個だよ!』と答える
ちょっとしたクイズ遊びもできます
コップを2〜3個用意して、
それぞれに違う数のブロックを入れ
「どれが一番多くて、どれが一番少ない?」
とすれば、数量の考えにつながります
ドリルのような教材を使わなくても、
遊び・生活の中には“数”が溢れているものです
会話の中に、ちょっとしたエッセンスを加えるだけで、
子どもの興味は満たされ、さらに増していくでしょう
🎯 毎日伸びる数の力
生活には、数に関わる場面がたくさんあります
ドリルなどで勉強をしなくても、
数を「見る・比べる・分ける・数える・使う」体験は
日常にすでに用意されています
大人のひと言を少し意識するだけで、
子どもの数の概念は着実に育ち、
小学校での学びの土台になります
【今日からできる声かけ例】
・入浴で :「10数えたら上がろう」
・記念日で:「あと3回寝たらお誕生日だね」
・カレンダー:「今日は何日?」「遠足まであと何日?」
・並ぶ場面:「何人並んでいる?」「自分は何番目?」
・時計 :「長い針が9になったら出かけよう」(=あと15分)
毎日の何気ない風景の中で、数は自然に育ちます
量→対応→分解・合成→前後関係を、
体験と会話で少しずつ積み上げていきましょう
▶︎ できたら良いは、「まだで良い」
【焦らなくても大丈夫!】
#0 できたら良いは「まだで良い」──概要
#1 できたら良いは、「まだで良い」──ひらがなの話
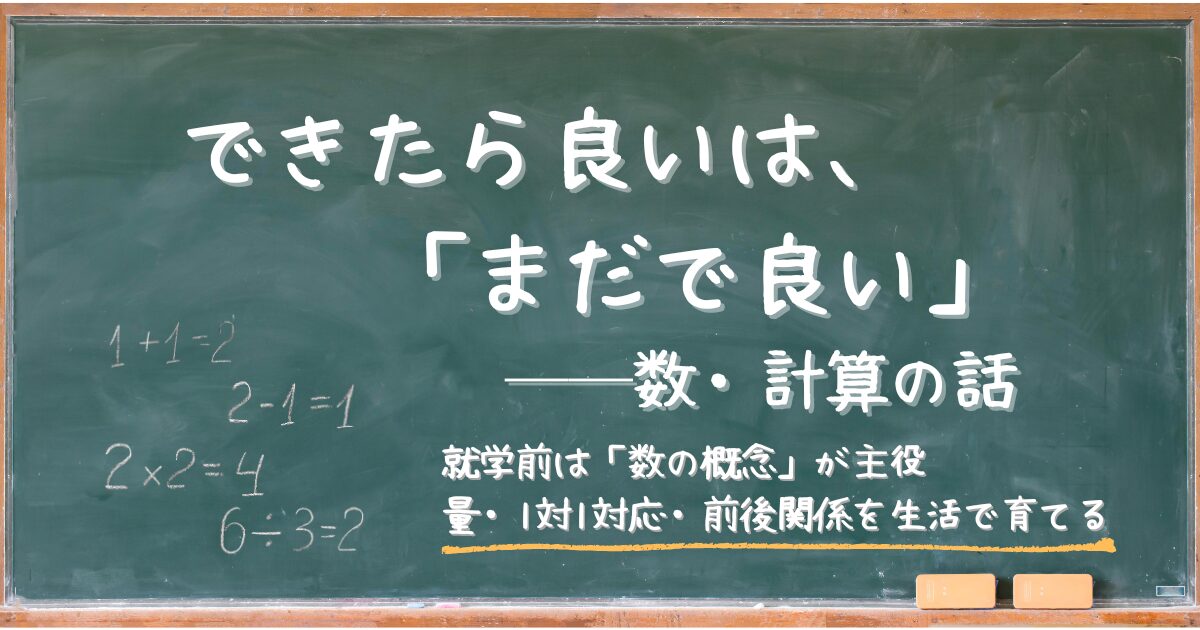
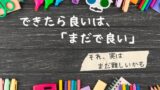

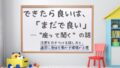
コメント