こんにゃちは、猫月です😺
保育園の生活の中で、
「小学校へ行ったときに困るから」という理由で、
子どもに“今のうちに”経験させようとする場面があります

猫さん、聞いてよ!
うちのクラス、“もう”4歳なのに
食べ物の好き嫌いが多いの!

“まだ”4歳児だよ?
子どもの発達的に、好き嫌いが減るのは
思春期を迎える頃だからね
食べ物の好き嫌いは、子どもの自然な姿です
幼児は、発達的に甘味を好み、苦味に敏感です
新しい食べ物を警戒する傾向(フード・ネオフォビア)は
2〜6歳で強く、年齢に伴って和らいでいきます
思春期ごろには味覚の感じ方や受け入れ幅が安定し、
「何でも食べられる」に近づくのは
学童期〜思春期にかけてが一般的です
だから就学前は「食べるよう促す」より、
【少量×繰り返し×楽しい体験】で“好きの芽”を増やすことが大切です
食べ物の好き嫌いに限らず、
大人の「できた方が良い」という思いから、
実は、まだその子は困難なことを、
求めている場面があるように感じます
私の感覚としては、
「できた方が良い」ことは
「まだ、できなくても良い」ことです
この記事では、保育園でよく見かける
「できた方が良い」を取り上げつつ
「まだ、できなくても大丈夫!」を考えていきます
🔽 「子どもと寄り添う」参考になります
ひらがなが書けた方が良い
『年長になったら、ひらがなは書けた方が良い』は
保育士の中でもよく耳にするフレーズです
でも、ひらがな・カタカナの習得は、
小学校1年生の範囲です
それは、学習指導要領にも記載されています
まず、「読む」ためには、
記号と文字の違いを区別できることが大事です
犬の絵を見て『ワンワン』と言うのと同様に
“あ”の字を見て『あ』と言うのは、
「読める」とは異なるのです
「書く」はさらに高度です
文字の形を認識した上で、
形をトレースする必要がありますからね
たとえば、幼児は鏡文字を書くことがありますが、
あれは間違えているのではなく、
左右の認識が未熟だからです
その段階の子どもには、
「正しく書く」ことは
脳の機能を超えた課題と言えるでしょう
幼児期は、言葉や音、
生活にある文字に関心を持つだけで十分です
絵本やポスター、商店のポップなどを、
「面白い」と感じられるように、
大人が一緒に楽しんでいくだけで十分なのです
数がわかる方が良い
小学校へ行くと算数が始まるからか、
幼児期から「数」を教えようとする方がいます
ですが、そもそも“数の概念”とはなんでしょうか
数字が読めることと、
10まで順番に数えられること(数唱)と、
数量(多い・少ない、大きい・小さいなど)とは、
別々の概念です
2歳児くらいになると、
1から10までを唱えられる子はいます
ですが、これは順序を覚えているだけで、
「4は1より大きい」とか
「5は7より小さい」という
数の概念がわかっているわけではありません
たとえば、数量の概念は難しくて、
同じ10個の石を並べていても、
間隔を広く並べたものと狭く並べたものだと、
広く並べた方を「多い」と感じるのが子どもです
『1+1は、2だよ!』
『100+100は200!!』と得意げな5歳児も、
計算をしているわけではありませんよね
ただ記憶しているだけです
まずは、数唱ができるようになり、
実際のものと数唱が対応できるようになること、
ものの多い・少ない、大きい・小さいがわかることなど、
生活の中で感じられることが大事です
「パパの方がご飯が多い」とか
「食べたら少なくなった!」とか
「みんなに2個ずつハンバーグをよそう」とか
数や量と近しくなっていけると良いですね
椅子に座って過ごせる方が良い
小学校の授業は、1コマ45分です
でも、45分間をずっと座っているのは、
実はかなり難しい所作になります
大人からすると、
「座っているだけ」と思いがちですが、
身体を静止させるという動作は、
筋肉を常に緊張させているということ
大人で例えるなら、
「ダンベルを持ち上げたまま45分間腕を下げずにいる」
それくらい難しいことです
実際の小学校では、
45分の授業の中でも、
こまめに子どもが立ち歩く機会を取り入れています
前に出るとか、手伝いをするとか、
隣の席と向き合うとか、
それとなく工夫をして過ごしています
45分間の座学をできるのは、
10歳以降といわれていますから、
欧米では児童が立ち歩くのは
自然な姿と考えられているそうです
これがなぜか、保育園では、
「部屋の中では座って遊びましょう」と
子どもに声をかける保育士がいるのです…
小学4年生でやっとできることをですよ?
5分間座って過ごすことができたら、
私なら拍手します👏
それくらい難しい所作ですからね
座って話を聞くなら、手短で簡潔に伝える
座っていても身体のどこかが動かせる遊びを用意する
室内でも動ける場を設ける
大人が環境を工夫することが大事です
泳げた方が良い
保育園の水遊びの中で、
「泳げるようになってから小学校へ」と
息巻く保育士がいます…
保育園はスイミングスクールではないですし、
そもそも小学校でも2年生までは、
“水遊び”を課程としています
幼児期は、思考よりも感覚が優位です
水が「怖い」「苦手」と感じたら、
そもそも意欲を失ってしまいます
小学校へのバトンを考えた場合、
幼児期に「水で遊ぶって楽しい」と感じて、
体育に臨めることが大事なのです
たとえ泳げなくても、水に潜れなくても、
「水遊びは面白い」
「水に入ると気持ち良い」
と子どもが感じられる体験を重ねたいですね
相手の気持ちを考えられる方が良い
私は常々同僚に、
「子どもに道徳を求めるのはやめよう」と伝えています
これは、道徳は不要という話ではなく、
幼児期にはまだ道徳の理解は難しいということです
ヒトは本来、主観的に物事を考えます
「相手の気持ちを想像する」と言いますが、
これも「自分だったら」という想像の延長であって、
相手の気持ちが実際にわかる人はいないのです
ですが、保育の中で、
「好き嫌いをしたら、給食さんが悲しいと思うよ」とか
「それをしたら、ママが泣くよ」とか
誰かの気持ちを想像するように求める声があるのです
私なら単純に、その子にとって
メリットかデメリットかで伝えます
「野菜も食べた方が、元気に過ごせるよ」とか
「それをしたら危ないよ」とかですね
好き嫌いをしたら、調理師が悲しむと言われても、
子どもからしたら「苦手なものは苦手」なんです
その上で、誰かの思いまで上乗せされたら?
より「ずーん…😰」とした気持ちになるんじゃないですかね
まだまだ幼児なんですから、
あくまでその子に矢印を向けた関わりを
心掛けたいですね
🎯「できたら良い」は「いつかはできる」
子どもの発達・成長を信じていれば、
「できたら良い」ことは、
「いつかはできる」ようになることばかりです
ひらがなも、数も、
座って過ごすことも、水泳も、
相手の気持ちを慮ることも、
相応の時期になれば、
環境の中で身についていきますよね
でも、相応の時期でないのに経験すると、
それはとても負担の強い事柄になってしまいます
子どもが自分から興味を持ったら、
きっと適切な時期がやってきたということでしょう
子どもの意欲が芽吹いた時に、
その意欲を発揮できるような環境の準備はしておく
私たちにできるのは、あくまで
子どもの「育ちたい」を支えることだと思います
先手、先手を打って、
「もーやだ!!」となってしまったら、
それは大人が成長の妨げをしているということです
子どもの成長を信じて、
ぐっと堪えて見守るのも、
また子どもへの温かい関わりなのだと思いますよ
【それぞれの内容をより詳しくお話ししています】
#1 できたら良いは、「まだで良い」──ひらがなの話
#2 できたら良いは、「まだで良い」──数・計算の話
#3 できたら良いは、「まだで良い」──座って聞くの話
#4 できたら良いは、「まだで良い」──水泳の話
#5 できたら良いは、「まだで良い」──“相手の気持ちを考える”話
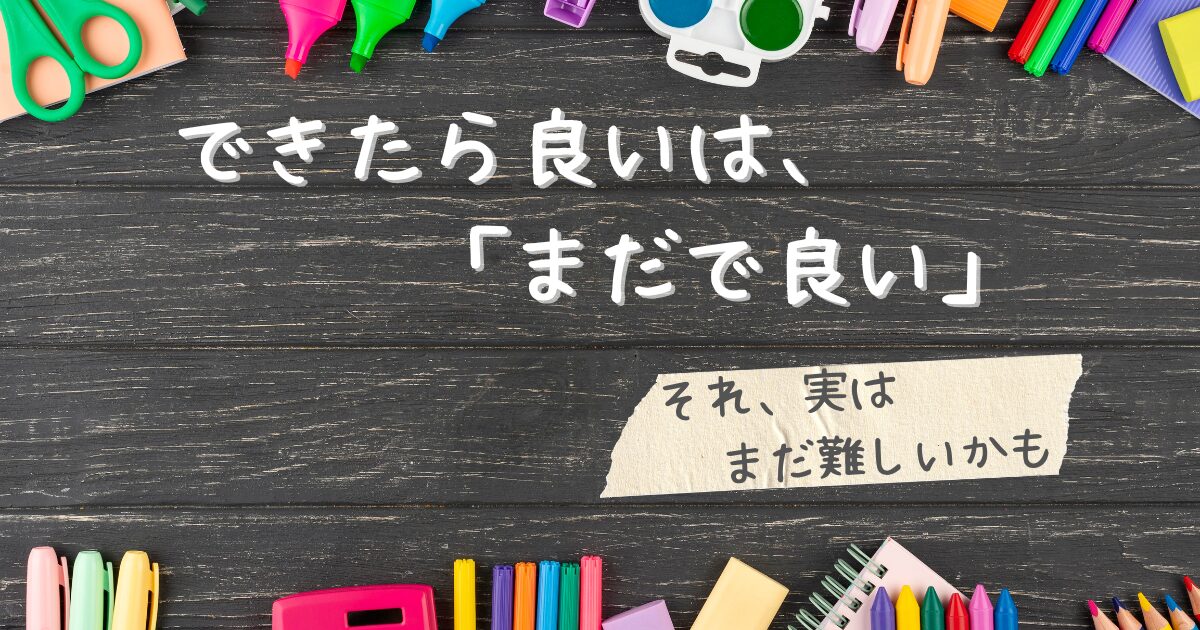
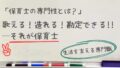

コメント