こんにゃちは、猫月です😺
保育士同士で関わる中で、
こんな声が聞こえてきました…

猫さん、聞いてよ!
まーだ、“保育士は遊んでるだけ”
って言う人がいるの…
どうしたら、私たちの専門性って伝わるのかしら?

そうだねぇ、わかってもらうのは難しいね…
“保育士になるために何を学んできたか”を
振り返ってみようか
きっと、自分たちの専門性の“幅”に、
改めて気づけると思うよ
保育士は「子どもと遊ぶ」だけの仕事と言われて、
歯噛みしたこともあるのではないでしょうか
そこで反論しようにも、具体的な説明が難しい…
日々の忙しさの中で、
「自分たちがどれだけ幅広い学びをしてきたか」
意外と忘れてしまっている人が多いのかもしれません
今日は、保育士になるために学んできたものを振り返り、
私たちが身につけている専門性を、
改めて認識する機会にしたいと思います
保育士資格は、“オールラウンド”な性格
保育士は国家資格です
つまり、「国が定めたカリキュラムを修めた上で認められる専門職」です
大学・短大・専門学校などで学ぶ内容を見てみると、
「保育」だけではなく、
「教育」「心理」「福祉」「医学」「芸術」と
幅広い分野を修学します
分野の広さに驚く人も多いでしょう
なぜこんなに多いのか?
それは──保育が「子どもの生活そのもの」を扱う仕事だからです
食べる・寝る・遊ぶ・笑う・泣く
そのすべてを支えるには、
ひとつの専門特化では難しいのです
実際に学ぶ科目を見てみよう
たとえば、保育士資格の取得に必要な科目には
こんなものがあります
🧠 心と発達を理解する分野
・保育原理
・発達心理学
・幼児理解
・人間関係
・保育者論
🏥 健康と安全を支える
・乳児保育
・小児医学
・栄養学
・健康運動科目
🏠 家庭と社会を支える
・社会的養護
・家庭福祉
・教育原理
・教育課程論
・福祉六法
🎨 感性と文化を育む
・児童文化
・音楽
・造形
・リズムなどの表現科目
👣 現場で学ぶ
・保育実習(保育所・福祉施設)
・実習指導
※私が履修した当時と科目名が違ったらごめんなさい🙇♂️
これで全部ではないですが、
それでも多岐に渡っていることがわかりますよね
こうして並べてみると、
保育士が学ぶ内容はまるで「人間の生活の縮図」そのもの。
まさに、“生活の専門職”を目指す学びです。
なぜ、こんなに多くの分野を学ぶのか?
子どもの「生活」を支えるということは、
身体の健康、心の成長、人との関係、社会とのつながり──
すべてが重なり合う世界全般を扱うということ
保育士は、子どもの暮らす世界を守るために、
医療・教育・福祉・心理など、
他分野の専門家と連携して動く存在だからです
そのためには、
「それぞれの入口」を知っている必要があります
病院、学校、地域や自治体、
場合によっては、児童相談所や法曹と関わることもあります
”いざ”というときのために、
それぞれの知識の端緒を握っておきたいのです
全分野で100点でなくてもいい
でも、60点(単位を収められる点)の知識を
広い分野で持っておくことで、
子どもの最適な支援につなげられるんです
専門的な学びを経て、あなたは“保育士”になっている
「学生のころの勉強なんて、もう忘れちゃったなぁ」
と思うかもしれません
でも、毎日の保育の中で、
あなたは確かにその学びを活かしているはずです
発達を見立てるとき
保護者に寄り添うとき
子どもの体調に気づくとき
そのすべてが、学んで身につけた
基礎的な力の延長線上にあります
あなたは今も、
子どもの“生活の専門家”として働いているんです
🎯保育士は“総合的な”専門家

こうして振り返ってみると、
私たちって、いろんなことを学んできたのねー
現場でどう活かしているのかも、考えたいわね

そうだね
子どもの“生活”を支える保育士は、
幅広く知識があることが大事なんだよ
保育士の役割は、
子どもの生活を全面的に
支援・援助することです
それは日常に根ざしたものなので、
端から見ると、特筆した専門性は見えづらいのでしょう
ただ、実際に必要とされる知識や技術を
学問として起こすと、
これまで見てきたように多岐に渡るのです
「遊んでいるだけ」に見える保育も、
その中には、人間の発達の理解があり、
子どもの発達に応じた関わり方や言葉選び、
提供する玩具や絵本、遊ばせ方まで、
細心の配慮があって保育をしています
世のお父さん・お母さんは、
子どもと過ごしていると、
ただ「遊ぶ」がいかに難しいかを、
ひしと感じていると思います(笑)
保育の総合的な内容については、
また機会のある時にお話ししましょう
🔽 法律を知っているのも、保育士の専門性の一つですね
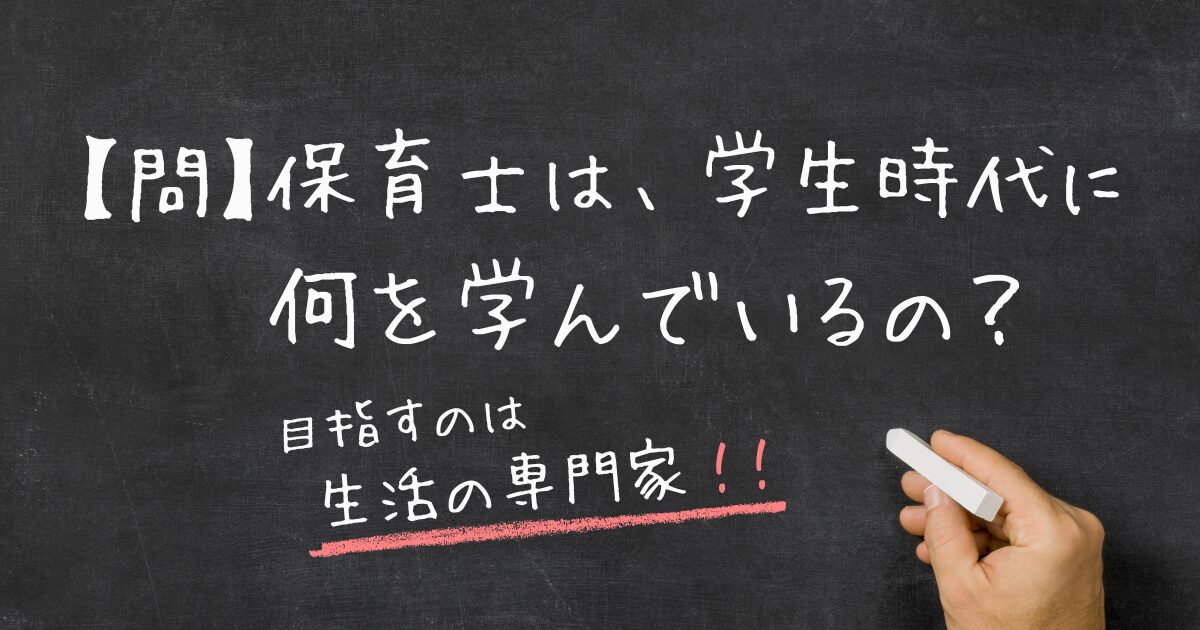

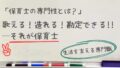
コメント