こんにゃちは、猫月です😺
子どもは好きな絵本の世界にのめり込みますね
身近なおもちゃを見立てながら、
ごっこ遊びで楽しむ姿もよく見かけます

でも、子どもの発想って
原作の内容とはかけ離れていきますよね…
発表会では保護者に見せられないかなー

んっ?ちょい待ち!
もしかして、発表会って、
絵本の原作通りに見せると思ってる???
発表会の相談事を聞いていると、
『絵本の内容通りに展開しないと、保護者がわからない』とか、
『子どもの発想を活かすために、オリジナルで創らないと…』
なんてことを耳にすることがあります
“原作のまま”か、“完全な創作”か
【0 or 100】と思っている方が
少なからずいらっしゃるみたいです💦
私は、子どもの発想は大事にしつつ、
原作をベースにアレンジして脚本を書くことが多いです
今回は、子どもたちが好きな絵本を、
劇ごっことして仕上げていくことについて、
実践例と合わせてお話ししていきます
アレンジには1〜99の選択肢がある
子どもたちのごっこ遊びは、
「絵本の通りにやる」か「完全オリジナルにする」か、
0か100かの二択ではありません
実際にはそのあいだに、
1〜99のアレンジの可能性が広がっています
例えば “おおきなかぶ” をアレンジする
「ばあさんやーい!」
『……』
「おや、今日は留守かいね?」
「まごやーい!」
『……』
「出掛けとるんかね?」
「犬やーい!」
『わん!』『あん!』『キャン!』
「えっ、うちには犬がこんなにおったがね?!」
“おおきなかぶ”の物語には則りつつ、
出てくる役や順序、数はアレンジされていますよね
これは、子どもの発想や様子によって変わってくるのです
子どもの発想で変わる流れ
ごっこあそび楽しんでいる子どもたちは、
物語を再現することを楽しんでいるわけではありません
あくまで、物語の中に入ることを楽しんでいるのです
保護者に観てもらいたいのは、
この「楽しんでいる」子どもたちの姿です
だから、子どもたちの発想を大事にしたい
子どもたちに合わせて、ごっこを展開したいのです
先ほどの“おおきなかぶ”でいえば、
その日にやりたい役をやるのも、
登場人物の出番の順序を変えるのも、
子どもに合わせたアレンジです
物語は原作を基盤にしながらも、
子どものやりたい役や気分で、
ごっこ遊びはアレンジされていくのです
発表会という非日常の中で
発表会は、子どもにとって特別な空間
緊張して出番に出られない子もいれば、
舞台袖でアイドリングしているうちに、
少しずつやる気が顔を覗かせる子もいます
先ほどの「ばあさんやーい!」「まごやーい!」に
前に出てこられなかった子がいたとして、
他の役の子が遊んでいる姿を眺めているうちに、
気持ちが乗ってくることもあります
「もう一度呼んでみようかね
ばあさんやーい!」
と呼び直せば『はーい』と平気な顔して
保護者の前に立つ子もいるんです
ごっこ遊びの“本質”って?
大切なのは、
「物語の通りに演じる」ことでも、
「全員が順番通りに登場する」ことでもなくって、
“子どもが楽しんで遊ぶ”ことですよね
発表会で観てもらいたいのは、
そういう子どもの姿です
その姿こそが、
子どもたちのごっこ遊びの本質であり、
1〜99のアレンジのどこに落ち着いても、
その価値が変わらないことです
アレンジにも“幅”がある
では、実際に保育で遊んだ例をお話ししていきましょう
ここでは3つの作品を
・『原作により近い演出』をしたもの
・『原作の設定を元に、子どもに合わせた演出』をしたもの
・『かなりオリジナルな演出』をしたもの
この順に紹介していきます
ももたろう(4歳児)の場合
▶️ 「ももたろう」さくらともこ・せべまさゆき(PHP研究所)
ほぼ絵本の内容通りに展開した事例です
さくらともこさんは、元園長&オペレッタ作家です
この絵本自体が台本として成立しているので、
くり返し読むうちにセリフが自然に根付きます
保育室に置いておくことで、
“遊びの延長”で進められました
絵本の内容が、子どもたちに定着した場合は、
そのままごっこ遊びとして展開できます
おむすびころりん(3歳児)の場合
▶️ 「おむすびころりん」さくらともこ・にしうちとしお(PHP研究所)
3歳児は発表会デビューの年
「全員が主役」で楽しめるように、
登場人物はネズミだけにしました
ハツカネズミ・ジャンガリアンハムスター・カピバラなど、
子どもたちと一緒に“ネズミの仲間”を調べて役を広げたのです
劇中では、穴に落ちてくる食材は
おむすびだけでなく卵やリンゴ、じゃがいもなど
「これで何を作ろうか?」と
子どもたちと発想をふくらませていきました
原作をベースにしながらも、
子どもの好奇心や
担任の願い(食育)を織り込んだアレンジです
本来の主人公であるおじいさんがいなくても
ごっこ遊びとして成立するのです
不思議の国のアリス(5歳児)の場合
▶️ 「不思議の国のアリス」ロバート サブダ(大日本絵画)
5歳児では、自由な創作が可能になります
題材に選んだのは、
何でも起こる世界観が魅力の『不思議の国のアリス』
セリフは子どもたちのアイデアを極力採用し、
当時流行していた芸人のギャグ(四千等身や夢屋まさる)も
セリフや演出として盛り込みました
もちろん、面白ければ良いというものでもないですから
早口言葉や回文、セリフしりとりなど、
「言葉あそび」をテーマに盛り込んだのです
原作を踏まえつつも、
子どもたち自身が“新しいアリスの世界”をつくり上げます
作品の中に飛び込んだ子どもたちのイメージを、
ごっこ遊びとして展開したのです
大人もアレンジして遊んでる?!
ごっこ遊びにおいて
「原作を大事にするべきだ」
という意見があるのも理解しています
原作者へのリスペクトですよね
ただ、アレンジは原作を壊しているのではなく、
楽しんでいるが故の“展開”だと思います
大人も、原作を元に2次展開させて楽しんでいますよね?
例えば、人気ゲーム『桃太郎電鉄』
▶️ 桃太郎電鉄2〜あなたの街もきっとある〜
この作品は、さくまあきらさんが
桃太郎を元に『桃太郎伝説』というRPGゲームを作成し、
それをさらにボードゲームとして展開したものです
『桃太郎伝説』には、桃太郎だけでなく、
金太郎、浦島太郎、かぐや姫などが、
昔話オールスターのように登場してきます
でも、原作を蔑ろにしているかといえば、
それぞれの設定や伝承を尊重しつつ、
再講話しているのです
原作が楽しいから、自分の世界観も湧き起こる
それが、アレンジする楽しさだと思います
絵本の読み方、アレンジしてるよね
『アレンジして良いのかな…』
『原作は大事だよね』
という相談から、今回の記事を書き始めたのですが、
「そもそも、作者の思う通りに絵本を読む」って、
難しいと思いますよ
以前、保育士仲間と“青空絵本会”を催しました
持ち寄った絵本をみんなで楽しもうという時間です
その時の感想としてあってのが、
『同じ絵本でも、読み手が違うと
物語の雰囲気が変わるよね』
というものでした
ひとつの例ですが、
『どこいったん』ジョン クラッセン/長谷川 義史(クレヨンハウス)
という絵本があります
タイトルからして関西弁調だと思いますよね
でも、大阪弁?奈良弁?…徳島弁かも?!
同じ関西圏の人でも読み方が変わってしまうんです
絵本を読む人によって、声や抑揚も違いますし、
そもそも感じている“面白み”も違うのですから、
同じに読むことなんてできませんよね
絵本を読むことですら、読者任せですから、
それをごっことして遊び、広げていくのは、
遊び手=子どもの感性に委ねて良いのだと思います
発表会で“見せたい”ものは?
さて、最後に発表会について触れていきます
あなたが、発表会で“見せたい”ものは何ですか?
保護者の方は、お子さんの何が“みたい”ですか?
『子どもが失敗したらどうしよう…』
こういう心配をする大人は、多いです
発表会の成功って?
私も保育士になったばかりの頃は、
セリフを正しく言うとか、
振り付けを間違えないようにとか、
そういうことにこだわっていました
でもね?それで正確な演技ができたとして、
子どもたちの顔が曇っていたら???
発表会は、子どもにも保護者にも、
保育士にも良い時間だったとは言えないですよね
“いつもと同じ”を心掛ける
私が発表会で心掛けているのは、
「いつもの子どもの姿」をどれだけ保護者に見てもらえるか
だと考えています
だから、子どもたちの様子に合わせて、
会場も遊戯室であったり、保育室であったり、
環境を大事にします
担任しているクラスだけ、
別にしてもらったこともあります
発表会の“目的”は?
私たちが間違えてはならないのは“保育の目的”です
上手な劇を見せたい・見たいのだったら、
劇団に入れば良いんです
でも、保育園の子どもたちは劇団員じゃない
会議でも毎年のように言います
「私は保育士です、劇団員と違います😊」
ごっこ遊びは、あくまで“遊び”です
発表会で見せたいのは、劇ではなく子どもの遊びなんです
子どもたちがどう楽しんでいるか
その楽しさをどう表現しているか
どう保護者と共有したがっているのか
そして保護者には、
「うちの子、楽しそう」を感じてもらいたい
だから、セリフを間違っても、
出番に前へ出てこられなくても、
何も問題ない
「失敗なんてない」を演出するのです
親子で楽しめたら、それが“成果”
発表会に“成否”があるとしたら、
親子が楽しめたかどうか、が水準じゃないでしょうか
笑顔がたくさん観られたら、
その発表会は成果を上げたのだと思います
人前に出るのが苦手な子はいます
そういう子を「前へ出られるように」とするよりも、
「その子が笑顔で過ごせるには?」を考えた方が、
保育士も子どもも楽しく過ごせると思います
ある年、セリフが言えなかった子がいました
でも楽器が好きだったので、
友だちの登場に合わせて「チーン!」とベルを鳴らす係を任せました
彼は堂々と舞台に立ち、誇らしげに役割を果たしました
家族も笑顔でその姿を見守ってくれました
目的さえ達成できれば、
手段は如何様にも工夫できるものです
親子が楽しむために、きっとやり方はあるはずです
🎯好きだからこそ、ごっこになる

絵本の原作通りじゃなくても、
発表会は成立するんですね
大事なのは“目的”かぁ…

絵本の世界観が好きだから、
子どもたちは自分もその世界に入ろうと、
ごっこ遊びをくり広げてるからね
私は、発表会のための準備は、
「子どもが好きになりそうな絵本」を
保育室に揃えることから始まると思っています
でも、思いもよらぬ絵本がブームになることもあります
どんな時でも、子どもたちがその絵本の、
何が好きなのか?どこを再現しているのか?
そういうところを観察します
衣装かもしれないし、
言葉の言い回しかもしれない
プリンセスなどへの憧れもあるでしょう
子どもの様子を見つめ、
その再現を手伝っていくうちに、
保護者にも楽しんでもらえるごっこ遊びになりますよ
だって、子どもたちが心から楽しんでいるんですから♪
日常のごっこ遊びを、
まずは子どもたちと目一杯楽しんでください
それが、発表会にもつながっていくはずです
▶ 各年齢で発表会に使った絵本たちです
【1・2歳児 ごっこ遊びと絵本たち シリーズ】
#1「おおきなかぶ」
#2「かくれんぼ ももんちゃん」
#3「3びきのこぶた」
#4「3びきのやぎのがらがらどん」
#5「てぶくろ」
【3・4・5歳児 ごっこ遊びと絵本たち】
3歳児 ごっこ遊びと絵本たち
4歳児 ごっこ遊びと絵本たち
5歳児 ごっこ遊びと絵本たち

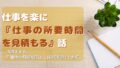

コメント