こんにゃちは、猫月です😺
『“○○な子”があらわれた!』では、
保育の現場でよくある
「こんな子、どう向き合う?」をRPG風に表現して、
ちょっとだけ“考えてみる”きっかけになればと思っています
今回も、日々の保育で出会いがちな
“ちょっと気になる子”をモチーフにしています
雑談のように、肩の力を抜いて読んでいただけたら嬉しいです☕️
さて、今回あらわれたのは……?
▶️ 遊んでいたマットの中に片付けちゃう
Chapter3 『かたづけをしない子が あらわれた!』どうする?

【あなたが保育をしていると、
“片付けをしない子”が現れました。どうしますか?】
「片付けて!」と言いたくなるけれど…
そろそろ次の活動に移ろうかと
「お片付けしてね〜」の呼び掛けに
遊び続けている子
大人としては「まぁまぁ、まだ遊びたいのかな?」と
ちょっと理解を示しつつも、
「それにしたって、毎回じゃない?」
「いつかは、素直に片付けてくれるのかな…」
なんて気持ちもありますよねぇ
もしかするとその子にとっては──
・遊びがまだ終わっていない
・実は遊ぼうと思っていたおもちゃがあった
・次の活動が魅力的じゃない
そんな理由があるのかもしれません
「まほう」をかけよう─子どもへの言葉掛け
「片付け」をして欲しいのは、
あくまで大人の都合です
だから「早く片付けて」ではなく、
・「片付けのお手伝いしてくれる?」と頼む
・「続きができるように飾っておこうか」と預かる
・「次に遊べるように“予約”しておく?」と約束する
そんな”ひと言”を加えると、
子どもの気持ちがふっと動くことがあります
「まほう」をかけておく─片付けの前に
「片付けるよ」とクラス全体へ声をかける前に、
私は下準備をしておきます
・「このおもちゃ、まだ使う?」
使わないものは、事前に大人が減らしておく
・「もう、これはおしまい?」
子どもの気持ちを確認し、意識の糸を切る
・「あと10分で片付けるから、やりたいものは今のうちに」
やり残しがないように、子どもに予告しておく
”片付け”は、整理整頓が整理整頓が成されれば良いと思っています
大人が9割片付けたって良いですし、
そのために子どもに断っておくのも大事でしょう
あと、子どもが気持ちよく次の活動に意識が向くように、
心残りがないように配慮もしたいですね
「片付け」と呼びかける前に、
もう片付けは始めておくのです
その子の“いま”を、尊重するために
「片付けをしない子」を前にすると、
つい「どうしてやらないの?」と
問い詰めたくなります
でも、その子にとっての
“片付けない理由”がちゃんとあるとしたら?
大人の都合だけで
「片付けて!」と迫ってしまうと、
子どもにとっては
「気持ちを切り替えるきっかけ」がつかめません
だからこそ──
🧙♂️ まほうをかけるように、気持ちをやわらかく包む言葉を
🪄 まほうを仕込むように、片付ける前の準備を
“片付けさせる”ではなく、
“次に向かえるようにする”
そんな視点があると、
子どもの行動も、大人の気持ちも、
ちょっとラクにしてくれますよ
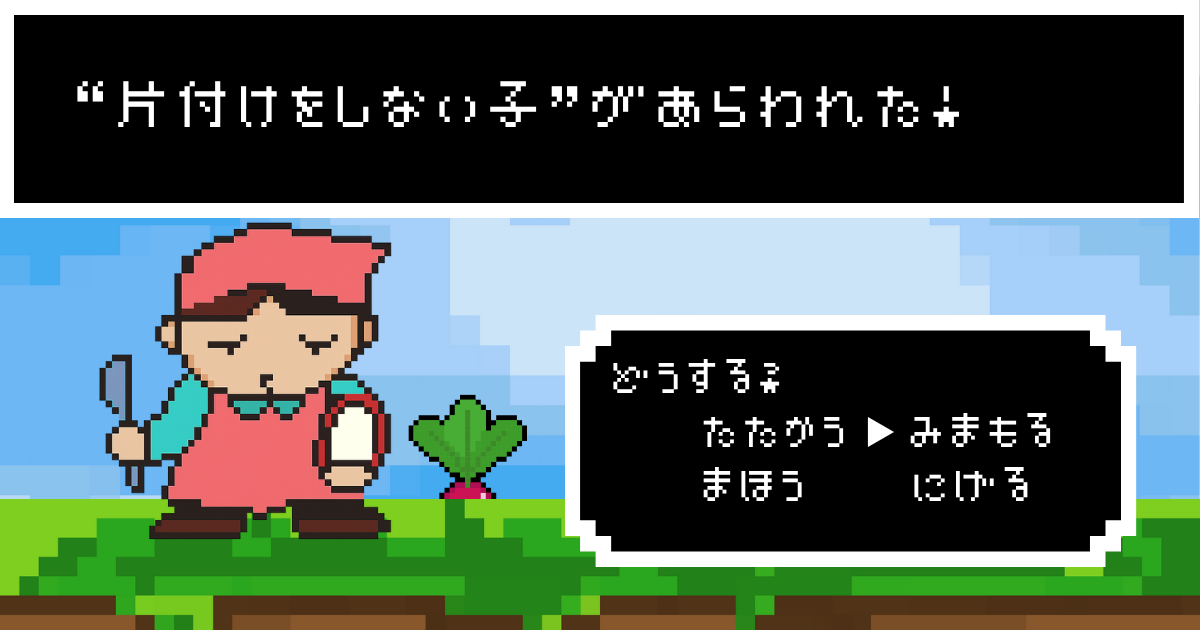


コメント