こんにゃちは、猫月です😺
『“○○な子”があらわれた!』では、
保育の現場でよくある
「こんなとき、どうする?」をRPG風に表現して、
ちょっとだけ“考えてみる”きっかけになればと思っています
今回も、日々の保育で出会いがちな
“ちょっと気になる子”をモチーフにしています
雑談のように、肩の力を抜いて読んでいただけたら嬉しいです🍵
さて、今回あらわれたのは……?
▶️ 適量な泡で手を洗えるように🫧
Chapter2『手洗いをやめない子が あらわれた!』どうする?
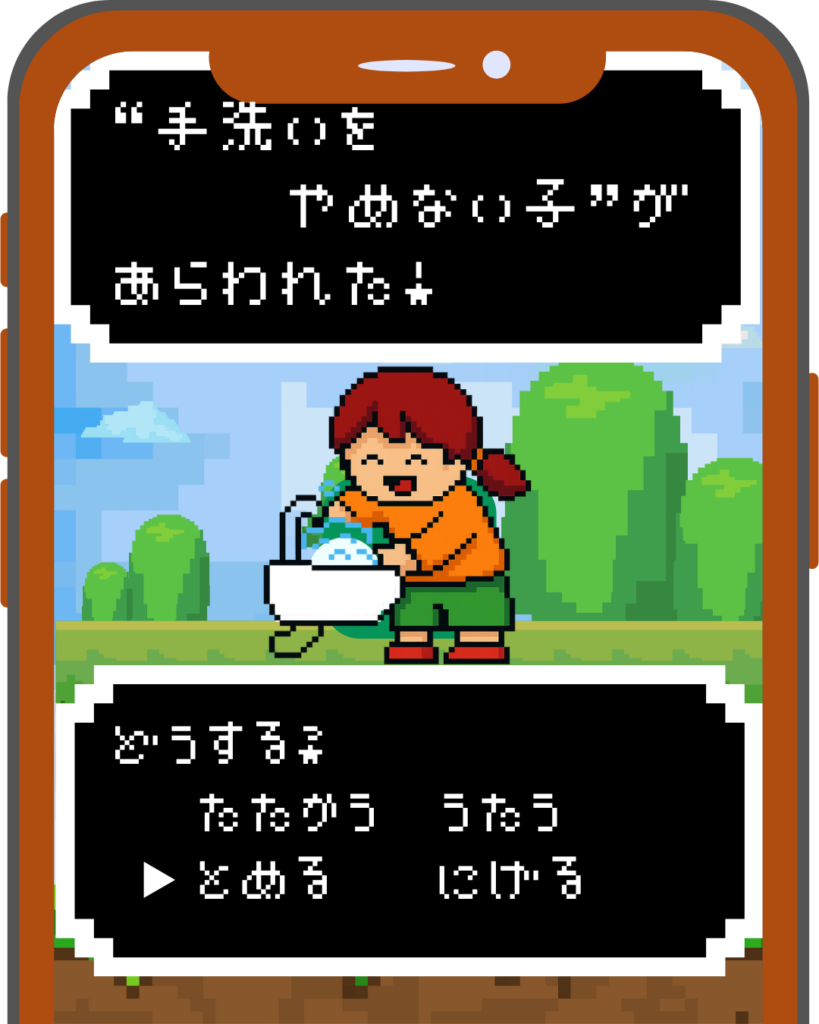
【あなたが保育をしていると、
“手洗いをやめない子”が現れました。どうしますか?】
“やりすぎてる?”が気になるのはなぜ?
手を洗うのは良いこと
でも、いつまでたっても蛇口の前から動かない…
「もうおしまいにしよ〜」と声をかけても、
水に触れるのが楽しくなって楽しくなっている
そんな姿に、ついイラっとしたこと、ありませんか?
そのイライラの正体って、
「手洗いじゃなくて、水遊びじゃん」とか
「他の子もいるのに、わがままでしょ」という
先入観だったりするかもしれません
その行動、何を表しているの?
・水の感触が心地よい
・泡の変化が好奇心を呼んでいる
・“ちゃんとやらなきゃ”という気持ち
・大人からの共感が欲しい
大人には「こだわり」とも見えるけど、
それって本人にとっては
”学び”や”探究心”や
”安心を得たい”のかもしれません
モラルよりも、“満たされる”関わりを
「ここでおしまい!」
「つぎのお友だちが待ってるから!」
と切ってしまうより
たとえば──
・「きれいに洗えたね」と認める
・「ピカピカのお手て見せて」と注目する
・「タオルも上手にできるかな」と促す
“大人が関心を寄せている”と安心があれば、
子ども自身が“気持ちを切り替える準備”がしやすくなります
『あわ あわ あわわぁ♪』
私は、子どもに手洗いを習慣づけてもらいたい時に、
子どもの手の平にハンドソープを載せて
両手を取りながら
♪あわ あわ あわわ(手の平の泡を見せる)
あわ あわ あわわぁ(手の甲の泡を見せる)
おみずを じゃー(蛇口を開く)
ゴシゴシゴシゴシ…(泡をすすぐ)
ほら、ピッカピカ!(水を切る)
と、節をつけて一緒に洗います
手洗いの動作を見せつつ、
行動の切れ目を伝えるのです
子どもが自分で手洗いをするようになると、
手洗いが水遊びになってしまう場面もあります
でも、そんな時はこの歌(?)を隣で口ずさむと、
子どもは自分で切り上げて、
ピカピカの手を見せてくれます
手洗いも強制しなくて済みますし、
子どもが満足して終えられる
と思っています
とめる?みとめる?─選んだその後の展開は?
こう関わるのが“正解”なんてものは、ありません
行動だけ見て「やりすぎ」と決めつけたら、
“子どもの思い”と“大人の正しさ”がぶつかります
でも、ちょっと見方を変えれば──
その子の好奇心や満足感が、
行動に表れているだけかもしれません
「止める」前に「なぜ?」を探る
そして「切り替えられる工夫」を
子どもと一緒に見つけてみましょう
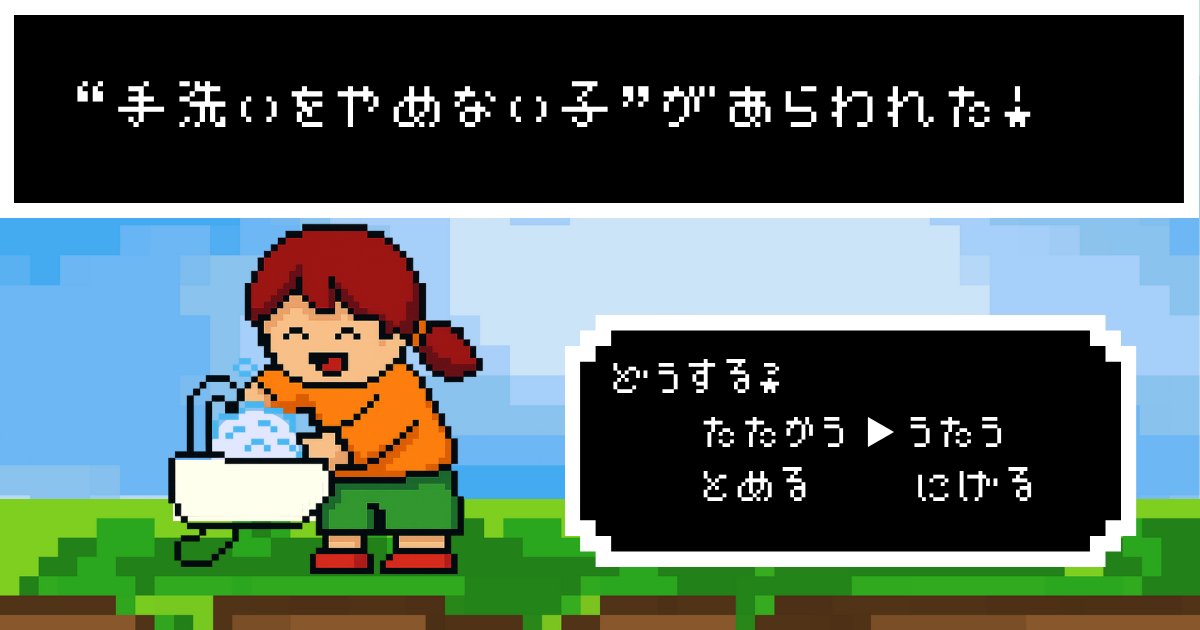


コメント