こんにゃちは、猫月です😺
先日、うちの職場でこんなやりとりがありました

手洗いの水で遊ばないよ
お水がもったいないでしょう!
後ろのお友だちがずっと待ってるよ!!

ムツキさん、まだ1歳の子ですよ
そんなにキツく言わなくても…

この子、いつも水道で遊ぶのよ
何回言ってもわからないの…
わかるまで言って聞かせないと!

たしかに、くり返してるんですけど…
う〜ん、どうしたら子どもに
わかってもらえるんでしょう?
子どもにやめて欲しいこと、
自分でやって欲しいこと、
家庭でも保育園でも、ありますよね
でも──
何回言っても同じことをする
最初は優しく伝えていたのに、
「こんなにくり返されたら、もうっ…💢」
と思うあの感じ
ところで、そこで強い言葉を使って、
子どもに伝わったことってありますか?
叱れば通じると思ってやってみても、
次の日には、また同じことをしていませんか?

・・・そうなのよ、
また同じことをするのよ

まぁ、そうだろうね(笑)
つまるところ、「子どもがわかる伝え方」を
考えていく必要があるんだよ
きっと、大人なら誰しも感じたことがあるでしょう
「何回言ったらわかるの?!」問題
今日は、この“魔のループ”を、
みなさんと一緒にほどいていきたいと思います
▶️ 叱らずに済む子育てを、行動心理学で解説する奥田健次先生の本です
なぜ?何回言っても伝わらない
「何回言っても、全然伝わらないんだけど…!」
そう思ったこと、ありませんか?
朝の支度で何度も促したり、
片付けは毎日声を掛けてたり、
危ないよと説明しても、また同じことをしたり…
一見すると、
「ちゃんと聞いてない」
「わかってない」
ように見えますよね
でも──
ここで、ひとつだけ考えてほしいことがあります
「何を伝えたいの?」が明確じゃない
大人からすると「簡単な話」のつもりでも、
子どもにとっては複雑な言葉があります
先ほどのムツキの言葉を借りましょう
「手洗いの水で遊ばないよ
お水がもったいないでしょう!
後ろのお友だちがずっと待ってるよ!!」
ムツキが子どもに伝えたい
“芯”は何でしょう?
おそらくは
「早く手洗いを済ませてほしい」
ただ、それだけです
ですが実際に口から出たのは──
・水で遊ばない
・水がもったいない
・友だちが待っている
この“3つの訴え”でした
子どもからすると、
「え…ムツキ先生は、何を言ってるの?」
という状態になります
その結果、
「何回言っても伝わらない」が起きてしまうのです
子どもが理解できる指示は“2つまで”と心得よ
OTの先生に伺ったところによると、
就学前の子どもが理解できる指示は多くて“2つまで”
さらに幼い年齢なら“1つ”が限界だそうです
つまり、ムツキの言葉は
子どもの処理できる容量(リソース)を、軽くオーバーしている
ということです
例えるなら、
コップの大きさよりも多量の水を
「何とか入るはず!」と注いでいるようなものです
「簡単に言ったつもり」は、大人の基準
よく大人は、
「そんな難しいこと、言ってないよ?」
「だって当たり前じゃない?」
と思いがちです
でも、子どもは発達の途中
大人の“簡単”は、子どもの“困難”です
大人なら手が届く荷物も、
子どもはジャンプしたって届かない
それと同じなのに、こと“言葉”となると
「大人と同じように理解できるはず」
と錯覚しがちなんです
意識したいのは「子どもにとっての情報量」
子どもと向き合うときに大切なのは、
・子どもに伝わる言葉で
・子どもに処理できる情報量で
伝えられているかどうか
ここがズレていると、
どれだけ優しく伝えても、どれだけくり返しても、
子どもは“処理しきれない”で終わってしまいます
子どもには、
“一番伝えたいこと”を伝えるように意識しましょう
じゃぁ、子どもに伝わる伝え方って?
子どもに何かを伝えるとき、
私がいつも心がけていることがあります
それは──
「子どもにとって、具体的に伝える」
ということです
「もちろん、そんなこと気をつけていますよ」
そう思われる方も多いでしょう
でもここで言う“具体的”とは、
大人にとっての具体ではなく、
子どもにとっての具体のことなんです
大人の“前”と、子どもの“前”は違う
例えば、子どもにこう声を掛けたとします
『ほら、前を向いて!』
大人がイメージしている“前”は、
「場所の正面」「先生の方」など、
文脈によって変わりますよね
でも子どもにとっての“前”は、
いつだって自分の正面
だから、『前を向いて』と言われたら、
“自分の前”を向いているつもりなのです
幼児を相手にするとき、大人は
「左右がわかりにくい」ことを前提にしますよね
でも実は、“前後”だって
年齢によっては抽象的なんです
方向を伝えるなら「具体的な見えるもの」で
なので私は、向きを伝えたいときには
「私の顔を見てください」
「テーブルとお腹を、ぴったんこ!」
などと、“実際に見えるもの・触れるもの”を使って
伝えるようにしています
「きれいにしよう」では伝わらない
これは方向だけの話ではありません
例えば、乳児に対して
『手をきれいにしよう』
と言っても、それがすぐに
“手を洗うこと”に結びつくとは限りません
そんなときは、
「お手て、アワアワしようね」
と伝えると、
手に泡をつける=手洗いをする
というイメージが、子どもの頭の中で鮮明になります
その体験と理解のくり返しが、
やがて「手をきれいに」=「手洗い」に
つながっていくのです
「子どもにとっての具体」を大切に
大人が言葉にしている“具体的”は、
子どもにとってはまだ抽象的なことがあります
だからこそ、
・子どもの見えるもの
・子どもの経験している行動
・子どもの今の理解段階
ここに寄り添った“具体的な言い方”を選ぶことが大切です
ここに気をつけるだけでも、
「伝わらない!」というフラストレーションは
ぐっと軽くなっていきます
「簡潔に伝える」って、どういうこと?
子どもに伝える時は、
子どものわかる具体的な言葉で
とお話ししました
ですが、
もっと簡潔な方法があります
何だと思いますか?
それは、「頷き」と「首振り」です
何気ない頷きで子どもを肯定する
子どもと目が合った時、
何かを言われなくても「うん」と頷く
とにかく肯定していく
そこには「楽しそうだね」「面白いことしてるね」を込めています
一方で、好ましくない行動をした時は、
首を振って「危ないよ」「それはよろしくないよ」を伝えます
ヒトは、ポジティブとネガティブを
7:1で覚えるそうです
「褒められた7回」と「叱られた1回」が釣り合う⚖️、とも言えます
何かを注意するためには、その前に7回は肯定していないと、
『自分はこの人に否定されている』と感じるわけですね
私はとにかく、何でも頷きます
目が合ったら、理由がなくても「うん」と頷く
「それで良いんだよ」をシャワーのように浴びせるのです
だからこそ、首を振った時に、
『あ、これはやっちゃいけないんだ』と
子どもは気づくのです
非言語の方が伝わることもある
面白いもので、
1歳になったばかりの子でも、
この頷きと首振りで理解してくれます
例えば、本棚によじ登ろうとしていた子がいて、
こちらをチラっと見る
私が首を振ると、
バツの悪そうな顔をしたり、
いたずらな笑みを見せたりしながらも、
棚から降りようとします
そこで降りた子に頷きを返すと、
笑いながら抱きついてきたりするのです
もちろん、これで通じるためには、
それまでのコミュニケーションの積み重ねがあってこそです
ただ、「子どもに伝わるように」工夫していくことが、
より“簡潔な伝え方”に繋がっていきます
「当たり前」にこそ注目する
アドラー心理学には
「当たり前のことにこそ、感謝をする」
という言葉があります
日常から相手に敬意を持って接することが、
私にとっても相手にとっても、
関係性を深め、互いの自己肯定感を育む
ということですね
頷き🙂↕️、サムアップ👍、OKサイン👌
相手を肯定する姿勢を持つことが、
大人も子どもも良好に過ごすためには、
大切だと思うのです
まずは、子どもに伝わる言葉選びをして関わる
その上で、より簡潔に伝えていくことを心がけていく
「真に伝えたいことだけを伝える」
「子どもを信頼する」
そこを意識したいですよね
🎯そうか、言葉は少なくて良いんだ
私も以前は、
子どもに言葉を尽くすことが大事だと思っていました
でも、言葉を尽くせば尽くすほど、
子どもは困惑していくのです
「どんな言葉なら、子どもに伝わるのだろう?」
そう考えるほど、霧の中にはまっていきます
そんな私が出会ったのが、
「子どもに伝わる情報は、ふたつまで」です
それでも、なかなか思った通りの反応が得られない
4、5歳児がやっぱり難しい顔をしている…
なんでだー?!
ここに、「保育を因数分解する」という、
今は私の十八番の考え方が加わります
大人は「ひとことだけ伝えている」つもりが、
実は複数の要素を含んでいることに気づくのです
例えば、トイレでの手洗いについて──
「トイレに行った後は手を洗って、しっかり拭いてきてね」
と伝えますよね
ところが子どもは、手洗いを忘れたり、
手が濡れたまま戻ってきたりするのです
大人からすると簡潔なつもりでも、
・トイレへ行く
・手を洗う
・水気を拭く
と3つの行動があるのです
因数分解した上で、
どうしたら伝わるか?を考えました
・部屋では「トイレに行こう」
・トイレでは「手を洗おう」
・洗い終わったら「手を拭いた?」
を伝えるようにしました
これだけで、子どもたちの姿が変わったのです
要は、一言で伝え切ろうというのは、
私が楽をしようとしただけなのです
必要な場面で、必要なことだけを伝えれば、
子どもたちには伝わるのです
常に言葉で伝えるわけではなくて、
ここで頷きと首振りが役立ちます
・トイレへ向かったら「うん」
・手を洗ったら「うん」
・手拭きを忘れたら?「ううん」
このやり取りで、子どもは気付きます
そして習慣づけば、大人の手を離れるのです
まとめとしては、長くなりました(笑)
・必要なことだけを伝える
・最優先事項を最優先に伝える」
・言葉をできるだけシンプルにする
これだけでも、幼い子にも伝わりやすくなります
「何回言ったらわかるの?!」と思ったら、
1回で伝わるだけの量に減らしてみてください
その子の姿を見つめれば、
その子に伝わる言葉の量もわかってきます
耳と目と心で「聴く」
それができれば──
大人が変わり、子どもも変わります
まずは、あなたが少しだけ
伝え方の工夫を始めてみませんか?
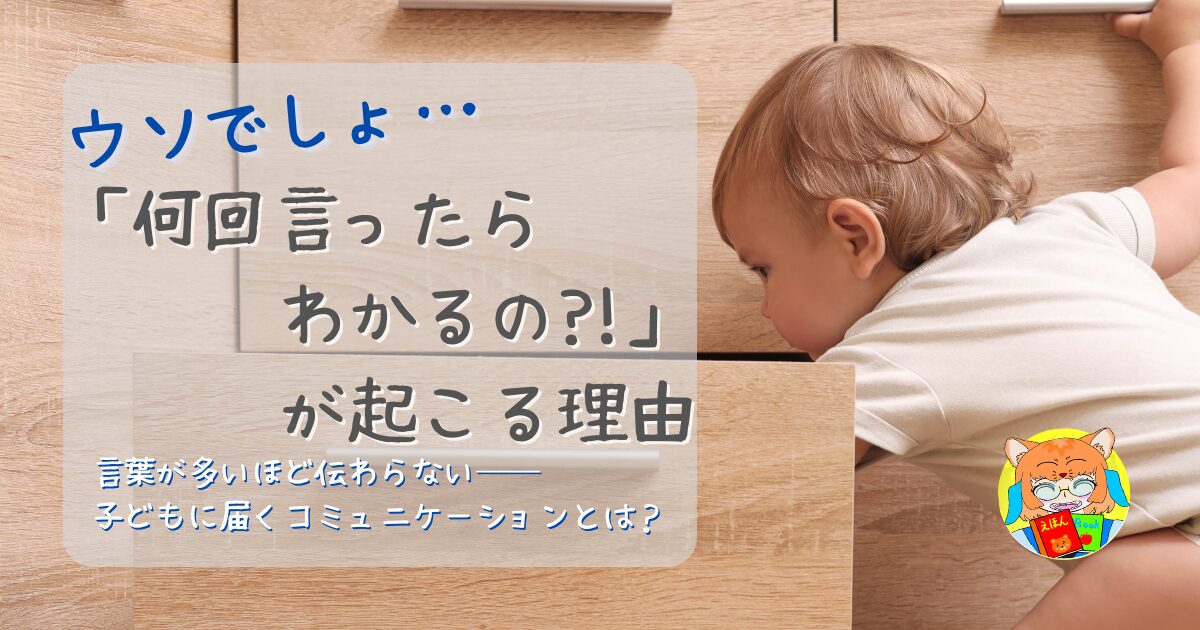


コメント