先日、できたら良いは「まだで良い」という記事を掲載しました
・ひらがなが書けた方が良い
・数がわかる方が良い
・椅子に座って過ごせる方が良い
・泳げた方が良い
・相手の気持ちを考えられる方が良い
記事中で、5つの具体例を挙げたのですが、
もう少し深掘りしていこうと思います
ということで、今回は
「椅子に座って過ごせる方が良い」について
特に「座って話を聞く」場面でお話ししていきます
🔽 理想的でも、どうにもならないことがあるんです!
就学前は、「話を聞いてくれた」と受け止めたい
就学前の子どもが
“じっと座って話を聞く”ことが難しいのには、
心理学的・身体的・神経生理学的な発達上の理由があります
これは「しつけ」や「やる気」の問題とは違って、
発達段階に応じた自然な特性なのです
発達的な理由(脳の未成熟)
幼児期は前頭前野(集中や自制に関わる領域)が発達途上です
長時間の注意持続が難しく、
「おもちゃが落ちた!」など
興味のある刺激にすぐ反応しやすい時期です
注意持続時間の目安
一般に、幼児の集中持続は5分程度、
小学校低学年でも10分程度が目安とされることがあります
※内容・環境で大きく変わります
「年齢+数分」程度の目安が語られることもありますが、
個人差が非常に大きい点を前提にします
「大人でも、集中の持続は22分が限界」と
私の大学の生物学の教授は仰っていましたね
身体的要因(体幹・感覚・姿勢)
体幹筋力や姿勢保持が発展途上のため、
同じ姿勢を保ち続けるのは負荷が高い行為です
前庭感覚(バランス)や感覚処理の特性も
「じっとしづらさ」に影響します
心理・環境的要因
音・光・掲示物などの
刺激が多いと注意が移りやすくなります
内容が長い、難しい場合も、
興味や理解が続きません
これは、大人でも同じですよね
短い話/静かな環境/関心に合う話材が、
子どもの集中には有効です
理解のポイント
・就学前は「座って聞く力」自体が発達途上
・集中の持続には年齢なりの自然な限界がある
・体幹、感覚、姿勢の未熟さが影響する
・環境調整と進行設計、適度な体の動きが、“聞けた体験”を増やす
「子どもがじっと座って話を聞けない」のは、
発達の自然な姿です
子どもに話を聞いてもらうには、
簡潔に、注目しやすい環境の中で、
子どもが聴きたくなるような内容を
伝えることが大事になってきます
「座って話を聞くこと」の発達段階(めやす)
※個人差は大きい前提です。数字は“最大”ではなく“目安レンジ”として
・1〜2歳(乳幼児後期)
自分で安定して座り続けるのは難しいです
短時間なら話に反応し、
興味のあるものには注目するが、
動きたがる時期なので、
2〜3分程度が限界です
・3歳(幼児前期)
一人で椅子に座り、
数分なら話を聞く姿勢を保てるようになってきます
興味がある話題や環境で約5分程度が目安です
座って聞くことに慣れる段階で、
ちょこちょこ動くのも自然な姿です
・4歳(幼児中期)
10分程度なら姿勢を保ちつつ話を聞ける場合があります
簡単な指示や物語なら理解しながら、
注意を向けることができるようになってきます
・5歳(幼児後期)
10〜15分程度、着席して話を聞ける力が発達してきます
気持ちのコントロールや
「着席する」という行動への理解も深まってきます
・小学校低学年(6〜8歳)
15〜20分くらいは着席して話を聞くことができるが、
まだ集中が途切れることもあります
活動の切り替えがある授業形式に対応しながら、
集中力を育てていく段階です
・小学校中学年(9〜10歳)
30〜45分間、
座って集中できる力がほぼついてきます
自己制御力や物事に集中する力が発達し、
「座って話を聞く」ことが一般的になります
以上のように、着席して話を聞く力は
年齢とともに徐々に伸び、
1〜2歳では短時間の反応、
幼児期で部分的集中、
小学校中学年で継続的な集中が発達していきます
椅子に座って話を聞けるのは、いつごろ?
上でも説明したように、
自分から集中して話を聞けるようになるのは、
小学校の中学年以降です
それも一つの目安であって、
集中力の持続や落ち着きの程度には個人差があります
実際には、小学校での授業も
細かい活動を組み合わせて、
集中力の波に合わせる工夫がされています
工夫例:ブロック設計(就学前)
・導入(短い話/キーワード3つ/見本提示)
・手元活動(触る・動かす・配る・並べる・書く)
・共有(見せ合い・発表・ペアトーク)
・姿勢リセット(立つ・伸びる・席替え・役割移動)
キーワードは「短く始めて、動いて、また座る」
これは大人でも同様で、
小さな集中の組み合わせで、
長時間の着席を成立させているのです
大人だって、集中は難しいものです
「つまらない」映画を、
最後まで見続けると想像してみてください
その時間は長く感じるでしょうし、
他のことばかりを考えてしまうでしょう
発達の目安は把握しつつも、
環境による影響が大きいことも、
意識していきたいですね
🎯とにかく「聞いてくれた」ことを認めていく
就学前は「座って聞けたか」より
「受け止めてくれたか」を評価軸にしたいです
作業療法士に聞いた話ですが──
どんな姿勢であっても、
大事なのは「話を聞こう」としていること
机にうつぶしていても、
足をブラブラさせていても、
こちらの話を聞いてくれれば、
目的は達成できているのです
そうなんです
「座って話を聞く」から難しくなるのです
私たち大人が本当に望んでいるのは、
子どもが話を聞いてくれること
ならば、聞いてくれた事実をまず認める——
それで十分です
「座って話を聞ける」のは、
就学してから数年後の話です
幼児期はまず「話を聞くって楽しい、面白い」を積み重ねる時期
その体験が、のちの姿勢・集中・学びを支える土台になります
▶︎ できたら良いは、「まだで良い」
【焦らなくても大丈夫!】
#0 できたら良いは「まだで良い」──概要
#1 できたら良いは、「まだで良い」──ひらがなの話
#2 できたら良いは、「まだで良い」──数・計算の話
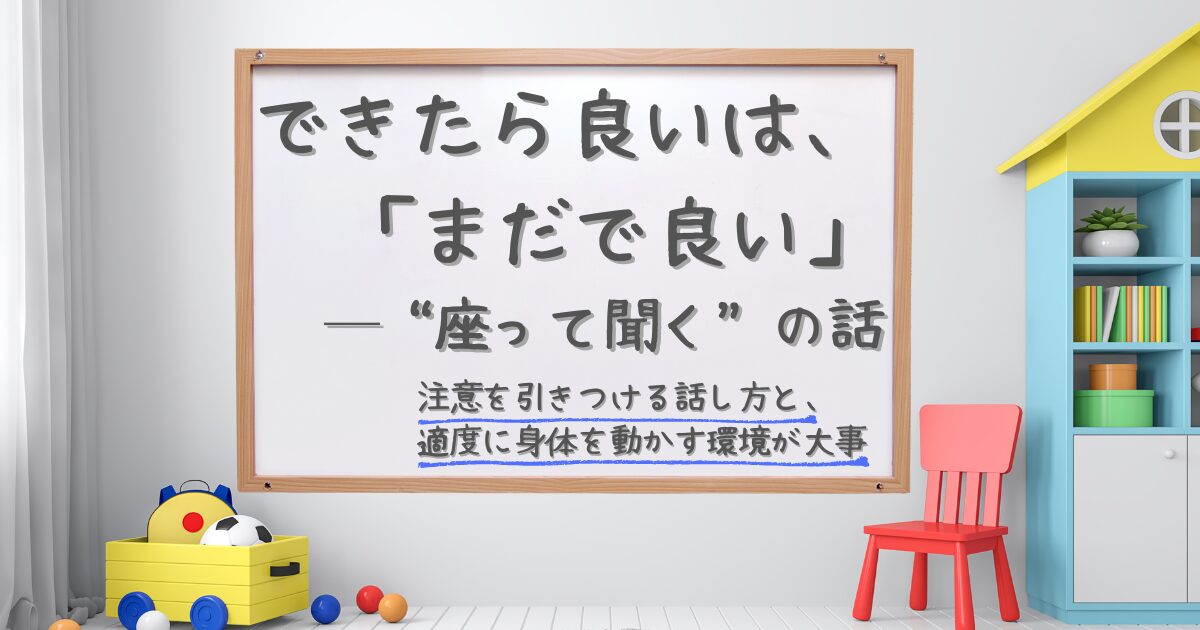
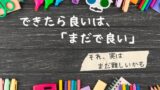
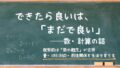

コメント