こんにゃちは、猫月です😸
新年度の始まり――
子どもたちは、期待と不安を胸に
一歩ずつ歩みを進めています
そんな子どもたちに
そっと寄り添ってくれる絵本を5冊、選んでみました
今回ご紹介するのは、その中の1冊――
中川李枝子さんによる名作『いやいやえん』です
絵本の紹介
『いやいやえん』
作: 中川 李枝子
絵: 大村 百合子
出版社: 福音館書店
あらすじ
「ちゅーりっぷ保育園」の年少組に通うしげるは
元気いっぱいですが、わがままできかんぼう
日常のささいなことにもしばしば
『いやだ、いやだ』と駄々をこねてしまいます
そんなある朝、しげるは顔も洗わず、着替えもせず、朝ご飯も食べずに
『いやだ』とごねています
その理由は、お父さんのお土産の自動車が
『赤は女の色だからいやだ』というものでした
はるのはるこ先生の勧めで
嫌いなことはせず好きなことだけをしていればよいという保育園
「いやいやえん」に通うことになりました
そこではしげるの『赤は女の子の色だからいやだ』という
わがままも許されるのですが…
猫月が魅力に感じるポイント
「いやいやえん」は絵本というよりも
児童書に近い作品です
本の中にはいくつものお話があって
表題の『いやいやえん』というお話もありますし
私が愛してやまない『くじらつり』のお話もあります
この『くじらつり』が
私とこの本の出逢いのきっかけでして…
東京都三鷹市にある「ジブリ美術館」では
ミニ映画が観られます
そこで『くじらつり』が上映されていたのです
宮崎作品として描かれていた、このお話しが
私にはとてもとても魅力的でして
では、原作も読んでみよう!となったのです
そして、原作の『くじらつり』が
まぁ面白いこと!
私の夢のひとつが
「いつか子どもたちと『くじらとり』をごっこ遊びで楽しみたい」
というものなのです
私も幼稚園時代は、毎日のように大型つみきで遊んでいました
そして、友だちと毎日ごっこ遊びに耽っていました
大型つみきは何でも作れますし、
ごっこ遊びで私たちには何にでもなることができました
あの時の子ども心を、そのまま表したかのような本なのです
この本は、読み切るには
とてもたくさんのお話がありますが
子どもが等身大の主人公たちと一緒に
物語に没入できる魅力があると思っています
子どもたちへの届け方
この本は児童書ですから
一緒に読む子どもも就学前が多いです
じっくりと集団で読み聞かせても
絵本の世界に入り込むことができるでしょう
また、この本には“スピン”がついています
栞のように読み途中に挟むひもですね
「続きは、また明日ね」を楽しめるのは
やっぱり年長児です
そういう「保育園で一番大きな子」とか
「もうすぐ小学生だね」ということを
暗に感じてもらえるのもの、魅力のひとつです
だから敢えて「今日は長いお話を読むよ」
「でも、みんななら“つづき”を待てるよね」
なんてくすぐりをいれてから読んだりします
加えて「つづき」という状況は
『この後どうなっちゃうんだろう?』
『こんなことが起きちゃうのかな⁈』
という子どもの想像力を掻き立てます
ゆっくりじっくり、読み込む楽しさが
この本にはあると思っています
「子どもはみんな問題児。」を読むと、もっと好きになる
「子どもはみんな問題児。」
著: 中川 李枝子
出版社: 新潮社
「いやいやえん」を読んでいて
不思議に思ったことがあります
この本にはたくさんの話があるのですが
長さがどれもまちまちなのです
それともうひとつ
私はよく絵本の分析をしますが
この本の物語には
統一された作品感やメッセージ性のようなものが感じられません
本当に、子どもと等身大な感じの作風なのです
その私の疑問に、中川李枝子さんが回答してくれました
それが「子どもはみんな問題児。」です
中川さんは、かつては保育士でした
そして、雨の日などに
子どもたちと「お話し作り」で遊んでいたそうです
そこで生まれた数々のお話が
「いやいやえん」に登場するたくさんの物語です
「子どもはみんな問題児。」の中で
中川さんは当時のエピソードや
卒園児と成人した後に再会した逸話などを
お話ししてくれています
保育士と子どもたちで即興で作ったお話しですから
物語の長さがまちまちなのも
子どもと等身大なのも納得です
この本を子どもたちと読むとき
私は秘かに願いを掛けています
「あなたたちも、友だちとたくさんの物語を紡げますように」って
「いやいやえん」ほどぶっ飛んだ保育園ではありませんが
子ども同士が集まれば
きっと毎日のように面白い物語が生まれるでしょう
本として形にはならないかも知れませんが
子どもたちの心に、大人になっても語りたい出来事がありますように
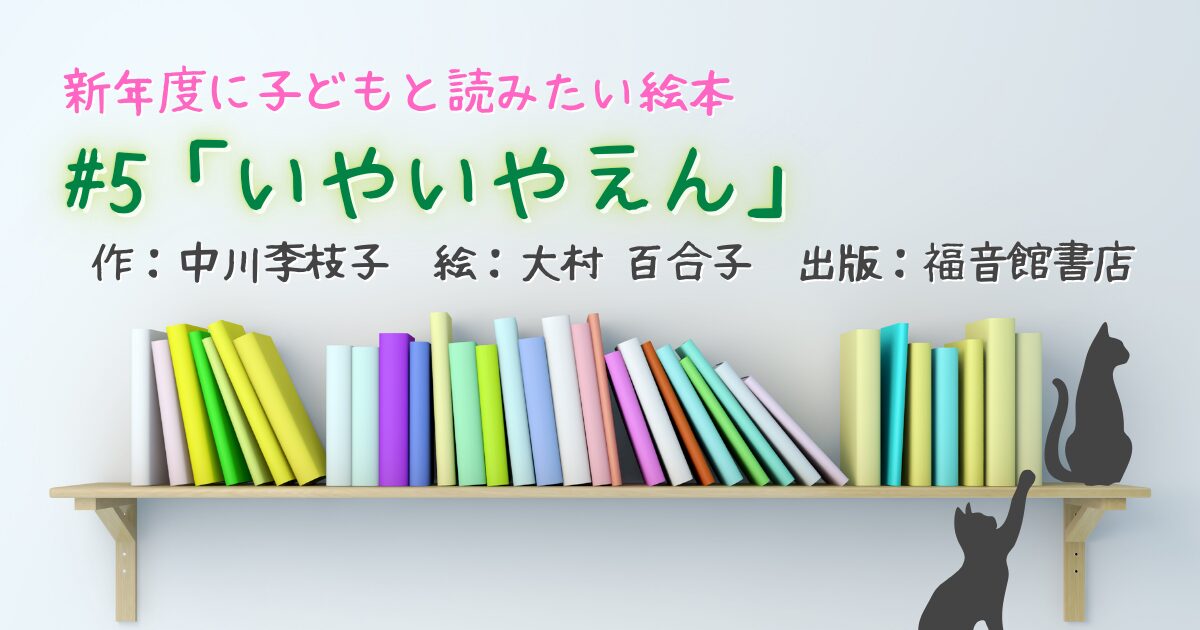


コメント