こんにゃちは、猫月です😺
先日、「できた方が良い」は「まだ、できなくて大丈夫」という記事を掲載しました
・ひらがなが書けた方が良い
・数がわかる方が良い
・椅子に座って過ごせる方が良い
・泳げた方が良い
・相手の気持ちを考えられる方が良い
記事中で、5つの具体例を挙げたのですが、
もう少し深掘りしていこうと思います
ということで、まずは
『ひらがなが書けた方が良い』について
お話ししていきます
🔽 実は、日本語の書き言葉で重要な“助詞”が身に付く絵本です
文字の読み書きは1年生で
保育園の見学でよくいただくご質問に、
『ひらがなの読み書きは指導しますか?』があります
園としては、次のようにお答えしています。
「ひらがな・カタカナの学習は、
小学校1年生の課題です」
「お子さんの興味には寄り添いますが、
園のカリキュラムには設定していません」
「大人と一緒に絵本を楽しむ経験が、
結果的に文字への意欲を引き出すことはよくあります」
学習に適切な時期
学習指導要領は、
子どもの脳と身体の発達に沿って
“無理なく身につきやすい時期”を設計しています
つまり「1年生でひらがな・カタカナを学ぶ」のは、
“発達に合った自然な時期”ということです
一方で、就学前に文字学習を急ぐと、
姿勢や運筆・目の使い方が整う前に記号学習が先行しやすく、
子どもには高負荷になりやすい面があります
文字は“楽しむため”の道具
文字は生活を豊かにする“道具”です
絵本の物語を味わったり、誰かに手紙を書いたり
——“知る・考える”を広げてくれます
子どもが「文字って便利!」と感じる最初のきっかけは、
多くの場合、“文字を介した大人との“ふれあい”です
習得までの発達段階
文字の獲得は、
ことばの発達(聞く→話す→読む→書く)と、
運動の発達(見る→描く→なぞる→模写→書く)が
機のように織り込まれています
ここには、
姿勢保持・目と手の協調・手指分離・適切な筆圧
といった“運筆の前提”が必要です
座っての学習も、実は身体機能に支えられた活動なのです
なお、幼児が鏡文字を書くのは
「間違い」ではなくて、
左右の認識や運筆の発達途中で
自然に見られることです
保育園で経験できること
注目・追視:しっぽ取りで目と体を合わせる
絵本の指差し読み
運筆の前提:ミニカーをマップで走らせる・迷路遊び
粘土や洗濯ばさみで、手指を思うように扱う
言葉の土台:しりとり・頭音探し・わらべうたなどで
“音の感覚”を育てる
いろいろな遊びを大人と一緒に楽しむことが、
就学後の学びにつながります
もし「勉強してほしい」と願うなら、
まずは遊び込む時間を大事にしたいですね
興味がある子には、どうする?
興味は、意欲の源泉ですね
私は、お絵描きと同じように、
自由に楽しめるようにしています
教えはしないけれども、
止めることもしないです
「どう書くの?」と聞かれれば応じますし、
ひらがな表の書かれた下敷きなど、
自分で模写をできるような環境は用意しておきます
🎯生活の中でこそ、文字の力は育まれる
ひらがなに限らず、
生活環境に文字があることは大事だそうです
絵本だけでなく、ポスターなども、
子どもの文字への興味を湧かせます
買い物の時のポップなども、
生活に根ざした文字環境ですね
買い物や銀行、役所など、
子どもを一緒に連れていくことも大事です
お店の看板や駅の時刻表など、
生活には文字が満ちていることを、
子どもと一緒に経験していくと、
文字の大切さが身に染みてきます
文字は生活道具ですから、
学校や保育園よりも、
日常で学ぶことが多いのです
“できたら良い”は“まだで良い”の合図です
1年生で伸びる力を信じて、
今は遊びと関わりで土台を育てていきましょう
「大人が一緒に遊ぶ」時間が、
子どもの成長への大事な投資になりますよ♪
▶︎ できたら良いは、「まだで良い」
【焦らなくても大丈夫!】
#0 できたら良いは、「まだで良い」──概要
#2 できたら良いは、「まだで良い」──数・計算の話
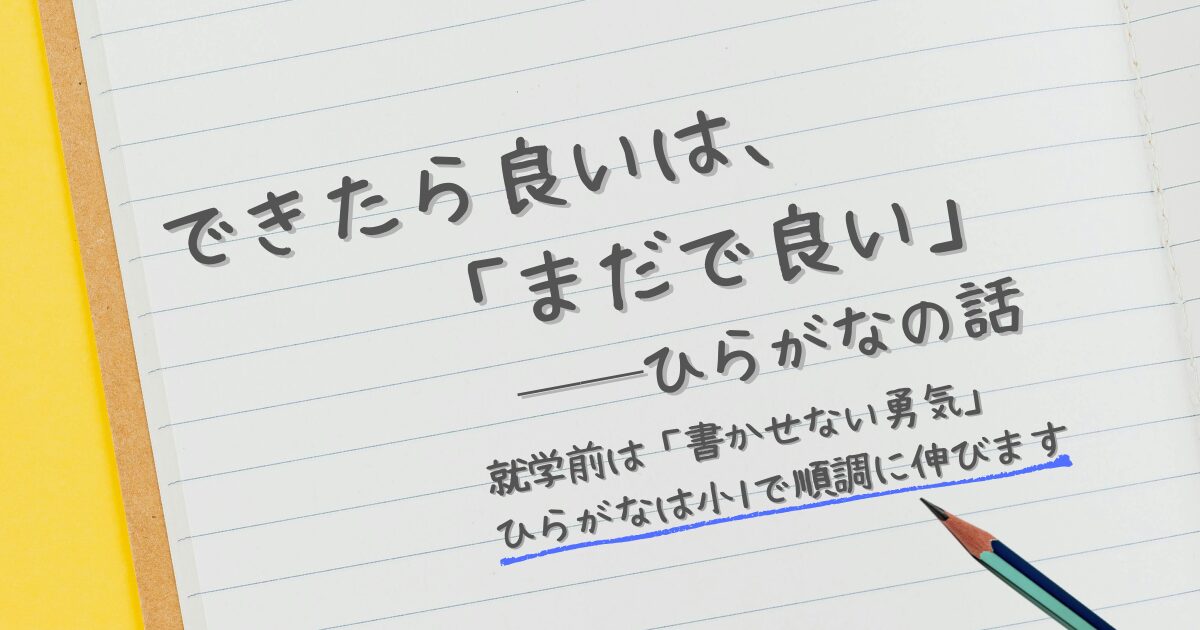
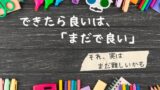

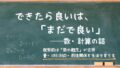
コメント