こんにゃちは、猫月です😸
今週は「子どもの権利を考えてみよう」というテーマで
子どもに関する条約や法律、憲章を、あらためて学んできました

今週は子どもにまつわる条約や法律、憲章について学んできました
みなさん、どんな感想を持ちましたか?

子どもの権利条約は、
18歳未満の子どもには“人としての権利”がちゃんとあるんだよね!
という国際条約でした

主に4つの権利が挙げられていて、
私たちも責任感に駆られちゃいますねぇ…

児童福祉法は、子どもの権利を守ることと、
そのための福祉施設や事業について書かれています

こども基本法は、すべての子どもが平等で健やかに成長できることを謳っていたわ
当たり前の話なんだけどね!

児童憲章は、世界に先駆けて
子どもの権利の理念を掲げてましたねぇ

私も含めて、みんな学びと気づきがあったみたいだね♪
じゃあ、今回は少し実践の話をしてみようか
私も5人も、振り返りと学びを得た中で
実際の子どもとの向き合い方について考えていきたいと思います
あなたも一緒に「こういう場面では…」と思いを巡らせてみてくださいね
■ 事例①:ベッドやソファで飛び跳ねて遊ぶ子

まずは、こんな場面を想像してみてください
子どもが、ベッドやソファで何度も何度も飛び跳ねて遊んでいます。
危ないな…と感じるけれど、とても楽しそうでもあります。
『やめなさい!』とすぐに止めますか?
それとも…あなたなら、どうしますか?
【キツキの場合】驚きと好奇心で見守る!

うわぁ〜!跳ねてるねぇ〜!すっごく面白そう!
本人にとっては“新発見”の真っ最中かも!
この感覚、今しか味わえないかもしれないよ?
【ナツキの場合】心配が先に立つ…

でも、でも…落ちたり、頭をぶつけたりしませんかぁ?
ケガしたら大変だし、やっぱり止めた方がいいんじゃないかって、
わ、私…心配になっちゃいますぅぅぅ…

“危ないからダメ!”って言いたくなる場面だけど、
“どうしてやってるのかな?”って考えてみた上で
「こういう遊びはどう?」と誘うのも大事かもしれないね
ベッドやソファで遊ぶのは、子どもの姿として“あるある”ですよね
好奇心や身体の使い方、浮遊感に足裏の感触の面白さ――
まずは、その子なりの“楽しさ”を受け止めてあげられると
子どももこちらの言葉に耳を向けてくれることが多いです
もちろん、環境の調整や声かけで安全を確保することも忘れずに!
子どもの動機や楽しさに気付くと
ベッドやソファ以外のもので、再現する方法も思いつきます
たとえば、浮遊感を感じたいのであれば「たかいたかい」とかね
■ 事例②:汚れていないのに着替えたい子

では、次の場面です
保育園で見掛ける姿かもしれませんね
服は汚れていないのに、ある子が『着替えたい』と言いました
「汚れてないよ?着替えなくて良いんじゃない?」と返すと
大人が見ていない隙に、水で袖口を濡らしはじめました
保育者として、あなたならどう関わりますか?
【レツキの場合】静かに観察しながら考える

この子は、“着替えたい”理由があったんでしょうね
“濡らす”という手段を選ぶくらいですから、どうしても着替えたかった…
大人の基準だけで判断すると、その子の大事なもの見落とすかも知れません
【ムツキの場合】それはワガママじゃない?とつい言いたくなる…

『着替えたい』からって、わざと服を濡らすのは、
自分の思い通りにしたいからやったことでしょう?
洗濯するのは本人じゃないし、それはワガママじゃない?

“着替えたい”という思いの奥に、どんな気持ちがあるのか――
それを想像すると、“濡らした”という行動の中から動機が見えてくるね
単純に、本当は着たかった服が別にあったのかも知れませんし、
大人に受け止められて、安心したい気持ちがあったのかも知れません
それとも、友だちとのやり取りの中で生まれた感情かも知れないです
行動だけを見て叱るよりも
まずはその子の言葉の奥の気持ちに目を向ける――
それができると、子どもの姿も変わってくるのではないでしょうか
■ 事例③:「帰りたくない!」と遊びを続ける子

では、もうひとつこんな場面を見てみましょう
保護者も保育士も、対応を悩ませる場面ですかね
お迎えの時間になりました。
他の子たちは帰り支度をしていますが、一人の子はブロック遊びに夢中で、なかなか動こうとしません。
お迎えの保護者が来ても「帰りたくない!」と泣いて訴えてきました。
さて…あなたなら、どう声をかけますか?
【ワツキの場合】気持ちに寄り添って、時間をかける

それだけ楽しかったってことですよねぇ♪
“帰りたくない”っていうのも、その子にとっては正直な気持ち
“今の気持ち”をいったん受け止めて、
“じゃあ、帰ったら何しようか?”って次の楽しみに目を向けてあげたいなぁ
【猫月の場合】“楽しい”への共感と、保障を

”楽しい”時間が終わってしまう寂しさもあるだろうし
自分の気持ちを大事にして欲しい思いもあるんじゃないかな
「明日も遊べるよ」って、”予約”してあげるとかどうかな?
『帰りたくない!』の奥にも、
“もっと遊びたかった”とか、“この楽しさをなくしたくない”とか
そんな思いがあるのかもと想像できます
そう考えると、この子にとっての“満足”って何なのか
ちょっと立ち止まって考えてみたくなります
「お迎えが来たから、お片付け」とルールにしてしまうよりも
「あなたはどうしたい?」「どうしたらそれが叶う?」を一緒に考えたい
いつでもそれを叶えられてあげられるかはわかりませんが
“意見を聞いてもらえた”、”一緒に考えてくれた”だけでも
子どもの安心感や、気持ちの満たされ具合は変わってくるはずです
■ 子どもと向き合う“まなざし”が、少し変わってきた?
ここまで読んでくださって、ありがとうございます
法律とか、憲章とか、
正直に言ってしまえば「面倒くさい」と思っていたんです(笑)
”保育士だから”という立場があればこそ
「いろいろな法律も知っていなきゃなぁ」と思うだけで
別に法律に精通していたい性分でもない
でも、今回の学びの中で感じたのは
どの条文にも、どの理念にも、
“目の前の子ども”との関わりにつながっていたということです
保育士として、私は子どもの”自立”を大事に考えてきましたが
子どもを“受けとめる”“尊重する”“待つ”という姿勢が
既に法律や憲章の中に記されていたのです
汐見稔幸教授が、保育所保育指針改定(2017年)の際に
『これまで先生方がやってきたことを、変える必要はありません』
と説明されていたのは、こういう背景があったからなんだなと
今回の学びの中でやっとわかりました
当時の私からすると
「保育所保育指針が変わるのだから、保育も変わるでしょう?」と思っていたので、
汐見先生の言葉の真意がわからなかったのです
とはいえです
今回学んできた「子どもの権利条約」「児童福祉法」「こども基本法」「児童憲章」は
まだまだ浸透していないとも感じました
私自身も、子どもと向き合う毎日を通して
より実感し、かみ砕いて、実践していく努力が必要です
“子どもの最善の利益”を実現するために
子どもが”しあわせ”を感じられる社会となるように
あなたも学びを得てくれていたら、嬉しいです
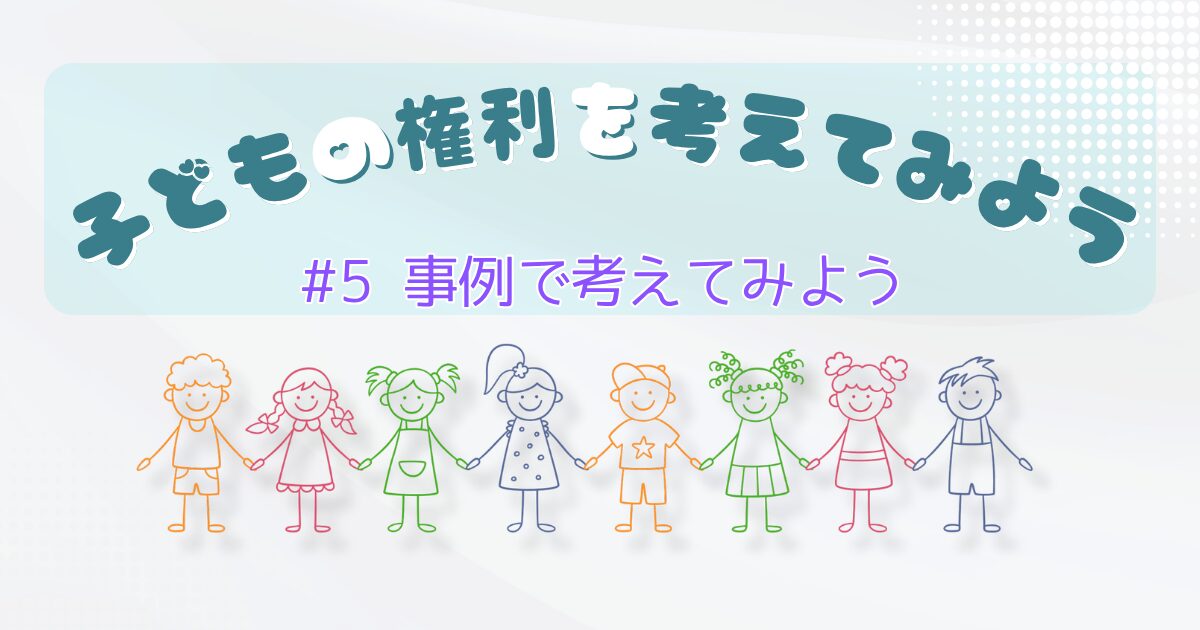

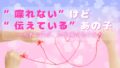
コメント