こんにゃちは、猫月です😸
5月5日は子どもの日――
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日です
親子あっても、保育でも、
子どもを対等に接することは、
大人にとってとても大切な責任のひとつだと
私は思っています

ところで、「子どもの人格を重んじ」るというのは
具体的にどういうことなんでしょうね

うんうん、言葉ではよく聞くけど、実際にどうするのかって難しいよね
私は、工藤勇一先生と苫野一徳教授の対談が
ひとつの参考になると思っているよ
先日、『子どもたちに民主主義を教えよう』(あさま社)に基づく
お二人の対談記事を読み直しました
読めば読むほど、これは学校や教育だけじゃなく
保育にも深くつながる内容だと感じたのです
今回は、その中から特に心に残った言葉をピックアップして
保育の現場での実践と重ねながら
「子どもの人権」について改めて考えてみたいと思います
▶参考にした図書はこちらです
大事にしたい、「子どもの当事者意識」
大人が何でもかんでも介入してばかりいると
「いじめゼロ」の発想こそが、いじめを増やす…教師や保護者が本当にすべきこと
いつの間にか子どもたちは
「自分の問題は自分で解決するものだ」という
当事者意識を失ってしまうんです
子どもの自律を奪っていくんです
アドラー心理学を学んでいる私にとって、
「課題の分離」は、保育者としてのベースにある考え方です
でも、多くの親や保育者、教育者にとって
子どもが困っているときに手を差し伸べるのは、自然な反応でしょう
ただしその“やさしさ”が
子どもから「考えるチャンス」や「選ぶ自由」を奪ってしまうことがあるのです
【保育での実践】
私が日々意識しているのは
「大人が解決しない」ということ
たとえば、友だち同士のトラブルが起きたとき
すぐに仲裁するのではなく、まずはこう聞きます
「どんな気持ちだったの?」と
お互いの思いを、自分の言葉で伝えること
そして、相手の言葉に耳を傾けること
その経験自体が、子どもにとって大切なプロセスです
そして最後に、こう問いかけます
「じゃあ、あなたたちは、これからどうしたい?」
大人が答えを与えるのではなく
子ども自身が“自分の問題”として向き合う
それが、当事者としての第一歩だと私は思っています
“心の教育”に目が向くけれど、重要なのは「行動に移せること」
どれだけ心の教育をやっても、行動が伴わないんだったらあまり意味はないですね
「思いやりの心をもちなさい」という教育が「子どもの問題解決力」を奪うワケ
保育園や学校でしばしば疑問視される
「ごめんね」「いいよ」問題があります
体裁的には謝っているし、許しているのだけれど
『そこに子どもの本心はあるのか?』という話ですね
このやりとりだけを見れば、
「ちゃんと行動しているじゃないか」と思われるかもしれません
けれど、それは大人の都合による“形だけの行動”にすぎません
子ども自身が、「こうしたい」と判断したわけではないのです
では、ここで言う「行動が伴う」とは何か。
それは、子ども自身が “お互いにとってmore better な関係性” を選び取る力を育てることだと
私は解釈しています
工藤先生は、こんなエピソードを紹介しています
息子が人間関係で悩んでいると直感的にわかったんですね。そこで僕はこんな声をかけたんです。
「思いやりの心をもちなさい」という教育が「子どもの問題解決力」を奪うワケ
「実はお父さん、職場で嫌いな人がいるんだよね」
あのときの息子の驚きと安堵の表情がいまでも忘れられません。息子は友だちと仲良くなれない自分を責めていたんです。そのあと僕はこう続けました。
「でもお父さんはその人に嫌いな態度は見せないし、毎日あいさつもするよ。もちろん攻撃などしない。先生が言っている『仲良くする』って実はそういうことなんじゃない。別にみんなを好きになる必要なんてないんだよ」
これはつまり、
「馬が合わなくても、穏やかに過ごす力」――
関係性を壊さずにやり取りする“win-win”な関わり方を
身につけることが大切だという示唆です
【保育での実践】
子どもも3歳にもなれば
ケンカをした際に相手が謝ってきても
『絶対に許さない!』なんてことを言うようになります
そういう時に「まぁまぁ、仲良くしなさいよ」
なんて大人が言うのは野暮なのです
まずは「そっか、許したくないのね」と
大人が一旦気持ちを受け止める
すると、本人が自分の気持ちと向き合えるようになるのです
『……いいよって、言う』と自分で判断することが
少しずつできるようになっていくものです
時には、振り上げた拳の降ろし方がわからなくなっている子もいます
でも、それもまた経験です
子どもが『言いすぎちゃったかな…』
『そこまで言うつもりはなかったんだけど…』
そんな内省が生まれる場面を、子どもたちは確かに積み重ねていきます
行く行くは”行動が伴う”姿につながっていくのだと思っています
面談は、子どもも親も“元気になる”場であってほしい
僕は「三者面談の目的は本当に情報の共有なんだろうか?」と教員に問いかけたんですね。「三者面談って子どもを元気にするためにやることじゃないの? 子どもに元気になってほしくない教員っているの?」って。すると教員たちか ら「ああ……」というリアクションが返ってくるんですね
学校「三者面談」で、「先生、チクりやがって」と…! 「逆効果の三者面談」「理不尽な校則」問題など、日本の「学校」の“おかしな真実”と“正しい対処法”…!
工藤先生が語るこのエピソードは
保育園での保護者面談にも大きなヒントを与えてくれます
保育園では、基本的には保育者と保護者の個別面談が一般的です
(個人的には、子どもを交えた三者面談も選択肢としてあっていいと考えています)
でもこの「面談」、実はなかなかの曲者で――
現場ではこんな声を耳にすることもあります
『あの子の姿、ちゃんと保護者にも知ってもらわなきゃ』
『“気になる子”って、伝えた方がいいよね』
もちろん、子どもの育ちや支援の必要性を共有することは大切です。
でもその視点が強くなりすぎると
面談のベクトルが“ネガティブ”に寄ってしまうことがあります
面談の本来の目的は、
「子どもの育ちを、保護者と一緒に喜び合うこと」
そして、面談は子育ての不安や悩みを安心して語れる機会であること
それが、子どもと親を元気にする面談につながると私は思っています
【保育での実践】
私が面談で大切にしていることは、以下のような点です
・保護者が感じている“子どもの成長”を聴く
・保護者が抱える“子育ての困り感”を聴く
・成長エピソードに共感しながら、園での様子を伝える
・困り感が成長のプロセスの一部であることを照らし返す
・子どもが集団の中で「できること」も「困っていること」も、事実として伝える
いわゆる“気になる子”についても、
まずは実際の姿を丁寧にお伝えした上で、こう整理して話します
・本人が「困っていること」がある
・その困り感に対して、今こういう支援を行っている
・より手厚いサポートのために、専門機関と連携する選択肢もある
何より重要なことは
子ども自身の生活の質(QOL)が向上することですからね
子どもは確実に成長しています
その成長が、保育園というコミュニティの中でもしっかりと発揮されている
時にはつまずくこともあるけれど、そこには支える大人の手立てもある――
そう感じていただければ、保護者は園生活に安心し
子育ての大変さの中にも、喜びや希望を見出せるのではないでしょうか
それが、保護者の明日への活力につながり、
結果として子どもにも、より好い影響が広がっていくのだと信じています
最後までお読みいただき
ありがとうございます
私は、「保育園は子どもたちによるコミュニティだ」と考えています
保育者はあくまで、子どもたちが営む生活の場の、支援者であり伴走者です
工藤さんの言葉を借りるならば
子どもたちが「社会の当事者」なのです
保育園は、まだ“社会”の入口かもしれないけれど
その中で子どもたちはしっかりと意思を持ち、日々の生活を送っています
「子どもたちを保育する」のではなく、
「子どもたちと保育する」という感覚
それを忘れずにいたいと、あらためて思いました
子どもの権利については、私も学び続ける立場です
『子どもの権利条約』や『児童憲章』を読み解いていく連載を予定しています
“なんとなく知ってる”で終わらせないために
あなたと一緒に「子どもの当たり前」を言葉にしていく時間にしたいと思っています
▶工藤先生の言葉を子ども向けにまとめた一冊
▶工藤先生から子育てを頑張るあなたへのエール
👇「子どもの権利」を考えるシリーズです
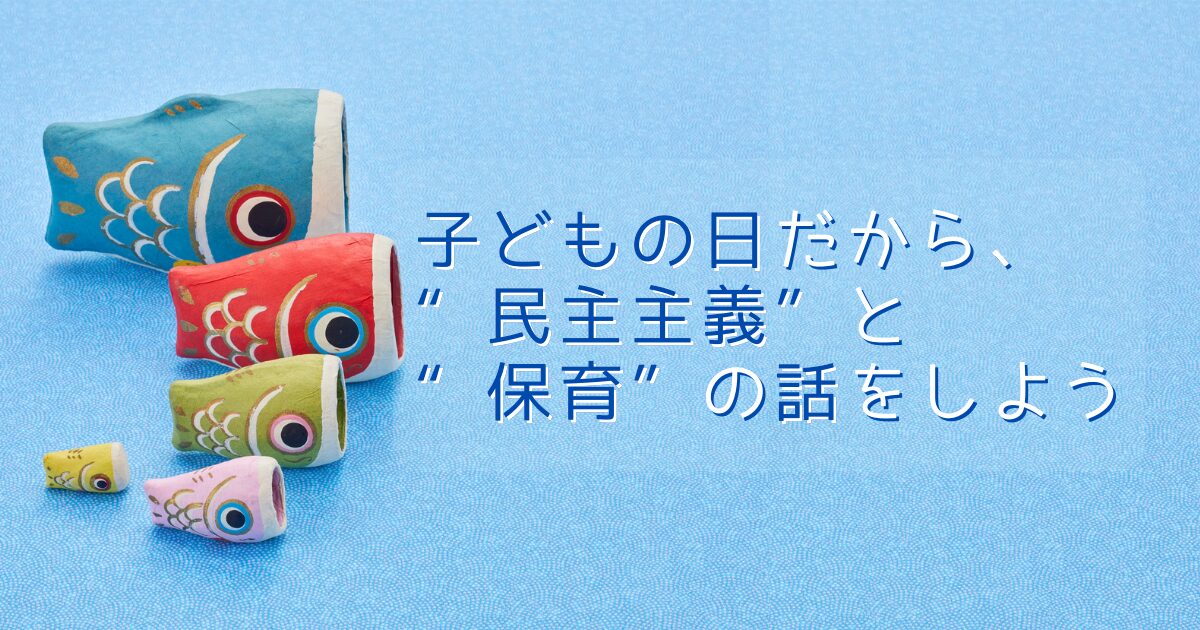



コメント