こんにゃちは、猫月です😺
質問をいただきました。
私の勤める保育園は、食事と午睡(お昼寝)が同じスペースなのですが、
食後に午睡準備をするので子どもを待たせる時間ができてしまいます。
子どもたちがスムースにお昼寝できる工夫はありますか?
保育室がそのまま食事やお昼寝のスペースであることは、間々あります。
遊んでいた部屋を片付けて、給食を食べて、
給食を片付けた後に
布団やコットを広げるパターンですね。
🔽 保育園で目にするコットです
今回の相談者さんは3歳児の担任で、
給食の片付けが終わってからコットを広げるので、
どうしても食後から午睡まで
待ち時間が発生してしまうということでした。
私の場合をお答えすると、
子どもたちと一緒に午睡の準備をします。
では、実際にはどうしているかお話していきましょう。
子どもの意欲を認める
「3歳児なら午睡準備ができる」というと、
誤解があります💦
3歳児からいきなり午睡の準備ができるようになったわけではなく、
もちろんその前提があるのです。
彼らは2歳児に、自分の布団を運ぶ経験をしていました。
大人が布団を片付ける様子を見て、
自分の布団を運び始めたんですね。
きっかけは、大人の模倣です。
その子どもたちの姿を見て、
「あなたたちにはまだ早い」と止めていたら、
この3歳児の姿には至りません。
子どもの主体性を尊重しつつ、
「どうしたら意欲を保障できるか」を
考えていくことが大事でした。
さて、布団を上げる場合ですが、
掛け布団は自分で運ぶことができました。
重さがそれほどではないですからね。
ネックは敷布団です。重量がなかなかあります。
引き摺れば運べるでしょうが、
それだと布団やカバーが傷んでしまう。
分かりやすいのは、大人が一緒に運ぶことで、達成感を得ること。
でも、二十数人に付き合うと、かなりの時間がかかります。
解決方法は、すぐに見つかるのですけどw
誰かが布団を運びたがる。
大人がそれを手伝う。
2人で1脚の布団を運ぶ姿を見る。
協力すれば重たい布団も運べることに気づく。
友だちと一緒に布団を運び始める。
運びやすい持ち方や向きを考える。
こんな感じの展開があって、
自分たちで布団を上げられるようになっていったのです。
布団が上げられるなら、
布団を広げることもできますね。
3歳児はコットで午睡をしますので、
敷布団よりも軽量です。
持ちやすさもあります。
ここで、大事なのは
あくまで“主体的”に参加すること。
やりたい子だけがやれば良いというスタンスです。
まー、そうすると大体全員がやるんですけど🤣
前段階の経験があってこその、
午睡準備が展開できるのです。
🔽 コアラ布団は、この価格でも素晴らしい寝心地です
子どもへの信頼と見極め
「その子のやりたい遊びが、その時の成長に必要な遊び」
これは、研修で聞いた作業療法士の言葉ですが、
それは子どもの生活全般で当てはまることなのだと思います。
意欲を大事にすることが、
結果として子どもの成長に大きく影響する。
そう考えると、
子どもが自分でやろうとしたことは、
最大限に尊重したい。
かといって、
明らかに危険なことをさせるわけには
いかないですよね🙅♀️
ではどうするかというと、
子どものやりたいことを細分化します。
私は勝手に「因数分解する」と呼んでます🤭
今回で言えば
午睡の準備をすることなのですが、
子どもが大人と同じように、
布団を一脚運ぶのは難しい。
では、最終的に布団一脚を運べるようになるとして、
その前段階は、何ができることなのでしょう?
敷布団が運べることかもしれませんね
でも、それも難しいなら、その前段階は?
掛け布団の方が軽いから運べるかも
でも、それも難しいなら?
頭の下に敷くタオルなら運べるかも
シーツを掛けるのは難しいけれど、
シーツをはがすことはできるかも知れない
ひとりで運ぶのは難しいけれど、
ふたりでなら運べるかもしれない
大人は「できっこない」と思うかも知れないことって、
「大人ならできる」形で考えてはいませんか?
日本人は、最終形を「できる」と考えがちだそうです。
英会話は、ネイティブとスラスラ喋れること、みたいにね
実際は、日常的に使っている英単語だって多いのにねー
料理なんかもそうじゃないですか?
土井善晴先生は「味噌をお湯でとくだけで味噌汁ですよ」と仰ってました(笑)
それくらい、「できる」のハードルは低くて良い。
意欲を尊重して、
その子の「できる」をどう提供できるかが、
カギなんです。
ただそのためには、
その子の成長を信頼することと、
その子の取り組めることと難しい事の境界線を見極めること
そこは、プロの視点で子どもをつぶさに見る必要はあるでしょうね。
子どもの機会を保障すること
ここで間違えてはいけないのは、
「全員で午睡準備を」と考えること。
それじゃ、ただの強要です。
子どもの意欲もへったくれもありゃしない😰
あくまで、子どもの機会を保障することです。
本来は、保育士が午睡環境を整えるものです。
子どもの午睡準備は、あくまでオマケ
でも、子どもの成長に役立つなら使わにゃ損々♪
そういうスタンスですよ(笑)
一番の目的は、
子どもたちがスムースにお昼寝できる
ですからねー🤗
今回の回答は、私の実践例のひとつです。
正解というわけではありません。
子どもの姿に合わせて、
その子たちに相応しい工夫の仕方があるはずです。
保育園の環境も、園ごとに変わりますしね。
私は勤めたことはありませんが、
系列には「午睡室」なる設備のある園舎もありましたねー😳
床暖房までついているというのですから、
うらやましい限りです。
とはいえ、「ないものはない!」ですから、
今ある環境で、最大限の工夫をしていきましょう♪
蛇足で、私の好きな言葉を置いておきます。
「ねだるな、勝ち取れ、さすらば与えられん」(アドロック・サーストン)
(誰も分からねー奴だ、これ🤣🤣🤣)
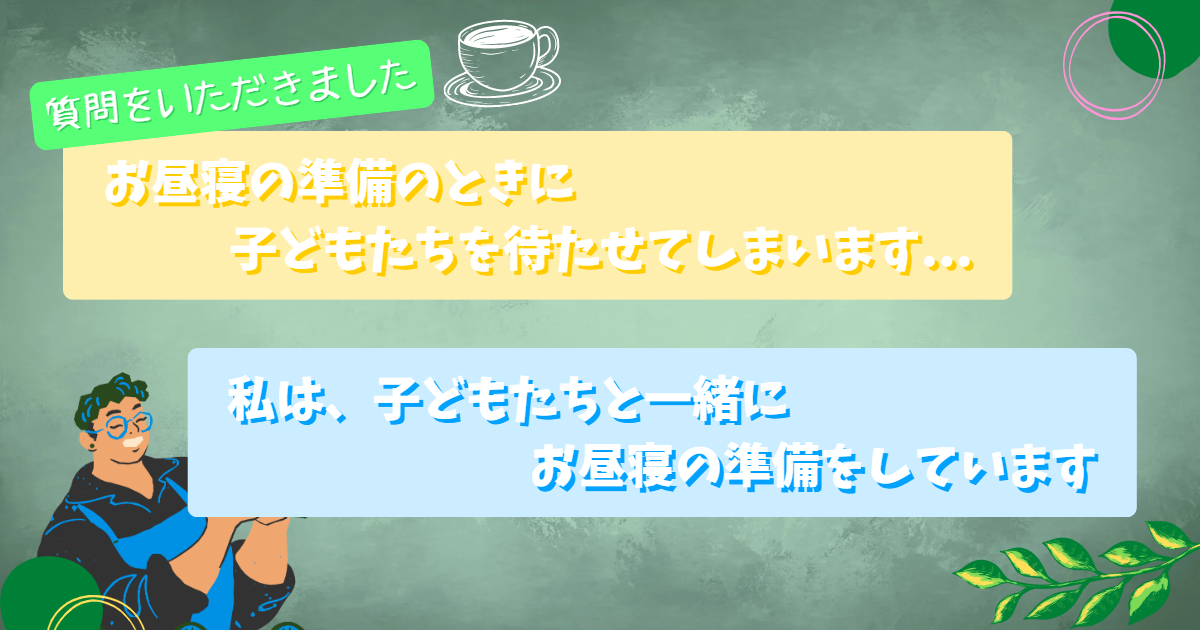


コメント