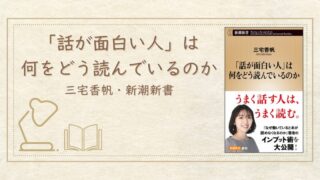 人との出会いと学び
人との出会いと学び 【書籍】「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか
「本が読みたくなる本」それが、三宅香帆さんの『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(新潮新書)です。この本を読んでいると、「じゃぁ、その作品を読んでみよう!」となります。自分の世界を広げてくれる本、あなたも読んでみませんか?
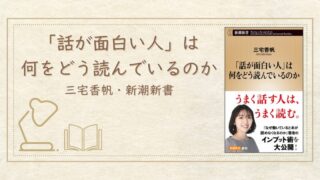 人との出会いと学び
人との出会いと学び  保育の考え方と指針
保育の考え方と指針  家庭でもできる、子どもとの関わり方
家庭でもできる、子どもとの関わり方 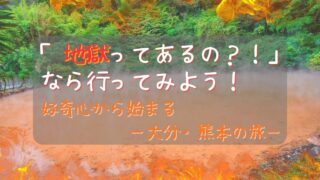 家庭でもできる、子どもとの関わり方
家庭でもできる、子どもとの関わり方 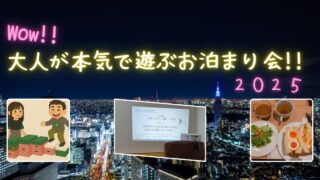 人との出会いと学び
人との出会いと学び 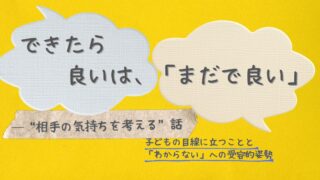 保育の考え方と指針
保育の考え方と指針 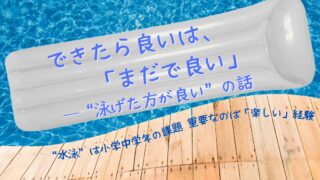 保育の考え方と指針
保育の考え方と指針 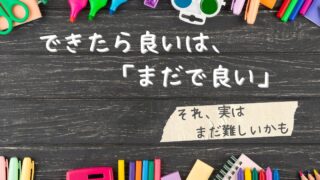 保育の考え方と指針
保育の考え方と指針  保育の考え方と指針
保育の考え方と指針  保育の考え方と指針
保育の考え方と指針