こんにゃちは、猫月です😺
先日、できたら良いは「まだで良い」という記事を掲載しました
・ひらがなが書けた方が良い
・数がわかる方が良い
・椅子に座って過ごせる方が良い
・泳げた方が良い
・相手の気持ちを考えられる方が良い
記事中で、5つの具体例を挙げたのですが、
もう少し深掘りしていこうと思います
ということで、まずは
『泳げた方が良い』について
お話ししていきます
▶️ まずは、水のそばで楽しく過ごす時間を大事にしましょう
就学前は“水って楽しい”を増やしたい
就学前に大切なのは、
「水が気持ちいい」「またやりたい」
という情緒づくりです
保育園の水遊びでも、
ビート板などを用意しているところがありますが、
そもそも本格的な水泳指導はできないはずです
保育士の養成課程に、水泳指導はありませんからね
個人的発想で“泳ぐ”ことを指導するのは、
私は危険だと考えます
「水泳」自体は、小学校中学年以降の課題になります
小学校1・2年の目安も水遊び中心(息を吐く=バブリング、潜って浮く=ボビング、壁つかまりの伏し浮き、補助具での浮き遊びなど)です
先取りで“泳ぎ”を急ぐと、
水への怖さが根付いてしまい、
就学後の意欲を削ぐことにもなりかねません
まずは安全な環境で、
「水で遊ぶって楽しい♪」感覚を伸ばしていきましょう
乳幼児期の発達段階の目安(触れる、浴びる、浸かる)
乳幼児期の水遊びの発達段階は、
大きく次のように分けることができます
乳児(0歳~1歳頃)
首がすわり、お座りが安定してくる
生後6~7か月頃から
水の感触遊びが始められるとされています
水の冷たさや流れる感触を肌で感じることで、
感覚の発達が進みます
まずはお風呂場やたらいで、
手や足にぬるま湯をかけるなど
慣れていくことが大切です
水の触感や水の音、
色を見るなど五感を刺激し、
「楽しい」「もっとやりたい」
と感じる経験を積みます
幼児(1歳~2歳頃)
歩行を始めて、徐々にバランスが安定し、
行動範囲が広がり、
手指での探索が増していく時期です
ペットボトルシャワーや容器で水をすくうなど、
手や指を使った動きを通じて巧緻性を育てます
また、水が流れる・溜まるなどの様子や色水遊びから、
「なんでだろう?」という好奇心が育まれます
水の動きや音・色の違いを体験しながら、
想像力や創造力も伸びていきます
幼児後期(3歳~5歳頃)
身体能力や理解力が発達してくると、
集団での水遊びや水の中で身体を動かす遊びなど、
本格的な「水慣れ」が目標になります
ジョウロや水鉄砲などを使い、
全身運動につながる遊びにも積極的に挑戦します
それと同時に、水の怖さを理解する時期でもあります
顔をつける・息を継ぐ・バタ足など、
泳ぐ動作の基礎を身につけていくこともあり、
友だちと安全に遊べるルールを知るなど、
社会性や協調性が育ちます
発達段階まとめ
・乳児は「水に慣れる」「五感を刺激する」ことが大事です
・幼児前半は「手や指を使う」「水の性質に気づく」「想像力を育てる」ことを楽しみます
・幼児後半は「運動能力や協調性を伸ばす」「基礎的な泳ぎの動作を身につける」段階です。
子どもの発達や特徴に合わせて、
無理せず安全を守りながら
楽しく水遊びを進めてください
幼児にとって水は“遊び”の道具です
幼児期は感覚優位です
まずは、気持ち良さの共有が、
水遊びの入口になります
「最初はお尻を濡らしてみよう」
「肩まで水に入って、ワニになろう」
「口だけ水につけて、“ぶくぶくぶく〜”」
水に触れる、水に浸かる、
水圧を感じる、水の重さを体感する、
息苦しくなることを知る
そういったことを、遊びを通じて知っていくのです
就学へつながる保育園での“水慣れ”
以前もお話ししましたが、
私はカナヅチです😫
幼稚園時代に身についた恐怖感が、
就学してからも拭えませんでした
そんな私が思うのは、
「大人が用意した環境次第で、
子どもの成長の芽は簡単に潰れる」
ということです
くり返しの話になりますが、
幼児期の水遊びはとにかく
「楽しい」で終わりにすることです
そのために大切なことの一つは、
保育士の関わりです
「一緒にワニになって!」
「今日はほっぺにお水つけられたよ」
「明日はね、顔を水につけちゃうよ!!」
遊びやちょっとした成長に共感することが、
その子の意欲を引き出し、
卒園後も成長する土壌となるのです
泳ぎに興味がある子はどうする?
「水への恐怖」は、本能的なものです
勇気を持って一歩踏み出すかは、
個人差が著しいもの
無理をさせないのと同様に、
意欲や好奇心も大事にしたいですね
同じ遊びで、個人に合わせて楽しむ方法はあります
私の場合は、フープをふたつ用意します
基本は、私が握った1本のフープをくぐるのですが、
その子のやりたい深さに合わせて沈めます
顔をつけたくない子は浅めに、
潜ってくぐりたい子は深めに、です
蹴伸びやバタ足をしたい子は、2本の間をくぐり抜けます
こうすれば、水の深さや潜る距離を
個人に合わせて調節できます
また、水遊びの準備でも、
個人の水慣れの段階を図ります
プールに入ると、まず身体を水に慣らすために、
足元から順々に水を掛けていきます
「最初は足だよ」
「次は、お尻にバシャバシャー」
「お腹にも掛けていこう」
「ほっぺも濡らしてみよう」
「できる子は、頭にも〜」
こうすることで、その子と水との距離感がわかります
ほっぺにチョンチョンっと水をつける子と、
頭にもザブザブ水を掛けられる子は、
それだけ水の得意さに差があるわけです
そういう個々の違いを把握しながら、
「こうしたら楽しめるんじゃない?」を、
目の前の子どもに合わせて提供したいですね
🎯 生活の中で伸びる“水への親しみ”
プールでない場面でも、水への親しみは湧いてきます
家庭でできる遊びとしては──
・お風呂でバブリング:
水をブクブクと吹いて遊びます
息継ぎに繋がっていきます
・お化粧ごっこ:
化粧水をつけるように、顔を少しずつ濡らします
水の冷たさを感じることと、
顔が濡れることに慣れていきます
・タオルでアンパンマン:
お風呂上がり、バスタオルの上で
「アンパンマーン!」と飛ぶポーズをします
背筋・両腕・両足をピンと伸ばして、
泳ぐ時の“浮き”の姿勢を体験します
なんてものがあります
遊びを楽しむことで、
子どもは動機や意欲が湧いてきます
それは、主体性を発揮するということですし、
後々の学習や運動への興味にも繋がっていきます
「水泳」が課題となるのは、小学校中学年
その時に「水が苦手」では困りますよね
「水の中で過ごすことが楽しい」を積み重ねることが、
子どもの成長の土台になります
お子さんと遊びながら、
「これは、水遊びが楽しくなるんじゃ?」を
いろいろと試してみてください
▶︎ できたら良いは、「まだで良い」
【焦らなくても大丈夫!】
#0 できたら良いは「まだで良い」──概要
#1 できたら良いは、「まだで良い」──ひらがなの話
#2 できたら良いは、「まだで良い」──数・計算の話
#3 できたら良いは、「まだで良い」──座って聞くの話
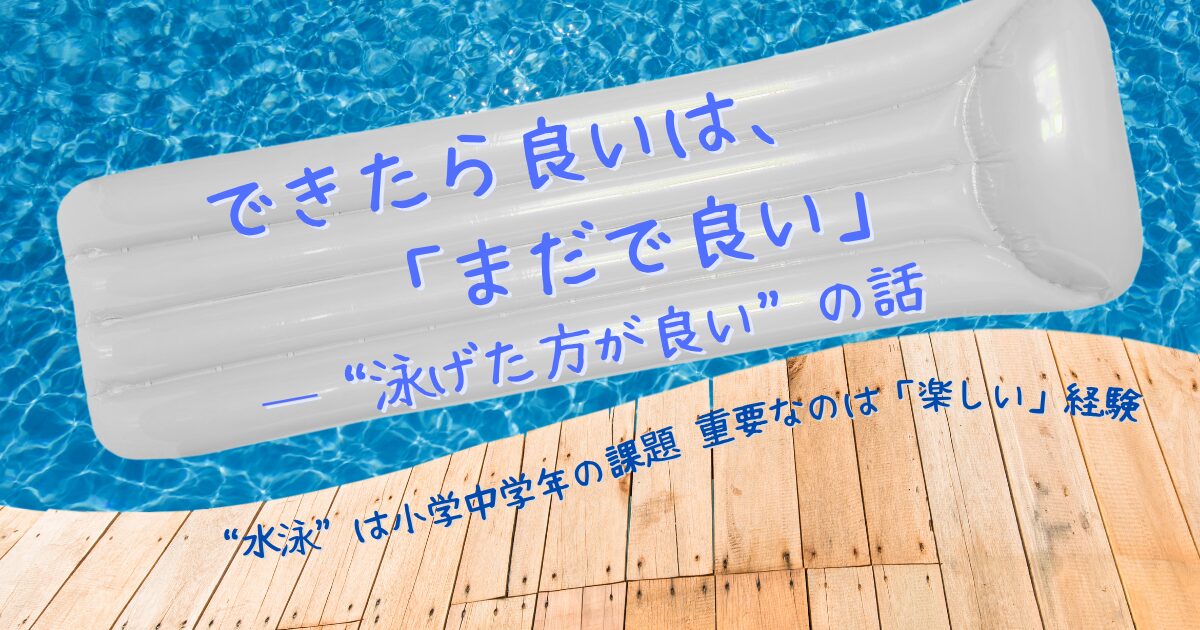
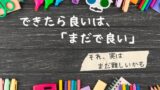

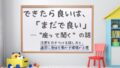
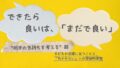
コメント