こんにゃちは、猫月です😺
先日、うちの職場でこんなやりとりがありました。

ご飯を配りますよー
ちゃんと座ってください
ほら、きちんと前を向いてねー💢

あらら、レイキさん
イライラしてますねぇ…
相手は小さな子ですからねぇ

わかってるんですけどね
簡単な話も通じないと、
冷静な私でもイラッとしますよ…
子どもにやってほしいことを、
できるだけ簡潔に伝えているのに、なかなか通じない
これ、家庭でもよくある一幕ですよね
でも──
何度も伝えても伝わらないと、
穏やかに話そうと思っていても
「もうっ…なんでわからないの💢」
となってしまう
ところで、どうして伝わらないのか、
立ち止まって考えたことはありますか?

考えるも何も、
あれ以上の“やさしい言い方”って
ありますか???

言葉としては“やさしい”よね
でも、その“やさしい”が、
大人基準だったらどうだろう?
以前にも、子どもへの伝え方の話をしました👇
今回は、
大人と子どもの「言葉の受け止めの違い」について
あなたと一緒に考えていきましょう
「ちゃんと」では、ちゃんと伝わらない理由
シンプルな質問をしますが、
「ちゃんと」って、どういうことを表しますか?
「ちゃんと」の意味って、具体的にどういうものでしょう
主には、以下のような意味合いで使われる口語(話し言葉)です
・乱れがなく、よく整っている様子
(例:「ちゃんと片付ける」)
・確実に物事を行う、間違いなくやる様子
(例:「ちゃんと約束を守る」)
・必要なことや量が十分に満たされている様子
(例:「ちゃんと食べた?」)
こうして言葉に起こしてみると、
思っているより、ずいぶん複雑だと感じませんか?
これを幼児に「理解しなさい」と要求しているのが、
「ちゃんとしなさい」という発言です
実は、子どもに何かを伝えているようで、
“具体的には何も伝わっていない”言葉が「ちゃんと」です
子どもからすると、ほぼ“宇宙語”
音は理解できても、行動のイメージが沸かないのです
「ちゃんと」は、
縦関係で使われる言葉ですよね
対等な対話の中では、ほとんど登場しません
言葉を向けられる側にとっては、
軽い圧力がかかった状態です
理解できていなくても、
本心とは異なる要求であっても、
「Yes」と答えざるを得ない言葉
あなたは、上司や先輩から
『ちゃんと仕事して!』と言われて、
「No」と答えられる人は、まずいません
その状況で“どうしたらいいですか?”と質問できるでしょうか? 💬問いかけの質を少し変える
つまり「ちゃんと」を使うことで、
子どもは“考える前に止まってしまう”のです
理解しようとする力も、発揮しづらくなります
もちろん、大人には
“大切にしたくて言っている”側面もあるのですが、
結果的には、その言葉が子どもの思考を止めてしまっている
だからこそ、言葉の選び方に気付くことが
大人の務めだと私は考えています
では、“ちゃんと”の代わりに、
どんな言葉で伝えればよいのでしょうか
一緒に考えてみましょう
子どもにちゃんと伝わらない言葉がある
大人が何気なく使う言葉で、
子どもには難しい言葉があります
まずは、どんな言葉が伝わりづらいのか
そこから考えてみましょう
先ほどのレツキの言葉を借ります
ご飯を配りますよー
ちゃんと座ってください
ほら、きちんと前を向いてねー💢
彼女は子どもに
「前を向いてね」と伝えています
ですが、その意図が伝わらず、
イラっとしてしまいました
ここで、少し考えてみましょう
子どもに方向を伝えるとき、
どんな表現を使いますか?
例えば「右」「左」なら、
「スプーンを持つ方」「お箸を持つ方」など
子どもがイメージしやすい言い換えをしますよね
では、「前」だったらどうでしょう?
レイキが伝えたい「前」は
👉 “テーブルの方向”=大人が基準にした「前」
ですが、子どもにとって「前」は
👉 自分が向いている正面
必ずしも一致しないのです
大人は
「前と後くらい、わかるだろう」
と考えがちですが、
実はこの「前/後」でさえ、幼児にとっては抽象的な概念です
他にもこういう言葉はあって、
| 大人の言葉 | 大人のイメージ | 子どものイメージ |
|---|---|---|
| 声を小さく | 今の半分の音量 | 今より小さく(したつもり) |
| ゆっくり噛もう | 噛む回数を増やす | 噛む早さを遅くする |
| もう少し前 | 一歩前に | 30cm動く |
| ちゃんと座って | 足揃える、背筋伸ばす | とりあえず座る |
つまり、“量”や“速さ”の感覚が違うのです
子どもはふざけているわけではなく、
イメージが難しいだけなんです
「”やさしい言い方”でも、わからない場合がある」
そういう前提でコミュニケーションを取ることが、
子どもと向き合う姿勢として、とても大切です
“伝わるように言葉を工夫する”のが、
大人の役割ですね
子どもの「具体的」で伝えよう
またもや、レツキの言葉を借ります
ご飯を配りますよー
ちゃんと座ってください
ほら、きちんと前を向いてねー💢
この言葉掛けは、どう言い換えれば、
子どもにストレートに伝わるのでしょう?
私だったら、このように話します
ご飯を配りますよ
テーブルとお腹を──ぴったんこ!
手は、おひざに置いてねー
・テーブルを正面にする → テーブルとお腹をぴったんこ
・姿勢を正して座る → 手はひざに置く
行動をイメージできることがポイントです
1歳児でも、これなら伝わります
私が大切にしているのは、
動作に「擬音+意味」をセットで伝えること
・「くっつけて」より → 「ぴったんこ」
・「ゆっくり歩こう」より → 「そーっと」
・「静かに」より → 「しーっ」
擬音は、子どもの感覚に直接届く言葉です
こうした表現は、
私と子どもたちが積み重ねてきた日々の中で
自然に生まれてきたものでもあります
“伝わる言葉”は、大人が探すのではなく、
子どもとの関係性の中で育てていくもの
あなたのクラスや家庭にも、
その子たちだけの「伝わりやすい言葉」があるはずです
こんな場面「伝わるように」を考えてみよう

…なるほど。
“正しさを知らせる”より、
“届くように言う”が大事、って感じですか

方向の感覚も、わかります〜
大人が“前を見てね!”って声を掛けても、
子どもは、自分が向いてる方向が“前”だと感じますよねぇ

ふたりとも、
大人と子どもの視点の違いを感じてもらえたかな
では─“こんな時は、どう伝える?”を考えてみようか
ここまで見てきたように、
「ちゃんと」「しっかり」のような抽象表現だけでは、
子どもには行動のイメージが湧きにくいことがあります
実際の保育や家庭の場面で、
あなたなら、どんな言葉をかけるでしょうか?
正解を探すというよりも、
「どう伝えたら、あの子に届くだろう?」
を考えてみてください
🟡手洗い(1歳児)の場面で──
いつまでも水を触り続けている子がいます
後ろには、順番を待っている子もいます
≪あなたは、どんな言葉掛けをしますか?≫
🟢片付け(2歳児)の場面で──
外遊びに出ようと声を掛けましたが、
片付けずに逃げ回っている子がいます
≪あなたは、どんな言葉掛けをしますか?≫
🔵話を聞く(3歳児)場面で──
リーダー保育士が子どもたちに話をしている状況で、
隣の子とお喋りしている子がいます
≪あなた(サブ保育士として)なら、どう声を掛けますか?≫
🔴午睡(4歳児)の場面で──
周りの子は眠っている中で、
布団をいじり続けている子がいます
≪あなたなら、どう声を掛けますか?≫
🟣話し合い(5歳児)の場面で──
行事の話し合い中、窓の外を眺めていて
話し合いに集中できていない子がいます
≪あなたなら、どう声を掛けますか?≫
5つの年齢と場面をご紹介しました
あなたなら、それぞれどう言葉を掛けるでしょう
“子どもに届くように”を意識して、
頭の中で言葉を選んでみてください
まずは、考えることが大切です。
その積み重ねが、
実際の保育現場で
「この子には、どんな言葉が届くだろう?」
と立ち止まって考える瞬間を
増やしていくと、私は思っています
猫月なら──こう言葉を掛ける
先の五つの場面で、
私ならどうするかをお話ししていきましょう
あくまでひとつの例ですので、
参考として読んでいただければと思います
🟡手洗い(1歳児)の場面で──
「水にさわるの気持ちいいねー」
「♪じゃーじゃー、ゴシゴシ
じゃーじゃー、ゴシゴシ
お水を止めて きゅっきゅっきゅ」
「キレイなお手々で、遊びにいこー!」
手洗いを終えられないのは、
水が魅力的だから
止めさせたいなら、
それ以上に魅力的な次の目的を用意します
また、「お友だちが待ってるでしょ?」と
言いたくなるところですが
目的はまず “手洗いを適切に終えること”
道徳的な話は、理解できる年齢になってからで十分です
👉ここでの「ちゃんと」は、
「手洗いを終えること」ですね
🟢片付け(2歳児)の場面で──
これも、1歳児の手洗いと似たような場面ですね
今、目の前の遊びが魅力的なのですから、
まずは、そこに共感します
その上で
「また遊びたいなら、“取っておく”?」とか
「次に遊べるように“予約”しておこうか」とか
遊びを保障するような言葉を掛けます
保障したところで、
戻った時には忘れていることも多いですが、
『自分の“遊びたい”気持ちが守られた』ことで、
次の行動に移りやすくなります
👉ここでの「ちゃんと」は、
「次の遊びへ行こう」です
🔵話を聞く(3歳児)場面で──
ぶっちゃけると、
3歳児が集団の中で保育士の話を聞くのは難しいです
会話は基本的に、対面した相手と行うものです
当然、隣にいる子の方が近いので、
対面の状況になりやすいです
そんな子どもたちに、
サブとして声を掛けるとすれば、
「◯◯先生、何かお話ししてるね」
「これから何かするみたいよ」など
興味と期待を持てるよう、そっと耳打ちします
ここで「ちゃんと聞きなさい」
「静かにしなさい」と言えば、
子どもは「注意されたこと」に気持ちが向き、
かえって話が入らなくなります
そもそも、保育士は話を聞いてもらう立場ですから、
子どもの興味が湧くような話をするようにしたいですね
👉ここでの「ちゃんと」は、
「お話を聞いてみよう」です
🔴午睡(4歳児)の場面で──
私は、布団に入った時点で、
子どもは「寝たい」と思っているのだと受け止めます
ですが、何らかの事情で寝付けくて、
手近にある布団をいじっているのだと推察します
そっと隣につきつつ、
「今日は◯◯して楽しそうだったねー」
「昼寝でも、楽しい夢が見られるといいねー」
などと言葉を掛けます
大人だって、
寝たいのに、眠れない時がありますよね?
「今日は、なんか寝付けないんだな」と、
おおらかな気持ちで関わりたいですね
👉ここでの「ちゃんと」は、
「安心してね」です
🟣話し合い(5歳児)の場面で──
子どもたち同士の話し合い、
できれば、全員が意見を出した上で、
みんなの総意を形成していきたいと願うところです
とはいえ、そこはまだまだ幼児ですから、
興味はあっても自分の意見がまとまらない子もいます
・Yes/Noで答えられるクローズドクエスチョン
・自由に意見できるオープンクエスチョン
・3〜4択程度のセミクローズドクエスチョン
これらの組み合わせで、回答をアシストしていきます
たとえば「◯◯って意見があったけど…」
・あなたは、賛成(反対)?=クローズド
・あなたは、どう思う?=オープン
・あなたなら、A?B?C?=セミクローズド
というような問い掛けですね
回答があってもなくても
「考えてくれてありがとう」
と大人が応対することで、
子どもは自分が期待されていると感じることも
また頭の片隅に置いておきたいですね
あくまで、猫月ならこうするという話ですが、
あなたの関わりのヒントになれば嬉しいです
👉ここでの「ちゃんと」は、
「あなたの話を聞かせて」ですね
🎯「ちゃんと」は、“行動のイメージが難しい”言葉
大人が日常的に使う
「ちゃんと」「しっかり」「気をつけて」「もう少し」
といった言葉
これらは、
大人同士であれば文脈や経験で補完できる表現ですが、
子どもにとっては
“何を・どのくらい・どうすれば良いか” が明確ではありません
特に幼児期は、
・抽象語よりも、具体的な動作表現
・論理よりも、感覚や擬音
・指示より、共感と誘導
が届きやすいという特徴があります
“知らせる”よりも“届くように言葉を設計する”意識が大事です
・ 「テーブルとお腹を、ぴったんこ」
・ 「声を“お話し声”にしよう」
・ 「時計がここに来るまでにできるかな?」
大人が言葉を少し“設計し直す”だけで、
子どもの行動は驚くほどスムーズになります
子どもに話が通じないときは、
「言うことを聞かない」
ではなく
「行動イメージが持てていないだけ」
これは叱る理由ではなく、
“伝え方を見直すサイン”です
保育でも家庭でも、まずはこう考えてみましょう
「この言葉で、子どもは何をするイメージが湧くだろう?」
「その子にとって“動きやすい情報”になっているだろうか?」
たったこれだけで、
保育や育児の空気が少し柔らかくなります
大人の言葉が変われば、子どもの姿も変わります
『押してダメなら、引いてみよ』って言葉もありますからね
今日からほんのひと言を、少しだけ“子ども基準”に変えてみませんか?
この記事があなたの「言葉を選ぶ時間」を生み、
子どもとの関わりを少し楽に、少し楽しくする
きっかけになれば嬉しいです
次回も一緒に考えていきましょうね
▶️ 子どもと向き合うときの言葉、ちょっとだけ考えてみませんか
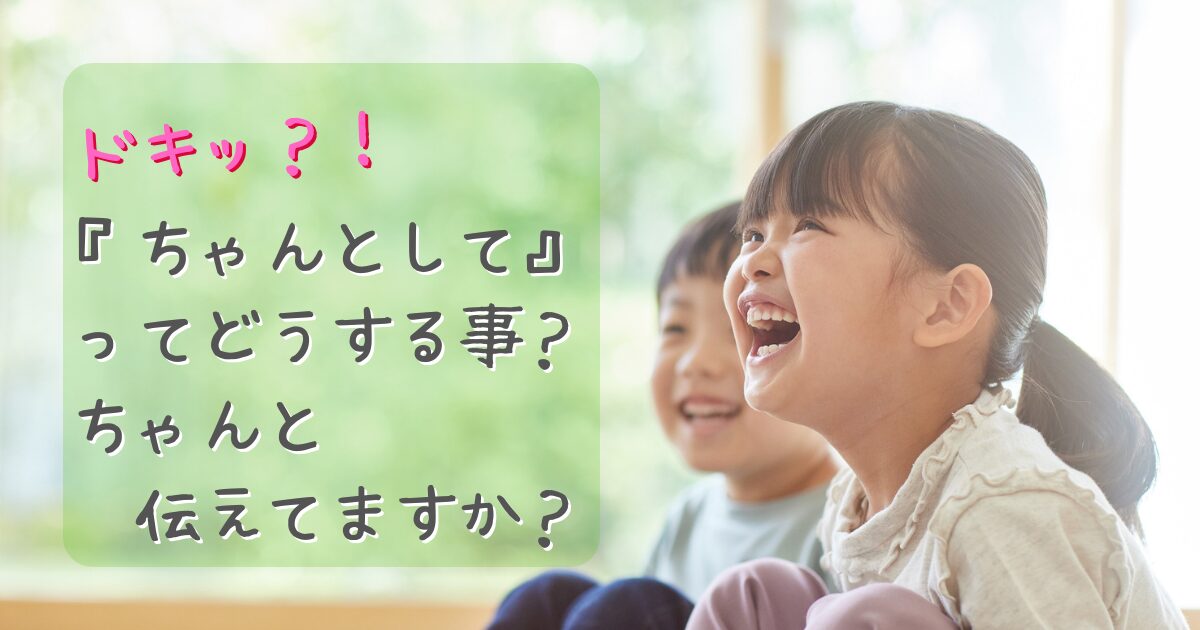

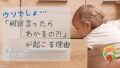

コメント