こんにゃちは、猫月です😺
先日、できたら良いは、「まだで良い」という記事を掲載しました
・ひらがなが書けた方が良い
・数がわかる方が良い
・椅子に座って過ごせる方が良い
・泳げた方が良い
・相手の気持ちを考えられる方が良い
記事中で、5つの具体例を挙げたのですが、
もう少し深掘りしていこうと思います
ということで、まずは
『相手の気持ちを考えられる方が良い』について
お話ししていきます
就学前は「事実→推測」を増やします
Q:目の前に引き出しがあります。中に何が入っているでしょう?
——「わかるわけないでしょ」と思ったあなた、
正解です(笑)
では、その引き出しが
あなたの家のクローゼットだったら?
「ここはTシャツ」といった
見当がつきますよね
つまり、推測には“手がかり(経験・情報)”が必要です
ところが私たちは、
子どもに対して似た構図の言葉掛けをしています
例えば──
「赤ちゃんが寝てるから静かに」
「ごはん残したら給食さんが悲しむよ」など
目の前で赤ちゃんが眠っていれば静かにできますが、
隣の部屋の状況や、
見えない相手の気持ちを見通すのは、
幼児には難題です
大人が“相手の気持ち”を推測できるのは、
過去の経験、
場面の情報、
それをつなぐ処理力(言語化・想像)
が揃っているからです
大人でさえ情報が足りなければ当てられない
まして幼児ならなおさらです
何かを想像して考えるためには
事実(見えたこと)
→推測(〜かもしれない)
→確かめ(どうしよう)
この順序で、道筋が増えていきます
“思いやり”はもちろん大切です
ただし就学前は、
まずどれだけ多くの事実を見つけられるかを育てます
事実が集まるほど「〜かもしれない」が生まれ、
確かめる行動につながっていきます
順を追って伸びゆく力だととらえ、
大人は過程を支える姿勢で見守っていきましょう
乳幼児期の発達段階の目安
幼児期から児童期にかけて「相手の気持ちを考える」力は、
次のような段階で発達していきます。
生後6ヶ月~1歳ごろ
身近な大人が見たものを追う
「共同注意」が始まります
他者が何に興味をもっているか気付く段階です
1歳~2歳ごろ
他人の行動目的(意図)を少し理解できます
親が指さすものを見るなど、
相手の期待がわかってきます
2歳~3歳ごろ
ごっこ遊びなどを通して
他人の“視点”を少しずつ経験していく時期です
まだ「自分の考えが相手にも同じ」と思うことが多く、
自己中心性で関わっていきます
4歳~6歳ごろ
他者にも「自分とは違う考えや気持ち」があると
気づくようになります
ここから本格的な「相手の気持ちを考える力」の土壌が育まれ、
徐々に相手の考えや感じ方を
推測できるようになっていきます
小学校(児童期)
他者の気持ちを考えて行動したり、
集団でのルールや役割を理解する
自分と相手の違いを知り、
比較したり協調したりできるようになる
「相手の気持ちを考える」力は、だんだんと育つもの
4~6歳ごろから芽生えはじめ、就学後にさらに深まります
「保育園の年長でも、まだ難しい」ということを、
大人は承知して関わる必要がありますね
「相手の気持ちを考える力」を育む関わり方
子どもが「相手の気持ち」を考える力を育むために
大人ができる効果的な関わり方は、以下のポイントが大切です
感情を言葉で表現させる
子どもと一緒に
今日のできごとや感じたことについて会話します
「あなたは面白かったんだね」
「友だちはどう感じたのかな?」と
感情を言葉にする経験を重ねていくのです
これにより自分や相手の気持ちに気づく力が育ちます
共感的な態度を大人が示す
子どもが何か伝えてきた時に
「あなたはそう考えたんだね」
「それは面白そうな発想だね」などと
気持ちに寄り添う姿勢で応じます
子どもは共感的な応答をくり返す中で、
自分の感情が尊重されていると感じ、
『友だちの考えたことも面白いかも』
『あの子はこんなことが好きなのかな』と
他者への共感力も育みやすくなります
他者の視点を考える機会を作る
絵本や遊びの中で
「このキャラクターはどう思ったかな?」や、
「もし自分がされたらどう感じる?」と対話し、
相手の立場に立って考える機会を作ります
正解・不正解ではなく、
まず想像してみることを経験していきます
模範となる行動を示す
大人が子どもに対して
思いやりのある言動を見せることが
一番の学びになります
例えば──
「ありがとう」と感謝を伝える
「ごめんなさい」と謝る
困っている人に声をかける
大人がモデルとなることで、
子どもも同じように振る舞うことを身につけていくのです
えっ?!「自分の気持ち」って何?
突然ですが!
ここで、ふたつの絵本を紹介します
『カラーモンスター きもちは なにいろ?』
作:アナ・レナス 訳:おおともたけし
版:永岡書店
『こころをなくしたかいじゅう』
作:新井洋行
版:パイ インターナショナル
『カラーモンスター』は、
気持ちを色に例えて表現しています
『こころをなくしたかいじゅう』は、
感情にはどんなものがあるかを、
主人公のオルーガが探っていく作品です
子どもは「自分の気持ち」というものを、
まだ理解するのが難しいのです
『え?自分の気持ちがわからない???』
と思われたでしょうか
子どもはまず、
生理的に“快”か“不快”かで感じたことを判断します
だから幼い頃は「いや!」を頻繁に口にするんですね
相手の気持ちを考えるためには、
まずは自分の気持ちがどんなものなのかを
自分で理解する必要があります
「自分の気持ち」を想像する機会も、
また子どもにとっては大事な成長の土壌になります
絵本を通して、
子どもと一緒に「気持ち」を考えてみてはいかがでしょうか
子どもの育ちが見える「サリーとアン」
あるところに、
サリーとアンという二人の女の子がいました
二人はままごとをしていて、
サリーは人形で遊んでいました
遊びの途中、
サリーは自分のかごに人形を寝かせ、
布で覆ってその場を離れました
その様子を見ていたアンは、
サリーのいぬ間に人形を抜き出すと、
自分のおもちゃ箱の中に隠してしまいました
そこへ何も知らないサリーが帰ってきます
Q:さて、サリーは人形で遊ぶために、
どこを探すでしょうか?
![[サリーとアンの課題]を表現した挿絵です。床にゆりかご、おもちゃ箱が置かれています。両端には二人の女の子が立っていて、一人の女の子は自分の人形を探しています](https://nekozuki-no.com/wp-content/uploads/2025/11/sarryann-1024x683.jpg)
あなただったら、
サリーはどこを探すと考えますか?
おそらくは、サリーが人形をしまった
「かごの中を探す」と答えますよね
ところが、幼児にこの問いを投げ掛けると、
多くの子は『おもちゃ箱の中』と答えるのです
それはどうしてか、わかりますか?
子どもは、アンが人形を隠したことを知っています
「人形は隠されている」という情報ですね
でもそれは「自分は知っている」ことであって、
「サリーは知らない」ことですよね
「相手の気持ちを考える」力がある子は、
「サリーは知らないはずだから、元のかごを探すよね」と
サリーの立場で想像できるのです
この「サリーとアンの課題」を投げ掛けることで、
子どもの育ちの現在地がわかる、という話です
🎯「わからない」は大事な言葉
最後に、コミュニケーションで大事なことをお伝えします
私は、子どもたちに向けて
「ありがとう」と「ごめんなさい」
という言葉が大切だよと伝えています
それと同じくらい
「わからない」も大事な言葉だと考えています
大人は経験とその場を観察する力があるので、
コミュニケーションにおいて
相手の気持ちを推察することができます
でもそれだって、100%当てるのは難しいですよね
子どもだって
「相手の気持ちを考える」ことには
挑んでいるのです
相手の表情や、声量や、態度など、
いろいろ感じながら関わっています
でも、読み間違えることもあれば、
気づけないことだってあります
相手の気持ちを考えてみた上で、
「わからない」ことだってたくさんあるのです
相手を怒らせてしまった
相手を悲しませてしまった
でも、自分の何がそうさせたのか
「わからない」
「考えたけど、わからない」
「だから、教えて欲しい」
それも大事なコミュニケーションですよね
そんな時に、大人が「こうでしょ!」と迫ってしまうと、
「わからない」を口にすることが
はばかられるようになってしまいます
子どもに「相手の気持ちを考える」ことを願うなら、
まずは大人が子どもの気持ちに立ちましょう
「何か、困った顔をしているね」
「私で良ければ一緒に考えるよ」
「そう、あなたはそう考えたのね」
「“わからない”ことに気づけたんだね」
そういう受容される対話の中で、
また子どもは気づきも増えていくのです
気持ちは目に見えないものです
相手の気持ちを知るには“感じる”力が大事です
だからこそ、大人が正解を教えるのではなく、
子どもの感覚を伸ばしていく関わりを
大切にしていきたいですね
【焦らなくても大丈夫!】
#0 できたら良いは「まだで良い」──概要
#1 できたら良いは、「まだで良い」──ひらがなの話
#2 できたら良いは、「まだで良い」──数・計算の話
#3 できたら良いは、「まだで良い」──座って聞くの話
#4 できたら良いは、「まだで良い」──水泳の話
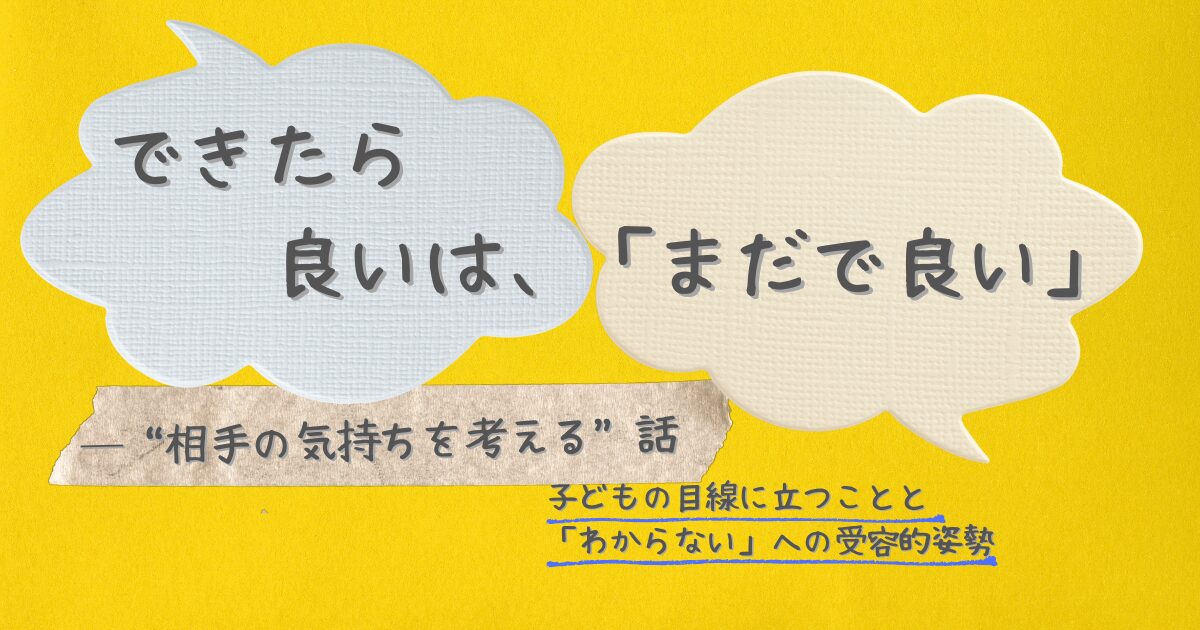
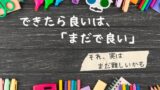


コメント