こんにゃちは、猫月です😺
保育園の仕事は、保育ばかりではありませんね
保育日誌を書く
デイリーや月案を作成する
関係機関との連絡をする
様々な事務仕事もあります

猫月さーん、
倉庫のドアが開かなくなったんですけど
教材が取り出せないので、直してくださーい

ちょっと待ってて!
今、役所からの電話に対応中だから
終わったら急いで行くよ!!
想定外の作業が発生することもありますね💦
時間には限りがありますから、
仕事は計画的に進めていく必要があります
ところで、計画的に仕事をするには、
それぞれの業務を完了させる
“時間の量”を計算する必要があります
あなたは、「クラス便りを作る」
「制作の準備をする」など
所要時間を見積もっていますか?
初めての仕事ならともかく、
経験したことのある仕事であれば
おおよその時間はわかると思います
もし計算できないのだとしたら、
それは仕事のやり方に問題があるかもしれません
そして、その状態を放置しておくと、
チームの仕事に不具合が出るかもしれませんよ
仕事の進め方といえば、
沢渡あまねさんの出番です!
今回も『職場の問題地図』(技術評論社)を参考にしながら
“仕事の所要時間の見積もり”について
考えていきましょう
▶️ 仕事で迷子になったら、この地図を読んでみましょう!
時間も予算内で仕事をする
まず初めに、「時間にも予算がある」
ということをお話ししておきます
私の職場でいえば、1日8時間労働です
つまり、与えられた時間的予算は8時間
これを超えて仕事をするのは、
「時間の赤字を出した」ということです
お金で考えたら、
予算を超えて業務を成したとしても、
それは職場に損失を出したということですよね
時間でも、それは同じです
「8時間で成果を出す」から、私の仕事には価値がある
プロとして給料をもらうということは、
金銭的にも、時間的にも、
黒字で成果を出すから報酬に繋がるのです
所要時間で迷子になる2つの背景
まず“所要時間”がわからなくなる
背景を考えてみましょう
①経験と感覚で仕事を進めている

仕事の進め方なんて感覚よ
所要時間なんて意識したことがないし…
そもそも、みんな仕事のやり方も、
所要時間も違うでしょう?
でも、そんな状態で毎日の仕事をしていたら、
どうなってしまうでしょうか
「担当者が休んだら仕事が回らない」
「人によって仕事のスピードや品質が違う」
「誰に聞いたら良いかわからない」
「後任にきちんと引き継げない」
仕事の所要時間を見積もれない職場環境は、
組織として大きな問題です…
②業務のプロセスがない
経験と感覚頼みの職場には、
“仕事のやり方=業務プロセス”がありません
結果どうにか仕事が終わりさえすれば良い
仕事のやり方がバラバラでも、
誰も問題に思わない
そもそも、同僚のやり方に興味が湧かない
みんなが自己流の仕事に満足し、
自分のやり方が正しいと信じている
人によって仕事の捉え方も、
中身も違うので、
ノウハウが組織に溜まらないまま
目先の仕事だけは回っていく
当然、
「共通の業務プロセスを定義しよう」
「仕事のやり方を改善しよう」
なんてモチベーションは働きようがありません
悲しき「3ナイ」連鎖~共通プロセスがナイ、測定できナイ、改善しようがナイ~
共通の業務プロセスがない
言い換えれば仕事を進めるための
共通の“箱”(仕事の範囲)がないので、
「仕事の所要時間を見積もる」と言われても
思考停止してしまいます
どこをどう測ったら良いのかがわからない
「ええと…この仕事って、
どこから始まって、どこが終わりなんだっけ?」
となってしまいます

仕事の始まりと終わりくらいわかるわよ…
制作なら、準備を始めて、
子どもたちができる形になったら終わりよ

それは、全員が同じ手順、時間量でできてるかな?
ムツキは理解してても園のみんなはどうだろう
誰が、どの活動に、どれだけ時間をかけているのか
測定不能、比較も不能…
これでは業務改善のしようもありません
定義できないものは、管理できない。
W・エドワーズ・デミング博士
管理できないものは、測定できない。
測定できないものは、改善できない。
博士が提唱したPDCAサイクルは有名ですね
事細かな業務マニュアルはなくとも、
せめて共通の“箱”はきちんと定義して、
時間や効率を測定できるようにしておきたいものです
所要時間を見積もれないとどうなるの?
①業務量が多い
部下に仕事をお願いしたくて、
所要時間を見積もってもらいたい上司
しかし、部下からは明確な答えが返ってこない
「とりあえず、早い方が良いから、
今日中にやってもらおう」
実態がよく分からないから、
上司の都合だけで話が進む
とりあえず、気合と根性で何とかしているから、
今回も何とかなるだろう
それが繰り返され、
どんどんと新しい仕事が積み重なり、
常にアップアップ…
園長:
「とにかく、仕事がいっぱいで余裕がないんです。
これ以上仕事を増やさないでください
または人を増やしてください!」
管理者:
「いっぱいって、どのくらい?
対応件数や対応時間を教えてもらえる?」
園長:
「……とにかく、大変なんです」
管理者:
「う~ん。それじゃ、上に大変さを説明できないよ」
現場の大変さが伝わらないのは、
所要時間や業務量を定量的に示すことができないから
結果、仕事の無限増殖を招いていくのです
②スピードが遅い
人によって、箱の捉え方も違えば、やり方も違う
そんな状態では、他人と横並びして
仕事の効率や速度を比較できません
比較対象がない
即ち「自分の仕事の効率が良いのか、悪いのか」を
相対的に判断しようがないのです
チームのメンバーの誰かが
せっかく良いノウハウを持っていても、
その人にしか通用しない
いつまでたっても
個人個人の仕事のやり方が改善されない
その結果、業務効率もスピードも上がらないままになるのです
「一時作業」と「繰り返し作業」の識別ができているか?
仕事の所要時間を見積もれるようにするには
どうすれば良いでしょうか?
まず、業務プロセスを決める必要があります
それには、共通の“箱”を定義するのです
箱があることで、
その仕事の始まりと終わりがはっきりし、
所要時間を測定できるようになります
仕事の始まりと終わりを定義する
仕事の一つ一つ箱を、
5つの要素に沿って定義してみましょう
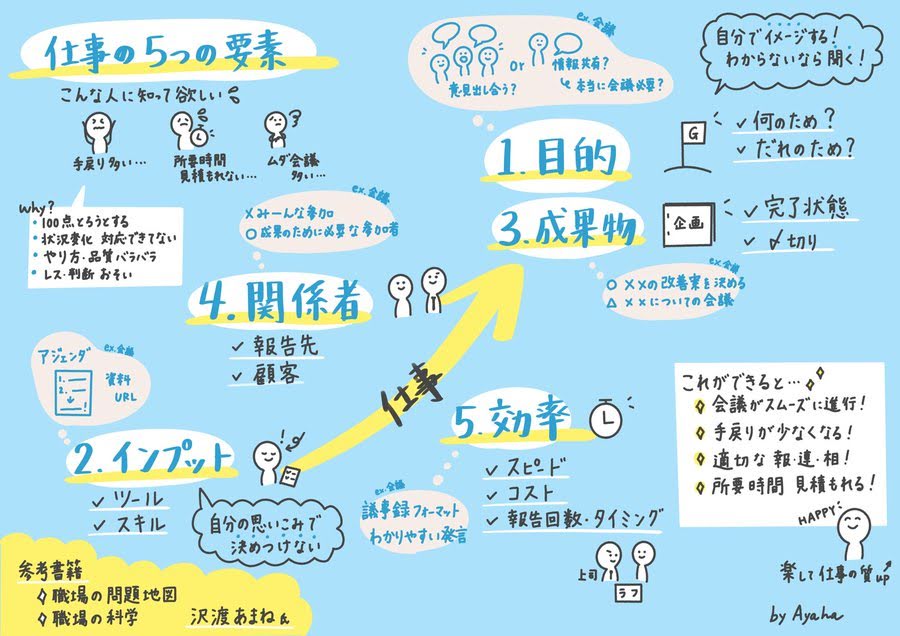
②インプット が ③成果物 に変わるまでの時間が、⑤所要時間 です
この⑤を測定するのです
このとき、その仕事が
「一時作業」か「繰り返し作業」かによって
アプローチが異なります
「一時作業」の場合(突発的なレジメ作成など)
かかった時間を実績値として記録します
そして、似たような仕事が発生したときに、
5つの要素をもとに実績所要時間を説明できるようにしておきます
「繰り返し作業」の場合(手続き、日誌、報告業務など)
作業者全員の所要時間を毎回記録し、分析します
そして、標準所要時間や目標所要時間を設定し、
優れたやり方をチーム全体のやり方に横展開するなど、
改善活動につなげます
ここで設定した標準所要時間や目標所要時間は、
「私たちは、どの仕事を、どのレベルで頑張るべきか?」
を示す、チームの指針にもなります
「松竹梅」を示せるか?
一時作業を依頼されたとき、
成果物の選択肢を相手に示せると重宝されます
「松竹梅」オプションを提案できたら理想的ですね
松竹梅は、相手のためだけならず、
自分の仕事も楽になります
例えば、私が心掛けていることで言うと
会議でレジメが必要になった場合に、
・資料のボリュームは:
B4、A4、A5、どのサイズが適量か
・資料のイメージは:
すべて事前に記載しておく?
自分で記入してもらう?
といったことを園長に諮ります
『A4サイズで、事前に記載しておいて』となれば
「1時間でラフを作成してきます」と回答できるわけです
相手のメリット
・成果物をイメージしやすい
・判断に時間がかからない
自分のメリット
・作業効率が良い
(すでに経験し、パッケージ化された作業をこなすだけ)
松竹梅を提案できるかどうかは、
一見、個人スキルの問題に思いがちです
しかし、これこそ組織の業務プロセスがあっての賜物
業務プロセスがきちんと定義されていて、
効率やスピードを測定できていて、
過去の仕事が知識化されているからこそ成せる業です
チームで取り組みましょう
そもそも、仕事を受けるたびに毎回イチから考えていたら、
残業はいつまで経っても無くなりません!
🎯“箱”をイメージすること
「仕事の量」を理解するために、
“箱”をイメージするのです
箱が大きければ、必要な時間も増えるし、
箱が小さければ、その仕事は早々に片付けられる
それがわかると、「これは今日中に終わらせられる」と
仕事の優先順位も変わりますよね
まずは、日常の仕事がどのくらいで終わるのか、
自分で測定してみてください
その日の保育日誌
1冊の連絡帳
午睡の布団上げ
測れる仕事はたくさんあるはずです
そして、それを同僚と共有する
そうすれば、「私たちに必要な時間」がわかります
私はこれを保育に応用しました
記事は一例ですが、
保育での子どもの所要時間を測って、
子どもたちに還元したのです
まずは試してみてください
やっているうちに、なれてくると思います
「彼を知り己を知れば、百戦危うからず」(孫子の兵法)
なんちゃってw
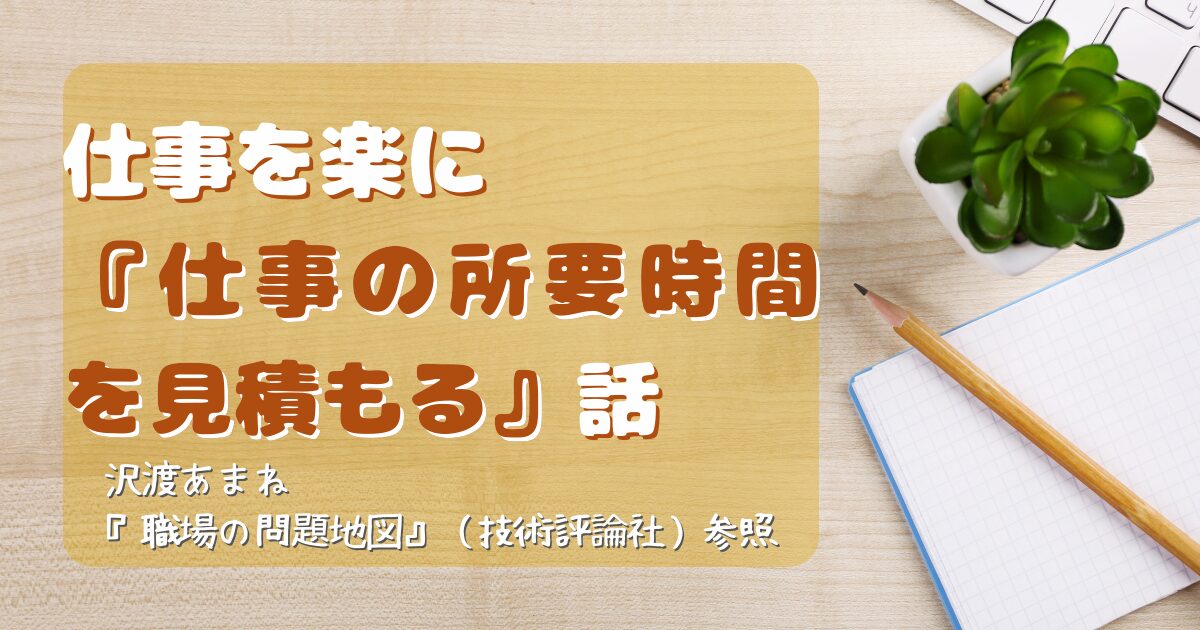
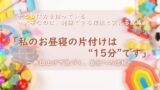


コメント