こんにゃちは、猫月です😺
このシリーズでは、
RPG風に「○○しない子」があらわれた時、どうする?
を考える記事をお届けしています
今回は、保護者からもよく相談される
「食べない子」とどう関わるか
というお悩みについて、
要点を整理しながら、猫月だったらどうする?
という内容でお話ししていきます
▶️ まずは、子どもの食べたい意欲を大事にしたいですね
Chapter8『“たべない子”があらわれた!』

【あなたが保育をしていると、
“たべない子”が現れました。どうしますか?】
たべない子にも、いろいろある
大人からすると『食べない子』に見える子にも、
いろいろな理由があると思います
どんな理由があるか、考えてみました
① 一回の食事量が少ない子
どの食品も口にしているけれど、残している
② 苦手な食材が多い子
よく食べるものと、口をつけないものがある
③ 咀嚼が弱い子
口に入れてから、なかなか飲み込めていない
④ 食事そのものが不安な子
食事の時間を嫌がる
自分から食べようとしない
子どもの食事の様子を見ていると、
なんとなくでも理由がわかってくると思います
💡その子の食事を豊かにするために
関わり方や環境を工夫すると、食べるようになることもあります
向き合い方の一例をお話ししていきます
① 一回の食事量が少ない子
少量盛りで達成感を重ねていくと、自分の適量がわかるようになります
食べ切れることで、食事への自信もついていきます
「もう少し食べてみようかな」の意欲も湧いてきますね
② 苦手意識がある子
まずは好きな物で心とお腹を満たしましょう
お腹が満たされると気持ちにも余裕が生まれます
気持ちに余裕があると、新しい食材への挑戦もしやすくなる
満たした上で「これも、一口食べてみない?」と誘ってみましょう
③ 咀嚼が弱い子
咀嚼の弱い子には、食材を細かく刻みがちですが、
それだと「噛む」動作が不足してしまいます
棒状の茹で野菜やパンなどで前歯を使った“噛みちぎり”を経験し、
顎の力を育てる経験を重ねたいですね
★誤嚥防止のため、食後の口内チェックは大切です
④ 食事そのものが不安な子
食事は、本能的に警戒心が働く場面
家庭との雰囲気や、食文化の違いに警戒しているのかも…
安心できる環境、大人の受容的な見守りで
「ここで食べても大丈夫」という実感を持ってもらいたいです
大人が食べたことを喜ぶと、「喜んでもらえた」“貢献感”から、
食べようという動機が持てるようにもなっていきます
これが“正解”というわけではないですが、
私が保育園で出会ってきた子たちは、
食べる量が増えてきましたよ♪
🎯 「食事」は、お腹も心も満たす時間
「食べない」と大人としては心配ですよね
でも、安心感や達成感が積み重なれば、自然と食べられるようになります
「いつかはたくさん食べらるようになるよね」と
寛容な眼差しで見守っていると、
いつの間にかその子は大人のように食べている、
なんてよくある話です
お腹も心も満たす時間にしていきましょう
👈Chapter7『“すわっていられない子”があらわれた!』
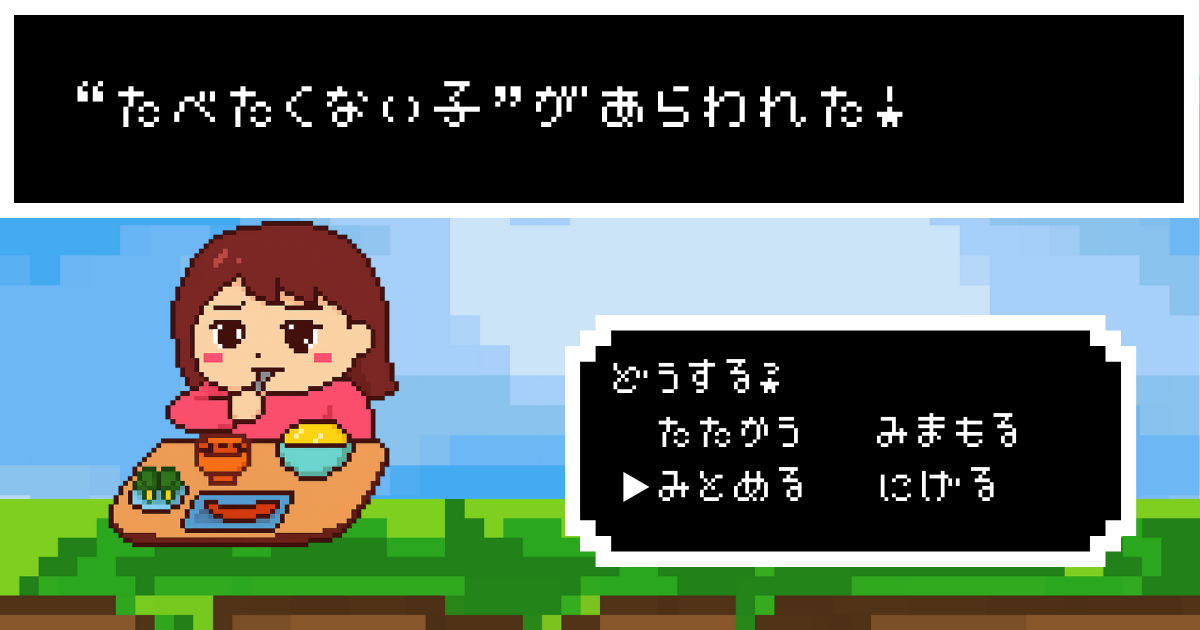


コメント