こんにゃちは、猫月です😺
子どもとのやりとりの中で
「この子のコミュニケーション、なんか心配だな・・・」
という悩みを感じたことはありませんか?

なかなか大人の話を聞いてくれなかったり、
自分の気持ちを話してくれない子がいたり…
まぁ、子どもって気ままなものよねー

子どもは確かに気ままではあるけれど、
大人の話し方で聞こうとしてもらえることもあるし、
実は子ども自身は気持ちを表現しているのかもよ?
子どもたちとの日々の保育の中で
私はよく「話してくれない子」や「話を聞いていない子」に出会います
そんな時、大人はつい
「お口で言おうね」とか「しっかり聞いてね」と
声を掛けがちです
でも、子どもの姿を見ていると
”話せない”心情であったり、
“聞こえていない”状況であったりすることも
少なくないような気がしています
本当に必要なのは、
“話すこと”や“聞くこと”ではなく、
“伝わること”なのではないでしょうか
保育の現場では、言葉にならない想いや、
言葉では表しきれない感情に出会ったとき
大人はどのように子どもと向き合えば良いのでしょうか
今回は、そんな「言葉以外のコミュニケーション」に焦点を当てて
私の体験をもとに綴ってみたいと思います
話さなくても、通じる大人がいる
時々、保育園では”話さない子”がいます
理由はその子によって様々ですが
環境によるものであったり、
自分で“ここでは喋らない”と決めていたりします
そんな、とある子と過ごした時間のお話です
“しゃべらない子”にも、ちゃんと世界がある
4歳で入園したLくんは、
数字や車のナンバーが好きな男の子でした
一方で、集団行動は苦手で、
ドッジボールの時間になると園庭の隅に隠れてしまうような姿もありました
保育園ではほとんど喋らず、
担任は「やりたくない」が言えるように働きかけていましたが、
言葉が出ることはほとんどありませんでした
通じる人には、言葉がなくても通じる
そんなLくんは高速道路が大好きで、
遅番保育の時間になると自分の頭の中にある高速道路の地図を描いて遊んでいました
私はその絵を見ながら、
「これは三郷JCTかな?だったらこっちは常磐道だね」などと声をかけていました
彼から返事はないものの
Lくんの中では「この人には話が通じる」と感じてくれていたようです
ある日、彼は自分で描いた紙を私に見せに来ました
お母さんによると、それは鳥栖JCTだそうです
「おお、日本を代表するクローバー型のジャンクションじゃん」と伝えると、
それ以降、Lくんは私とは少しずつ会話をするようになりました
“この人とはしゃべれる”という安心感
自宅と同じくらいお喋りするようになってきたLくん
首都高の地図を描きながら
「ここって何ランプだっけ?」と聞いてくるようになりました
卒園後も妹のお迎えに来るたびに
私と会話をしてから帰るのが日課でした
妹の卒園式の日には、私宛に手紙を渡してくれました
担任でもなかった私との関係の中で、
Lくんは“話が通じる大人”がいる経験を重ねていたのです
言葉がなくても、ちゃんと“話している”
乳児とのコミュニケーションは
まだ“話せない”ことを前提に言葉を掛けていきます
“まだ話せない”子は、話していないわけじゃない
乳児クラスでは、言葉の出ない子や喃語の子どもたちと向き合う日々です
大人は指差しや泣き声、声のトーン、目線など、
あらゆる情報を受け取りながら、その子の気持ちを感じ取ろうとします
わからなければ、謝る。それも立派な対話
それでも当たらないことは多く、
「これはわからないな…」という場面もあります
私はそんな時は素直に、
「ごめんね、わからないんだ」と謝ります
すると子どもは『すんっ』と泣き止むこともあります
“わかってくれようとした”と、子どもは感じているのかもしれません
泣くことは、“伝えたい”表現のひとつ
「大丈夫、大丈夫」「泣かない泣かない」と言われても、
子どもにとっては何も大丈夫ではありません
大丈夫だと思っているなら、そもそも泣いていないのですから(笑)
私は「そりゃ、ママがいいよねぇ」「泣きたいだけ泣いてね」と伝えます
不思議と、その方が落ち着く子が多いものです
『今は泣きたいんだ!』というのも、
子どもが伝えたいことなんじゃないでしょうか
だから「存分に泣いてね」と大人に受け止められたことは
その子にとっては“思いが伝わった”体験だと思うのです
“いらない”を伝えるにも、言葉はいらない
小さな子が不意におもちゃを投げるのは、
機嫌が悪いとか捨てようとかいうのではなく、
ただ「もういらない」からかもしれません
そんな姿を見て「投げないで」と嗜めるより、
「もういらないのね。じゃあしまっておこうね」と返すことで、
その子の気持ちは“伝わった”経験として積み重なっていきます
子どもたちに学ぶ“伝え合う力”
うちの保育園にも様々な国籍の子どもが通ってきますが
母国語の異なる子ども同士が、
なぜか遊びで通じ合っている姿も見られます
伝え合うって、たぶんそういうことなんだと思います
Don’t think. Feel!🐉ってことですかね(笑)
“言葉だけじゃ通じない”体験を通して
ここでは、私が受講した研修の体験から
“言葉で伝える”ことついて気づいたことをお話ししていきます
目隠しで歩くだけ、のはずが・・・
その研修では、ペアになって「目的地まで行って帰ってくる」ワークがありました
条件は、一人が目隠しをして、もう一人は言葉だけで誘導する、というだけ
でも、これがとにかく難しい・・・
「右に手すりがあります」と言われても、
どれだけ振り向いて良いのかわからない
「30cmくらい先に段差があります」と言われても、
30cmを感じるのが難しいのです
言葉だけの誘導では、右も前も距離感も全然通じませんでした
「こんなに通じないのか」と痛感した体験でした
「言葉があれば伝えられる」は、思い込みだった
別の研修で講師から「はっぱをかいてください」と言われました
あなたなら、どんなはっぱをかきますか?
私はノートの端に葉っぱを一枚描きました
受講生がみんな顔を上げたところへ、
講師が笑いながら声を掛けます
「平仮名で書いた人はいらっしゃいますか?」
そうか、“はっぱ”って言葉だけでは意図は伝わらないんだ!
伝えるって、“相手に理解してもらう”こと
伝えるというのは、こちらの思いや考えを言葉にしても、
相手に共有してもらわないと成立しないんです
だから、言葉だけを増やしても伝わらない
「伝わって欲しいなら、相手がわかるように工夫する」
コミュニケーションで大事なことのひとつを
これらの研修を通して、そう実感しました
工夫できるのは“伝えたい側”
これは、保育でも同じだと思います
子どもになかなか伝わらないとイライラする気持ちはわかります
でも「何度言ったらわかるの!」ではなく、
「伝え方を変えてみようか?」と考えることが、
子どもに伝わるために必要なのではないでしょうか
“話を聞かせる”じゃなく、“聞きたくなる話し方”を
右から左に、じゃなく“上を通過している”
集団に向けて一所懸命に話しても、
子どもがまったく保育士を見ていないことがあります
そんな時に「先生のお話を聞いてね」と声を掛けても
子どもたちにはなかなか響いていません
子どもが話を聞いていないと感じたとき、
実は“大人の話が、頭の上を通過している”のではないでしょうか
子どもたちは、当事者だと思っていないのです
子どもに伝えたいなら、“聞きたくなる話し方”を
工藤勇一先生は
『お客に私の話を聞きなさい!なんていう社会人はいませんよね』という例をあげて、
「学生は教師の話を聞くもの」ではなく
「学生が聴きたくなる話をするのが教員の責任」と説かれています
この話は、保育の場でもまさにその通りです
聴きたくなるような話をすれば
子どもたちはこちらに耳を向けてくれます
“あなたに話し掛けます”と、まず知らせる
私は子どもに話しかけるとき、
まず「ピンポンパンポーン」と呼びかけます
“あなたに話し掛けますよ”の合図です
そして「これから3つのことを話します」と数を示して話します
予告と整理こそが“聞く体勢”を作る第一歩です
“聞いてもらえる話し方”は、保育士の技術
話す側の意識次第で、
子どもはちゃんと話に興味を示してくれます
その積み重ねがあればこそ
「あ、今は話を聞くときだ」という気持ちも持ってくれます
“聞かせる”のではなく、まずは“聞いてもらえる話し方”を意識することが大切です
“伝わる”って、どういうことなんだろう
私の過去の体験を通して
“伝わる”について考えていきましょう
言葉がなくても、想いは通じる
保育園には、いろいろな子どもが通ってきます
そして保護者の方々も、それぞれ異なる背景を持っています
以前、私が担任していたお子さんの保護者は
ご両親ともに聾唖(ろうあ)者でした
私たちは手話が使えなかったため、細かいやりとりは筆談で行い、
日常的なやりとりは、読唇術を使ってくださっていました
お互いの方法は違っても、
「伝えよう」「受け取ろう」という姿勢があれば、関係は築ける
この経験は、私の中で強く残っているもののひとつです
子ども同士の“ことばにならない会話”
2歳児のMちゃんには、場面緘黙のような傾向がありました
入園当初は、声を発することもなく、ただ静かに涙を流す日々
大人の言葉に反応はあっても、自分の気持ちを表すことができず、
担任もどう関わっていこうか戸惑っている様子でした
そんな中、Hちゃんが途中入園してきます
Hちゃんも言葉の発達は幼く、言葉数は少ない子でした
ただHちゃんは朗らかで、Mちゃんの隣でニコニコしていると
Mちゃんの表情も徐々にほぐれてきたのです
時にHちゃんは、Mちゃんの気持ちを感じ取って、
大人に「〇〇したいんじゃない?」と代弁してくれることも
ふたりの間には、言葉のいらない“会話”がありました
“伝えようとする気持ち”が、人を動かす
これは私が、成人の障害者施設で支援員をしていたときのことです
担当していたFさんは重複障害を持ち、歩行も発語もできない方でした
ただし、電動車椅子を自分で操作することができ、移動はある程度自立されていました
同じ送迎バスを利用していたNさんは、てんかんの持病がありました
ある日、Fさんがいつものようにバスに向かっている途中、
突然車椅子を止めて、私の顔を見て首を振ったのです
その視線の先には、立ったまま発作を起こしているNさんの姿がありました
二人は会話をしたわけではありません
でも、FさんはNさんの異変を感じ取り、
それを私に“伝えよう”としたのです
その場のやり取りに言葉はなかったけれど、
“伝わる”関わり方があったのです
走り回るあの子も、きっと“伝えている”
保育の中で、大人はつい「お口で言ってね」「ちゃんと話してね」と求めてしまいがちです
でも、子どもたちは実にさまざまな“表現”を使っています
・沈黙で訴える子
・走り回って表現する子
・喜怒哀楽よりも、“快・不快”の感覚で行動する子
“話す”という表現に収まらない子どもたちの発信を
大人はどこまで感じ取れているでしょうか
思い返せば、私自身もそんな子でした
「ドラえもん」を見ていて、のび太が失敗するたびに感情がざわついて、
なぜか部屋の中を走り回らずにはいられなかったんです
今にして思えば、あれは
“言葉にならない感情”を、身体で表現していたんだなと思います
だからこそ、保育の現場で走り回る子どもたちに、
一律に「部屋では歩きましょう」とは言えません
まずは“走って表している”気持ちに寄り添って、
そのうえで「その気持ちは、こう伝えたらもっと伝わるよ」と
知らせていくことが大事だと思うのです
“伝わる”経験が、“話せる”力につながっていく
言葉で伝えられることはもちろん大切です。
でも、その言葉を身につけていくためにも、まず必要なのは――
「自分の気持ちは、伝えてようとしていいんだ」
「伝えようとしたことは、誰かに届くんだ」
そう感じられる経験の積み重ねです
“話せる”ことより、“伝わる”こと
そのあたたかな経験の積み重ねが、
子どもたちの未来の“ことば”を育てていくと
私は信じています
最後までお読みいただき、
ありがとうございました
子どもが「言葉で伝える」ようになる前に、
私たち大人は、
子どもが日々どれだけの気持ちを“言葉以外”で伝えているかに、
気づけているでしょうか
目線、動き、沈黙、涙、笑顔、そして走り回る背中
それらすべてが、その子なりの“伝えたい”のサインなのだと思います
私たち保育者は、
「話すことができるようになる」ことだけを目指すのではなく、
“今、伝えてくれていること”に耳を澄ませ、
「あなたの声は、ちゃんと私に届いてるよ」と
返していける存在でありたいと思います
そんな日々の積み重ねが、
やがて子どもたちが自分の声で世界とつながっていく力になる
今日も、子どもの“声”に耳を傾けていきましょう

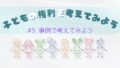

コメント