こんにゃちは、猫月です😸
今週は、子どもに関する法律を学び直しているところですが
法律と並んで「児童憲章」というものがあります
みなさんは、どんなものかご存知ですか?

“児童憲章”ってのも、子どもに関する大事なものだよね!

憲章だから、法律じゃないんですよね?

法律ではないけれど、子どもにとって大事な…
そう、大事なもの……なんだ、よね?

あらら…目がグルグルしてる――
これは、解説が必要そうですね!
今回はチャッピーに『児童憲章』がどんなものか
私たちにどんなことを求めているのか
そして、子どもたちの何を大事にしているのか
解説してもらいましょう
児童憲章って、どんなもの?

児童憲章は、1951年の“こどもの日”に制定された、
子どもの権利と福祉についての国民的な宣言なんです
法律ではない?“児童憲章”とは
戦後の混乱期、戦災孤児や浮浪児が多くいたなかで、
子どもを社会全体で守り育てていこうという理念が生まれました
児童憲章は法律ではありませんが
子どもを“守るべき存在”としてだけでなく
“人として・社会の一員として尊重する”という価値観が打ち出された点で
今でもとても重要な意味を持っています
日本の児童憲章は
国連で1959年に採択された「児童の権利宣言」より8年早く制定されており、
世界的にも先駆的な子ども憲章と評価されています
児童憲章の三原則(総則)

児童憲章には総則として三原則が書かれています
児童憲章の三原則
・児童は、人として尊ばれる
・児童は、社会の一員として重んぜられる
・児童は、よい環境の中で育てられる
この三原則は、現代でも保育・教育関係者にとって
重要な理念となっています

“社会の一員として”って考え方は、
今の“こどもまんなか”にも通じていますね
保育とのつながり

三原則でいう“よい環境”って、大人が思う“安全”だけではなくて、
子どもが安心できるかどうかということも含まれていますよね

あと、“よい環境”の話とは少し違うかもだけど……
“転ばぬ先の杖”よりも、“七転び八起き”できる力を育てるって考え方も、
最近よく耳にするよね

それはつまり、“安全に失敗できる環境”をどうつくるか、ってことですね
子どもが挑戦したり、間違えたり、泣いたり怒ったりすることも、
ちゃんと大人に受け止められる場所が“よい環境”なのだと思われます

子どもの感情や主張を、
“社会を構成する意見”として扱うことが大事ってことですね

たとえば、“ルールを一緒に考える”とか
“沈黙も意思のひとつとして尊重する”ような姿勢が
それに当たります
ルールといえば、以前こんな記事を書いたことがあります
子どもと“ルールを一緒につくる”というのは
まさに“社会の一員”として扱うってことだと思います
児童憲章の理念を学ぶと
こうして実際の保育の中でつながってくるんだな、と
あらためて感じますね
さぁ、これで「子どもの権利条約」「児童福祉法」「こども基本法」「児童憲章」という
子どもに関する法律などを学んできました
ところで、家庭や保育などで
子どもとの向き合い方にどう繋がっていくのか
次回は、具体的な子どもの姿を想定しながら
一緒に考えてきたいと思います



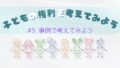
コメント