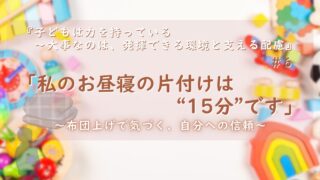 やってみたよ!こんな保育
やってみたよ!こんな保育 子どもは力を持っている─大事なのは、発揮できる環境と支える配慮 #6
寝起きの個人差がある子どもたち。そこで「自分が布団を片付けられる時間」を自覚してもらうことで、自分のペースをつかめたり、友だちを手伝う余裕が生まれることも。“15分”というリズムが、子どもの主体性と相互支援の芽を育てた実践例です。
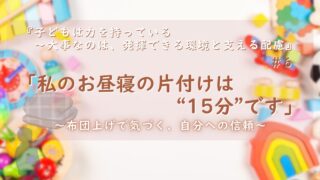 やってみたよ!こんな保育
やってみたよ!こんな保育 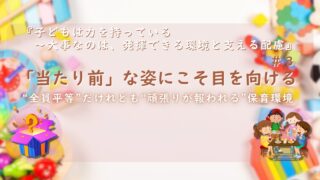 やってみたよ!こんな保育
やってみたよ!こんな保育 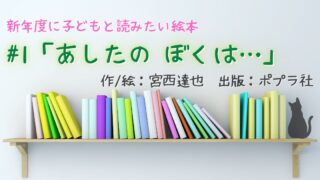 たのしい絵本とおもちゃ
たのしい絵本とおもちゃ 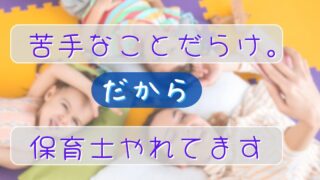 家庭でもできる、子どもとの関わり方
家庭でもできる、子どもとの関わり方  猫月のつぶやき
猫月のつぶやき 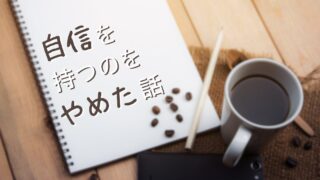 仕事をラクにしよう
仕事をラクにしよう  仕事をラクにしよう
仕事をラクにしよう 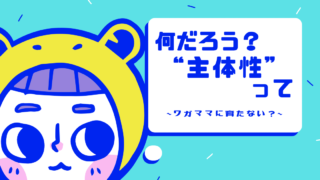 保育の考え方と指針
保育の考え方と指針