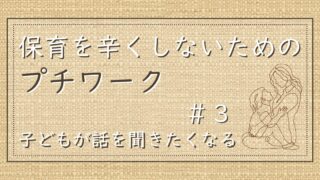 みんなのQ&A
みんなのQ&A 保育を辛くしないためのプチワーク#3 子どもが話を聞きたくなる
子どもたちへ話をする場面で─「静かに」「話を聞いて」と言いたくなること、ありますよね。そして、今日も同じことを言っている…。子どもが「話を聞きたくなる」工夫、興味ありませんか?あなたもできるようになりますよ
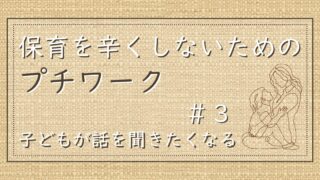 みんなのQ&A
みんなのQ&A 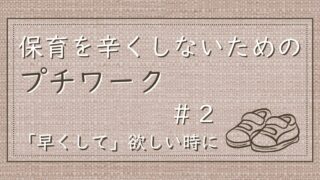 みんなのQ&A
みんなのQ&A 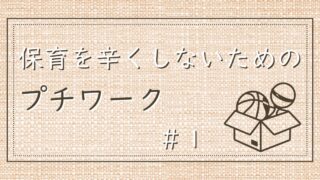 みんなのQ&A
みんなのQ&A 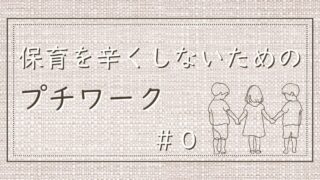 みんなのQ&A
みんなのQ&A  家庭でもできる、子どもとの関わり方
家庭でもできる、子どもとの関わり方  仕事をラクにしよう
仕事をラクにしよう 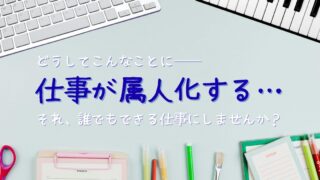 仕事をラクにしよう
仕事をラクにしよう  やってみたよ!こんな保育
やってみたよ!こんな保育 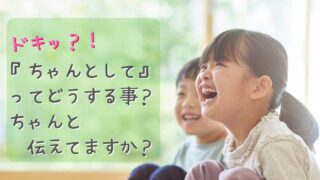 家庭でもできる、子どもとの関わり方
家庭でもできる、子どもとの関わり方 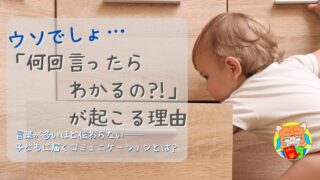 みんなのQ&A
みんなのQ&A